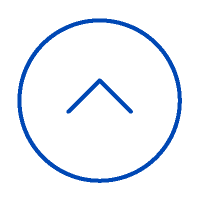-
いじめに関すること
いじめに関して、いくつかの情報をまとめておきたいと思います。
いじめの定義
まず「いじめ」とは何か、ですが、平成25年に制定されたいじめ防止対策推進法第2条によると、
「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」
となっています。被害者の主観的な感情が重要である点がポイントとなります。
これは、いじめの”深刻さ”を評価する際に、加害者が行った行為が性質が客観的に見て深刻であるかのみでは評価されないということです。
つまり、暴力行為と言葉による嫌がらせを伴ういじめが、言葉のみのいじめと比較してより深刻であると一般的に言うことはできず、いじめを受けた被害者が、どのような心理的ないし物理的苦痛を受けたか、によりいじめの深刻さは定義されるということになります。
日本の被害者への心理的影響を主体とした定義では一部のいじめ被害者を見落としてしまう可能性も指摘されています。
例えば文献1ではいじめを以下のように定義しています”Bullying is any unwanted aggressive behavior(s) by another youth or group of youths . . . that involves an observed or perceived power imbalance and is repeated multiple times or is highly likely to be repeated. Bullying may inflict harm or distress on the targeted youth including physical, psychological, social, or educational harm.”
「いじめとは、他の青少年または青少年グループによる、観察された、または知覚された力関係の不均衡を伴う、望まれない攻撃的な行動であり、複数回繰り返されるか、またはその可能性が高いものである。いじめは、対象となる青少年に身体的、心理的、社会的、教育的な被害を含め、被害や苦痛を与える可能性がある」とされています。
ポイントは、「観察された」「可能性がある」との記載が入っている点で、いじめを受けたすべての青少年が、いじめによってどのような被害や苦痛を受けたかをすぐに特定したり、表現することができるわけではないことがありうるということです。
例えば、神経発達症児は、自分がいじめられたりからかわれたりしても、いじめであることを理解できず、将来的にはそれが繰り返されることで重大な結末を招く可能性があるものの、現時点では大きな苦痛を主観的に感じているとは限らないということです。このようなケースもいじめと定義すべきとされています。ですので、被害者の捉え方のみがいじめを定義する要件ではないとされています。
いじめの早期発見
いじめ被害者の心理的苦痛をきちんとアセスメントすることができないと、教師は潜在的ないじめの存在を見落とす危険もあります。
文献2によるとオーストラリアの8歳から16歳までの女子913人、男子755人のうち、約半数の回答者(682人)が、過去 12 ヶ月間に少なくとも 1 回はいじめられたことがあると報告しました。
このうち、教師に助けを求めたのは男子の41.1%、女子の35.6%でした。
日本での調査結果では、いじめ発見のきっかけとして、教職員が発見した割合が約13%、本人が訴えたのは約18%、アンケート結果が約52%、保護者からの訴えが約10%となっています(平成30年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査より)。
つまり、いじめを受けても教師に助けを求めない児童生徒の割合の方が大きいということになります。
これについては、児童生徒の教師への信頼度などにより個人差はあるでしょう。普段から相談しやすい体制作りが重要であるということになります。
アンケートで明らかになる割合が過半数であり。文科省の作成した「いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例」では、「各学期に1回以上、無記名でいじめに特化したアンケートを行う」こととなっています(それを忠実に反映した学校いじめ防止基本方針はあまりないようです。だいたい年に2回とかのところが多いようです)。
保護者への定期的なアンケート実施も必要と思われます
いじめの被害者、加害者の割合
日本での小学校から高校までのいじめ認知件数は平成30年度で年間約54万件となっていますが、これはのべ件数ですので、実際に被害を受けた児童生徒の割合はわかりません。
アメリカでの年齢層が若干異なる4つの全国調査の結果(文献1)によると、National Crime Victimization Survey では、2011年に12歳から18歳の28%が学校でいじめを受けたことがあると回答しています。高校生を対象としたYouth Risk Behavior Surveyでは、2011年には20%の生徒が前年に学校の敷地内でいじめを受けたことがあると報告しています。
The Health Behaviour in School-aged Childrenは、5年生から高校1年までの児童生徒を対象とし、2009~2010年には、28%の児童生徒が過去2カ月間に少なくとも1回学校でいじめを受けたことがあり、11%の児童生徒がこの期間に月に2~3回以上いじめを受けたことがあると報告しています。
2歳から17歳までを対象とした養育者と児童生徒を対象とした全国電話調査では、13パーセントの子どもたちが身体的ないじめを受け、20パーセントの子どもたちが前年にいじめられたり、感情的ないじめを受けたりしたことがあることがわかりました。
アメリカと日本では状況は異なるかもしれませんが、日本がアメリカと同じ状況であり、仮に年間のいじめ被害率が20%とすると、日本での年間いじめ発生件数は小学校から高校までの児童生徒数を1250万人とすると、少なくとも250万件と推計されることとなります。
人種的問題などの背景の違いはありますが、潜在的ないじめ発生件数はもっと多い可能性があることに注意を要します。
一方、いじめに関して、第一群を、他人をいじめているが、自分自身はいじめられていない群(被害者)、第二群を、いじめられているが、他の人をいじめていない群(加害者)、第三群を、自分自身がいじめられているだけでなく、他の児童生徒もいじめている群(被害者であり加害者でもある)とすると、いじめに月に 2~3 回以上関与していた小学3 年生から 高校3年生を対象とした研究では、第一群が全生徒の 13%(被害者)、第2群が4%(加害者)、第3群が3%(被害者であり加害者でもある)との調査結果が報告されています(文献1)。
単なる加害者と同じくらいの割合で加害者かつ被害者も存在する可能性があることに注意を要します。
いじめの態様
どのようないじめが認知されているかについて、文科省平成30年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査より引用すると、「冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる」が62.7%(いじめ全体に占める割合)、「仲間はずれ,集団による無視をされる」が13.6%、「軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする」が21.4%、「ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする」が5.5%、「金品をたかられる」が1.0%、「金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする」が5.5%、「嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする」が7.8%、「パソコンや携帯電話等で,ひぼう・中傷や嫌なことをされる」が3.0%などとなっています。
海外のデータでは、12-18歳におけるネットいじめ被害を受ける割合が生徒全体の9%(いじめに占める割合ではなく、生徒全体に占める割合)との報告もあり、悪い噂を流す(18%)、悪口(18%)に次いで3番目に多い態様であったとの報告(文献1)もあり、海外では生徒の10人に1人がネットいじめの被害を受けているとの報告(2014年)もあり注意を要します。いじめの加害者の心理と加害者のリスク
いじめ加害者になる心理的背景としては、一般化は困難であるにしても、以下のような状況は想定すべきでしょう。
加害者における家庭環境における問題や未熟な防衛機制の発動しやすい状況など、学校内外での抑圧された状況が、心理的な代償として、被害者をターゲットとするいじめにつながると理解できる場合があります。
このあたりはいじめ加害者の保護者と面談の際、考慮すべき状況と思われます。
またいじめ加害者のその後の経過として、中学時代にいじめ加害者となると、成人になってから3つ以上の犯罪歴を持つ可能性が4倍になることや、後に犯罪に巻き込まれるリスクが高いことがわかっています。
また中学生でいじめ加害者となることは、その後の他人へのセクシュアル・ハラスメントやデート・バイオレンスの加害者となるリスクが高いことがわかっています(文献1)。
このようなことから、被害者のみならず、加害者へのケアも重要であることがわかります。単なる加害者に対する注意や叱責、懲罰によるいじめの抑圧は、さらに加害者の抱える心理的問題を悪化させる可能性があり、問題行動の修正のための肯定的なモデルが提案されていないため、最小限の効果しかないと言われています(文献3)
いじめへの対応について
いじめにどう対応すべきか、文科省の「いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例」によれば、
*いじめられた生徒又はその保護者への対応
・ 生徒から,事実関係の聴き取りを行う。
・ 生徒や保護者に「最後まで守り抜くこと」や「秘密を守ること」をはっきりと伝える。
・ 生徒の個人情報の取扱い等,プライバシーには十分に留意する。
・ 事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報は,家庭訪問等で速やかに保護者に伝える(即日対応)。
・ 生徒にとって信頼できる友人や教職員,家族等と連携して支える。
・ 安心して学習に取り組むことができるよう,必要に応じて別室での学習を提案する。
・ 状況に応じて,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの協力を得る。
・ 謝罪や事後の行動観察の結果,いじめが解消したと思われる場合でも,見守りは継続する。
* いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
・ 生徒から事実関係の聴き取りを行う。
・ いじめとして認知した場合,組織で速やかに対応し,謝罪の指導を行う。
・ 聴き取った内容を速やかに保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解を得る。
・ 保護者と連携した適切な対応ができるよう協力を求めるとともに,継続的な助言を行う。
・ 組織として毅然とした指導を行い,いじめは絶対に許されない行為であることを理解させる。
・ 生徒が抱える問題にも目を向け,いじめを繰り返さないよう継続的に指導・支援する。
* いじめが起きた集団への働きかけ
・ 知らなかった生徒や傍観していた生徒に対しても,自分の問題として捉えるように指導する。
・ いじめをやめさせることはできなくても,誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
・ はやしたてたり,同調したりする行為は,いじめに加担する行為であることを理解させる。
・ 教育活動全体を通して,いじめは絶対に許されない行為であり,根絶しなければならないという態度を育む。などとなっています。
実際にどのような対応がなされているかですが、文科省平成30年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査によれば、「いじめられた児童生徒への特別な対応」(特別な対応と書いてありますので、上記のいじめられた生徒又はその保護者への対応以外の対応と思われます)としてはは「スクールカウンセラー等の相談員が継続的にカウンセリングを行う」が3.2%、「別室を提供したり,常時教職員が付くなどして心身の安全を確保」が4.0%、「緊急避難としての欠席」が0.2%、「学級担任や他の教職員等が家庭訪問を実施」が11.3%、「学級替え」が0.1%、「当該いじめについて,教育委員会と連携して対応」が2.9%、「児童相談所等の関係機関と連携した対応(サポートチームなども含む)」が0.3%など(複数回答可)となっています。続いて、「いじめる児童生徒への特別な対応」としては、「スクールカウンセラー等の相談員がカウンセリングを行う」が1.8%、「校長,教頭が指導」が4.8%、「別室指導」が11.3%、「学級替え」が0.1%、「退学・転学」が0.1%、「停学」が0.1%、「出席停止」は全国で1名(中学校1件)のみ、「自宅学習・自宅謹慎」(出席停止との違いがいまいちわかりませんが)が0.2%、「訓告」が0.1%、「保護者への報告」が45.6%、「いじめられた児童生徒やその保護者に対する謝罪の指導」が43.4%、「警察等の刑事司法機関等との連携」は0.2%、「児童相談所等の福祉機関等との連携」が0.2%、「病院等の医療機関等との連携」が0.1%、「地域の人材や団体等との連携」が0.1%などとなっています(0.1%で500件程度)。
いじめに対する対応として、推奨されない方法が存在します。文献1によれば、いじめをした生徒を自動的に停学にするゼロ・トレランス・ポリシーは推奨されません。
またいじめをする生徒を一緒にグループ化することは、攻撃性を高め、いじめを悪化させる可能性があります。
また簡潔な集会や1日だけの啓発キャンペーンは、児童生徒に対する持続的な教育効果という点では、ほとんど効果がないと言われています。
またいじめ対策としては、傍観者をいかに仲裁者ないしシェルターのような存在にするかが重要であるとの議論もあります(文献4)。
これは教師の介入の契機をつくるため、およびたとえ中立的な存在であっても(友人とまでは言えなくても)、被害者を孤立させない仲間の存在があることにより、いじめによる心理的苦痛の軽減効果が大きいことを示唆する研究結果が存在していることによります。
文献1によれば、オンライン実験により、オンラインの活動から排除された若者について、無作為に未知の仲間とのインスタント メッセージのやり取りを行う群と、孤独なコンピューター ゲームをプレイする群とに割り付けしたところ、心理的苦痛からの回復は、孤独なコンピュータゲームをプレイするよりも、未知の仲間と対話する機会を持っていた人のためにはるかに迅速であったことが報告されています。これらの知見は、中立的な社会的交流でさえも、いじめられた後の心理的苦痛の回復に有用である可能性があることを示唆するものです。
したがって、教室における傍観者をいかに積極的に関わりうる存在にするかは重要といえます。
教師らの介入により、どの程度いじめの軽減効果があるかについては、文献2によると、いじめ被害者223名へのアンケートにより、7割近い児童生徒がいじめがなくなった(29%)ないし減少した(39%)と報告しています。
悪化したと答えたのは全体の7.6%でした。
このように教師の介入により大半が改善していることから、まずはいじめを教師が知るところとし、教師が介入を行うことが重要と言えます。
また教師はいじめを認知した場合には速やかに介入することが求められます。文献3によれば、教師がいじめを無視したり矮小化したりする場合、あるいは教師の介入の欠如を生徒がいじめを暗黙のうちに受け入れていると解釈する場合、攻撃的な行動が増える可能性が高くなるとされています。
また被害を受けた生徒は今後いじめを報告することを躊躇し、いじめを観察した生徒は介入したり助けを求めたりする意欲が減退すると感じることがあります。
教師が介入して、教師はいじめは受け入れられないことを伝えると、その結果、生徒はこの種の行動を正当化しようとする傾向が少なくなります。
また、いじめは放置すればするほどエスカレートする可能性も指摘されています(文献4)。早期介入が重要といえます。
教師の介入手法としては大まかに3つの戦略があるとされます。
第一は,加害者に対する懲罰戦略(指導,叱責、除名など)です。
しかし先に述べたように、この方法は社会的行動の修正のための肯定的なモデルが提案されないと、効果が乏しいものとなります。また加害者の心理的ケア(特に未熟な防衛機制が関与していると考えうる場合)が置き去りになってしまうと、根本的問題の解決にはなりません。
第二の戦略は、被害者や加害者に向けられた個別の支援であり、心理的に支援し、被害を受けた生徒への共感を高めることです。
第三の戦略は、生徒間の協力を促進し、保護者や他の専門家の支援を得て、クラスのすべての生徒を巻き込む支援協力的介入になります。
文科省の「いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例」では、加害者の保護者とも連携し、より効果的な加害者への教育的介入を模索する方向性が提示してあります。
この際、加害者の保護者の加害生徒への関わり方、家庭環境などが加害行為の背景要因として存在していないかをアセスメントすることは重要と思われます。実際には平成30年の文科省の報告では、先にみたように、加害者の保護者に対して報告などを行ったケースは全体の45.6%とされており、保護者との連携は半数以下となっている現状があり、今後の課題と思われます。
いじめが集団で行われている場合の対処は困難度が高いと言われていますが、以下のような方法が提案されています(文献2)
第1にサポートグループ法とよばれる方法があります。
これは、まず被害者にインタビューを行い、いじめの影響を受けた経緯や加害者が誰であるかなどの詳細な知識を収集します。
その後、この知識を加害者らと共有し、被害者をサポートし、加害者にも同じように影響を与えることを期待されている生徒を含む会議で共有し、加害者集団の問題意識の自覚と行動変容を期待するものです。
第2に共有懸念法(Method of Shared Concern)、またはPikas法として知られる方法があります。
この方法では、加害者である疑いのある生徒との一対一の面談に始まり、ついで被害者との面談が行われ、その後、加害者である疑いのあるすべての生徒との面談が行われ、話し合いによるいじめ解決策となりうる積極的な提案を考案し、可能であれば、被害者を含む最終的なグループ面談で解決策について合意するという包括的なアプローチになります。
いじめ防止対策推進法の施行に伴い、年々認知されるいじめ件数が増加し、現場の先生方のご負担は増えていきますが、先生方の心身の健康を保持しながら、包括的かつ効果的ないじめ対策が進むことが期待されます。
引用文献
1)National Research Council 2014. Building Capacity to Reduce Bullying: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18762.
2)Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2338; doi:10.3390/ijerph17072338
3)De Luca L, Nocentini A and Menesini E (2019) The Teacher’s Role in Preventing Bullying. Front. Psychol. 10:1830. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01830
4)荻上 チキ. いじめを生む教室 子どもを守るために知っておきたいデータと知識 (PHP新書). 株式会社PHP研究所. -
腸内細菌の話題
基礎研究レベルの話ですので、こんなお話もあるのかくらいの感じでみてください。
中枢神経疾患と腸内細菌叢の関係について2019年にNature,Cellなどの主要雑誌に論文が掲載され(文献1、文献3)、つい先日の5月にもNature誌に腸内細菌叢の論文(文献2)が掲載されたので、これはちょっと注目かもしれないということでとりあげてみました。
まず2019年のNature論文(文献1)について触れてみます。この論文では、家族性ALSにみられる変異SOD1蛋白質を発現するように遺伝子を組みこんだトランスジェニックマウスを作成し、SOD1変異ALSモデルマウス(仕様上イタリックにできないため、遺伝子表記をそのままにしています)の病態進行と腸内細菌叢の関係性が調べられました。
SOD1遺伝子変異によるALSの頻度は家族性ALS(ALS全体の5-10%程度と言われている)の中のさらに20%程度と言われています。
Blacherらはまず最初に、SOD1変異ALSモデルマウスの腸内細菌叢を各種抗菌薬を投与することにより除去しました。その結果病態進行が増悪しました。
続いて、健常マウスとALSモデルマウスの腸内細菌叢の構成細菌が調べられました。その結果、細菌の種類が異なることが明らかになりました。
11種類の細菌がモデルマウスの病態進行に影響を及ぼしうることが同定されました。
続いて、11種類の細菌を1つずつ腸内細菌叢除去モデルマウスに投与したところ、1つの細菌(Akkermansia muciniphila)が病態進行遅延をもたらしうることがわかりました。
一方、Ruminococcus torquesとParabacteroides distasonis は病態悪化をもたらしました。
Akkermansia muciniphilaの産生するニコチンアミドが中枢神経に到達し、保護的な作用を発揮するらしいことがわかりました。
研究者らはさらに、37名のALS患者について、便の遺伝子解析を行うことで腸内細菌叢を調べ、29名の健常者と比較しました。その結果、患者群と健常群とで腸内細菌叢の構成が異なることがわかりました。ALS患者においてはニコチンアミドを産生する腸内細菌が少ないことがわかりました。
以上が昨年のNatureでの報告になります。
今回のNature論文(文献2)では家族性ALSにおいて最も頻度が高い(家族性ALSの30-40%程度を占めるといわれている)C9orf72遺伝子に関連した報告です。
家族性ALSにおけるC9orf72遺伝子変異とは、第1イントロン領域のGGGGCCの6塩基繰り返し配列が過剰伸長し、この領域由来のリピート関連非ATG依存性翻訳(RAN翻訳:開始コドンを介さない非定型的な翻訳形式)によるジペプチド繰り返し転写産物(理屈では5種類のジペプチド繰り返し配列蛋白質:poly-グリシン-プロリン(GP)、poly-グリシンーアラニン(GA)、poly-グリシン-アルギニン(GR)、poly-プロリンーアルギニン(PR)、poly-プロリンーアラニン(PA))が生じるものです。
これらのうち特にpoly-GR,poly-PRの細胞毒性が注目されています。
TDP-43蛋白症の病理を呈することは他のALSと共通になります。
ハーバード大学のBurberryらは、C9orf72遺伝子を改変し、C9orf72変異ALSモデルマウスを作成しました。
これらモデルマウスでは免疫系の過剰応答がみられ、脳内炎症の亢進と運動機能の低下、生存期間の短縮などがみられました。
一方で、Broad Instituteでの全く同じ遺伝子変異を有するモデルマウスにおいては、生存期間の延長など正反対の結果が報告されており、環境要因が生存期間に影響することを示唆する結果が得られました。
環境要因が何かを調べるため、ハーバードの研究室とBroad Instituteの研究室との細菌やウイルスの環境の違いが調べられました。その結果、murine notovirusというウイルスと、Pasteurella pneumotropica, Tritrichomonas muris, Helicobacterと呼ばれる細菌がハーバードの研究室で多く存在することがわかりました。
ハーバードの研究室のモデルマウスに広域スペクトラムの抗菌薬を投与し、細菌を除去するか、もしくはBroad Instituteのモデルマウスより採取した糞便移植を行ったところ、ハーバードのモデルマウスの炎症反応が減弱しました。
研究者らは、細菌がどのように炎症をもたらすのかを調べるため、腸内細菌と共にマクロファージを単離しました。
その結果、ハーバードのマウスより採取され、腸内細菌と共に培養されたマクロファージは、Broad Instituteのマウスより採取された腸内細菌よりも、有意に多くの炎症促進性物質を放出することがわかりました。
以上の結果は、C9orf72蛋白質機能が低下すると、環境、特に腸内細菌叢が自己免疫、神経炎症、運動障害などの修飾因子となりうることを示唆するものといえます。
この結果からわかるのは、もし環境的に脆弱な一部の人々がいるとすると、腸内細菌の力もバカにならない可能性があるということでしょうか。
2019年のCell誌に掲載されたのは、自閉スペクトラム症患者由来の腸内細菌叢を無菌マウスに移植したところ、健常者からの腸内細菌叢を移植したマウスと比較してASD様行動を多く示したという報告になります(文献3)
というわけで、ALS(NCT03766321)、パーキンソン病(NCT03876327)などの神経変性疾患のみならず、精神疾患に対しても、糞便移植の臨床試験が実施中ないし予定されている昨今の状況です。
例えば、摂食障害(NCT03928808:第1相)、てんかん( NCT02889627:第2/3相)、双極性うつ病(NCT03279224:第2/3相)、統合失調症のうつ状態(NCT04001439)、自閉症スペクトラム(NCT03426826:第1相、NCT03408886:第2相、NCT03829878:第2相、 NCT04182633:第2相)、アルツハイマー型認知症(NCT03998423:第1相)など各種疾患に対する臨床試験が世界中で動いています。
ここでは詳細に触れませんが、アリゾナ大学で行われた18名の自閉症に対する糞便移植の第1相試験の長期経過については驚くべき結果が報告されています(文献4)。オープン試験なので本当かどうかは全くわかりませんが。果たして無作為割付二重盲検試験の結果はどうでるでしょうか?引用文献
1)Eran Blacher et al., Nature volume 572, pages 474–480(2019)
2)Burberry, A., Wells, M.F., Limone, F. et al. C9orf72 suppresses systemic and neural inflammation induced by gut bacteria. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2288-7
3)Cell. 2019 May 30;177(6):1600-1618.e17.
4)Sci Rep . 2019 Apr 9;9(1):5821 -
鉄は熱いうちに打てということなのか
2020年05月27日
今回の話題ですが、Lancet Psychiatryに”Multisystemic therapy versus management as usual in the treatment of adolescent antisocial behaviour (START): 5-year follow-up of a pragmatic, randomised, controlled, superiority trial”という論文がでていて(文献1)、著者をみたら、Fonagyとあり、あのFonagyの論文なら読まなきゃということで、少し調べて感じたことをまとめます。
専門医を目指す先生方はFonagyの名前は覚えておくべきです。FonagyはUniversity College Londonの教授で、メンタライゼーションの概念を愛着理論と統合し Mentalization-Based Treatmentを開発したイギリスの心理学者です。
専門医試験でもメンタライゼーションの言葉は第10回15番の問題に出現しています。今後精神科医であれば知っておくべき知識といえるでしょう。
メンタライゼーションに関する日本語の本では星和書店の”メンタライゼーションでガイドする外傷的育ちの克服”(崔 炯仁著)はわかりやすくお勧めです。
ただこの本だけではMBTのpracticalなところまでは記載がないので、実践的な内容を学ぶには別の本も必要でしょう。
論文の内容に戻ります。
この論文は、反社会的行為を犯してしまった11歳から17歳の素行症(DSM-IVまでの行為障害)の子がいる家庭に対して、Multisystemic Therapyを施行し、通常ケア群とその5年予後について比較したものです。
イギリスでは2014年に素行症患者は124万人と言われており、早期介入により素行症の症状を改善することにより1人の重症例当たり26万ポンドの経済的損失を防ぐことができると言われているそうです。そのため長期的に有効な介入手法を開発することが重要と考えられています。
Multisystemic therapy(MST)はアメリカで開発され、反社会的行動を呈しており、将来犯罪者になるリスクを有する子供のいる家族のために開発された介入技法です。この治療法のプログラムは集中的な介入であり、家族に焦点をあてており、その他、家庭や学校、地域など様々な場面での介入を含んでいます。
これまでの系統的レビュー(たとえば文献2)では、Multisystemic Therapyは、青年の反社会的行動、犯罪的行動を減少させ、個人と家族の問題を改善すると報告していますが、その元となった報告のほとんどが開発元のアメリカからの報告であり、海外での報告は結果は一定していません。
またすべての長期フォローアップについての報告もアメリカの症例であり、開発者らが報告したものであり、犯罪行為を除いた長期予後については報告されておらず、Multisystemic Therapyの長期予後はよくわかっていない現状です。
そこでFonagyらは、イギリスでMultisystemic Therapyの多施設介入試験(START試験)を実施しました。その18か月予後については既に文献3で報告されています。
START試験の結果の概略ですが、Multisystemic Therapyの無作為割付比較試験であり、11歳から17歳(平均13.8歳 SD 1.4歳:約80%が行為障害と診断。ADHD併存率は約30%)の反社会的行動を呈する若者684名がエントリー(エントリー基準は、過去半年以上にわたって基準を満たす対人暴力、攻撃性を認める、ないし暴力行為などで有罪とされた、ないし素行症と診断、ないし反社会的行動により放校処分となったのいずれかを満たすなどの子供)されました。9つの施設で行われ、通常ケア群とMultisystemic Therapy群に無作為割付されました。介入期間は3-5か月で、介入後18か月間の経過が観察されたものです。
どんな介入がなされたかですが、MST群では、介入は各家庭の状況に応じて調整され、各家族は週に3回、3-5回治療者が面談を行い、24時間対応可能なサービスを提供されました。随分手厚く手間もコストもかかるケアのようです。
家族への介入が中心であり、両親に子供の養育や問題行動に介入するスキルを教育したり、子供に家族の問題に取り組む技法を提供したりされました。またすべての家族メンバーが責任ある行動をとれるように促すことも行われ、家族のスキルを向上させ、様々な社会資源やサービスを利用する手段が提供されました。
一方で通常ケア群では若者犯罪対策チームなどにより提供され、家族への介入や、問題解決技法や物質乱用に対する介入、犯罪被害者への気づきなどの介入などがなされました。頻度などはMST群より低頻度に設定されたということです。それでもそれなりにきちんとした介入かと思います。
結果は、18か月後に脱落しなかった割合はMST群75%、通常ケア群68%でした。主要評価項目である、なんらかの理由で自宅外で家族と離れて生活する若者の割合(大半が就学年齢であり、犯罪や家庭内不適応などの特別な事情がなければ家族と離れて生活することにならず、またMSTが家族機能を強化することに主眼をおいているため、家族と一緒に生活できなくなるということはMSTの目的とは外れたこととなるため。また自宅外での生活はコストがかかるため)は13%(MST群)対11%(通常ケア)で有意差なく、犯罪率については18か月後にMST群は20%。通常ケア群は16%でMST群の優位性は示せませんでした。
副次的評価項目である両親からみた子供の反社会的行動については、6か月時点ではmultisystemic therapy群で通常ケア群と比較して有意な改善を示し、子供の精神的健康、気分、家族機能についても有意に良好でした。しかしこの優位性も18か月後にはみられなくなり、長期的なMSTの有効性については疑問が呈されていました。
今回はさらに期間を延長し、5年予後(5年後の犯罪率など)が追跡されたものとなります。
結果ですが、主要評価項目は60か月後の犯罪率であり、追跡できたのはMST群の311名、通常ケア群の300名(これは警察のデータベースで追跡)でした。一方で質問紙での評価は48か月時点でMST群171名、通常ケア群154名で可能でした。
60か月時点で少なくとも1回の犯罪行為を行った割合はMST群で55%、通常ケア群で53%で有意差はありませんでした。
また本人および家族に質問紙で評価した家族機能、家族葛藤、反社会的問題などの各項目も有意差はありませんでした(唯一非行仲間スコア:peer delinquency scoreのみMST群が有意に良好)。
結論としてはMSTは短期的(介入終了直後)には家族機能などを良好にする効果があるかもしれないものの、介入期間終了後さらに長期的には、犯罪率の軽減などに寄与しうる効果はないかもしれないということになります(ただし通常ケアもそれなりにきちんとした介入のため、差がでなかった可能性もあります)。イギリスの通常ケアの質が良くて差がでなかったのか、それとも平均14歳程度の素行症の子や家族に対してかなり力を入れた介入をしても通常ケア以上の効果はないということなのでしょうか。
もっと早期から介入することが重要なのかもしれません。
そのようなことを示唆する結果がありますので以下でみていきます。
また日本ではその役割は児相や児童養護施設、保護司などが担うことになるのでしょうが、実態や課題はどうなのでしょうか。
中学生程度の年齢の子の反社会的行動にいかに介入するか、難しい問題が垣間見えます(Fonagyらの報告では介入5年後の犯罪率が50%を超えている)。
一方で犯罪行為をしなかった群は、どのような要素で犯罪行為をしないことにつながったのかを調査対象としてみてもよい気がしました。
続いて、MSTの介入試験よりも小規模の介入試験となりますが、MSTの介入試験と同世代(10-17歳:平均15歳)の反社会的行動をとる子供たちを対象としたFunctional Family Therapy (FFT)のイギリスでの介入試験の結果(文献4)をみていきます。
家族内でのネガティブな関係性は子供の反社会的行動や非行の主要なリスク因子であることが知られています。
児童に対してはペアレント・トレーニングが有効であることが知られていますが5)、青年期に対してはその有効性が減弱することが知られています。
FFTはMSTと比較して、コストがかからず、より低頻度の介入でありながら、アメリカでの報告ではMSTと同等の効果があったと報告されている介入技法です。
FFTは11歳から18歳までの子供を持つ家族と子供を対象とする介入技法であり、子供の問題行動は家族間のネガティブな関係性に起因するとの仮説を前提に、扱いにくい子供をもつ家族に対して、家族のコミュニケーションを改善、支援したり、陰性感情や批判的態度を減少させることを目的とした介入技法となります。家族療法的介入に加えて、家族や子供に対して対処スキルを向上させたりするための認知面、行動面の変化、社会学習理論に基づいた介入技法です。
3-5か月間かけて1時間のセッションが合計8-12回施行されます。FFTは初期の開発者らの報告では有効とされました。
しかしこれについてもアメリカ以外の国の追試では有効性は再現されず、疑問が呈されていました。
そこで、Humayunらは、イギリスにおいて111名の平均15歳の反社会的行動を呈する(攻撃的行動により起訴されたか、もしくは警察に保護され当局の介入がなされた)子供を対象に、FFT+通常ケア群と、通常ケア群とに無作為割付し、18か月後の予後を検討しました。
FFTの介入には5つの段階があります。第一段階は、家族セッションに参加することに同意してもらうために、子供とその両親とつながるための積極的なアウトリーチを含むエンゲージメントです。
第二段階は、変化が可能であるという認識を高めるための動機付けになります。
第三段階はリスク因子と保護因子のアセスメントです。リフレーミングを含む一連の介入技法を通じて、家族内の意味を変えることが介入の焦点となります。
第四段階は行動変容であり、コミュニケーション訓練、問題解決のスキル、ペアレント・トレーニングなどが行われます。
第五段階は、特定の状況において学校などのコミュニティ機関と積極的に支援を求めるための訓練になります。
通常ケアはサポートとカウンセリングからなり、アンガー・マネジメントや性や薬物についての教育、被害者の気持ちについての教育などから構成され、家族への介入は行われません。主要評価項目は自己記入式の過去1年間の行為と頻度からなる非行行為質問紙(SRD)でした。65名がFFT群、46名が通常ケア群に無作為割付されました。
その結果、介入開始6か月後、18か月後、いずれにおいても主要評価項目においてFFT群と通常ケア群とで有意差は認められませんでした。
両群ともにベースラインからは有意な改善を認めました。また犯罪行為により過去6か月間に公的な記録が残された子供の割合については、ベースラインのFFT群57%、通常ケア群50%と比較して、6か月時点でFFT群29%、通常ケア群17%、18か月時点でFFT群 20%、通常ケア群 17%と両群ともに経時的な減少がみられたものの、群間の有意差はみられず、FFTの通常ケアに対する優位性を確認することはできませんでした。
以上のように、MSTにしても、FFTにしても、平均14歳から15歳程度の若者の両親に介入を行っても、残念ながらおしなべると明らかな効果が認められませんでした。
中学生の年代の反社会的行動についての対処がいかに難しいかを表しているのかもしれません。一方で、小学生くらいのもっと低い年代ならどうか、これについてはまだ希望の持てる報告があります。
ニュージーランド、オタゴ大学のDianne Leesらが報告した文献6は、3歳から7歳までの反社会的行動を呈した子供の両親を対象に、両親をサポートする介入(HPS)の有効性を通常プログラムと比較した無作為割付介入試験です。
ペアレント・トレーニングは問題行動のある子供の家族に対する介入技法として確立されたものですが、それでもなお1/3の家庭では、ペアレント・トレーニングを行っても子供の問題行動は解消しないとされています。
さらなるサポートが必要であると考えられ、Dianne Leesらは既存のIncredible Years Parent(IYP)プログラム(問題行動を有する子供の家族と対象に親子関係を強化し、適応的な行動を強化し、不適応行動を減弱させるプログラム)に加え、家庭訪問により両親へのコーチングを行うHPS(home parent support)プログラムを開発し、無作為割付試験を行い、HPSプログラムの有効性を検証しました。
HPSプログラムは、1回1時間、計10回の家庭訪問をベースにしたプログラムであり、家庭内の問題点を抽出し、両親の子供に対する期待やコミュニケーション、感情調節、セルフケア、かかわり方などについて支援を行うものです。
試験は3-7歳の問題行動を有する子供(Eyberg Child Behavior InventoryTotal Problem Scale:ECBI-Pが12点以上など、もしくは公的機関の介入や放校などの問題が生じた子供)126名とその家族が対象となり、HPSプログラム+IYPプログラム群とIYPプログラム群単独とに無作為割付され、6か月時点での予後が比較されました。主要評価項目はECBI-P得点であり、結果は、6か月時点においてHPS+IYP群はIYP単独群と比較してECBI-P得点で3.6点有意に(効果量cohen d=0.63)良好であったとのものでした。
70%以上のセッションへの参加率についても、HPS+IYP群は82.5%、IYP群は65.1%と有意にHPS+IYP群が良好な結果となりました。
18か月予後などの長期予後も気になるところですが、短期的には家庭訪問プログラムの有効性を示唆する結果となりました。
Dianne Leesらの結果についても再現性の確認を要しますが、早期介入で効果がみられたことはまだ子供が小さいうちにきちんと介入すれば、それなりに成果が得られる可能性があるという点で希望のもてる結果と言えます。早期介入の重要性を示唆する結果は文献7などにおいても示されています。また、Oregon Research InstituteのEdward G. Feilらは、対応困難な行動を呈する就学前の園児に対して、Preschool First Step to Success(PFS)と呼ばれる多面的な介入技法を適用し、通常ケアとの無作為割付比較試験において、社会的スキルの向上や問題行動の軽減効果がPFS群において約4か月後に有意にみられることを示しました(文献8)。
PFSは教師に対するコーチングと保護者に対するコーチングの2つの要素からなります。
教師はまずワークショップに参加し、教室運営の普遍的な原則を学びます。これらは行動分析学に基づく行動療法的な技法を用いるものであり、ルールの策定やフィードバックなどを通じて、期待される行動を園児に教えるための戦略の作成、動機付けシステム(報酬)を用いて、期待される行動を積極的に強化するための計画の作成などを習得し、その後実際に教室において、トークンなどを用いて学校での成功を促進する適応的な行動パターンと、仲間との関係を改善するための友情形成のスキルを園児に教える段階にうつります。
たとえば教室での適切な行動(教室のルールを守る、協力的である、共有する、静かに座って注意を払うなど)が成功した場合に、ポイントを獲得し、報酬を得るなどの正の強化による学習などを実践します。
また保護者に対しては個別に6-8週間の期間で週に1回、コーチが家庭訪問を行い、コミュニケーションと共有、限界設定、問題解決技法、自尊心を高める方法、友情を深める方法などについてコーチングを受けます。
コーチは保護者をサポートし、問題が生じた際には共に解決を図ります。
以上がPFSの概略ですが、このような教師および保護者への介入により園児の問題行動は短期的(約4か月)には有意に改善がみられたということですので、これもまた年単位の長期的な予後や再現性は気になるところですが、まだ幼い時期においては、このような保護者への介入や教師による介入が問題行動に対して有効である可能性があるということは注目すべきことかと思われます。
これらの介入試験の結果から得られる知見としては、反社会的な行動がみられる子供については、その予後を改善するためには、できるだけ早期に、できれば就学前から小学校低学年のうちから、家族も含めた積極的なサポート的介入を行うことが望ましいということかもしれません。
中学生になってからでは時既に遅しという可能性があるということです。小学校の先生方のご負担をこれ以上増やさないためにも、反社会的行動を示す児童については、早期に家族も含めて、学校外部の機関も協力して介入できるような包括的な介入を行うことができるシステム作りが必要なのかもしれません。
1)Peter Fonagy et al.Lancet Psychiatry 2020; 7: 420–30
2)London Journal of Primary Care, 2017 VOL. 9, NO . 6, 95–103
3)Fonagy P, et al. Lancet Psychiatry 2018; 5: 119–33.
4)Humayun S. et al. J Child Psychol Psychiatry. 2017 Sep;58(9):1023-1032.
5)Humayun S. Violence and mental health: Its manifold faces (pp.391-420)
6)Dianne Lees et al, JAMA Psychiatry March 2019 Volume 76, Number 3 241-248
7)Estrella Romero et al. Adicciones . 2017 Jun 28;29(3):150-162.
8)Edward G Feil et al. J Early Interv. 2014 September ; 36(3): 151–170. -
抗うつ薬の催奇形性について
2020年05月22日
第8回の精神科専門医試験では催奇形性について最も注意すべき抗うつ薬としてパロキセチンを選ばせる問題がでました。
4年前ですので、それはそれでいいのかもしれません。
しかしその前後の報告で、なんとも言えない報告が出てきていて、抗うつ薬の催奇形性をめぐる問題は混沌としてきていますので、その辺りの状況をざっとみてみたいと思います。まさにcontroversialという現状がわかっていただけるかと思います。
このような現状を踏まえると、今後しばらくは専門医試験にSSRIの催奇形性について問う問題は出題されないのではとも思われてしまいますが(出題されたらすみません。その場合の回答は慣例に従ってください)、確証はないです。
そもそもなぜcontroversialとなっているのか、それは観察研究に頼らざるを得ず、完全に交絡因子を調整することが困難であることのみならず、そもそも抗うつ薬によって例えば心血管奇形が生じるとしても、それが有意であると報告されたものにおいても、絶対的リスクの増加率自体が0.5%とか(通常妊娠であっても1万人あたり100人程度の危険率があるところが、パロキセチン曝露により150人くらいになるかどうか)という比較的小さい値になっているため、その差を統計的に有意な差として検出することが困難であるということもあります。
今後さらにうつ病の重症度評価も含めた抗うつ薬への曝露、非曝露症例の蓄積が必要ということかと思います(ここ最近の議論が混沌としてきている原因となっているうつ病罹患妊婦の中で投与、非投与でのリスクの比較をより大規模で行うためにも)
これまでに、純粋に抗うつ薬による催奇形性のリスクのみを抽出しようとして、様々な工夫がなされてきました。各種交絡因子を事前に検討し、前向きコホート研究を行うのみならず、妊婦をうつ病であって抗うつ薬を投与された群に対して、うつ病でも抗うつ薬を投与されなかった群を対照群として比較して、疾患そのものによる奇形リスク因子を除去して検討すること(文献4、文献5、文献6)や(それでもやはり重症度で調整しない限り、抗うつ薬を投与継続された群のうつ症状がより重篤ではなかったかという問題は残ります)、さらには同胞で母親が抗うつ薬を投与され出生した子と、投与されずに出生した子とで、催奇形性リスクを比較し、家庭環境などもなるべく揃えて比較しようとする報告7)などがなされています。
同胞比較は興味深いところではありますが、いかんせん大規模コホートにおいても症例数が少なく(現在までのところ多くても数千まで)、0.5%程度の絶対リスクの差異を検出するにはなお統計的検出力が低いのではないかという問題点もあるでしょう。その点今後のより大規模な報告が期待されます。
ここからは、抗うつ薬と催奇形性について、2018年の比較的新しいメタ解析の報告2)に至るまで、これまでの経緯を振り返ってみます。
初期のパロキセチンと奇形リスクの報告に関しては、2005年にGSKが後ろ向き観察研究により、第1三半期に抗うつ薬を投与された妊婦(3581名)から出生した児において、パロキセチン投与は、他の抗うつ薬と比較して、心血管奇形の調整後オッズ比が2.08(CI 1.03-4.23)と有意に高いと報告したことや、Alwanらが2005年にNataional Birth Defects Prevention Studyのデータベースを後方視的に解析し、SSRIを服用した妊婦は服用しなかった妊婦と比較して,児の臍帯ヘルニアのリスクが有意に高く(OR 3.0:CI 1.4-6.1)、最も影響が強いのはパロキセチンであったと報告1)したものなどとなります。
この結果を受けて、FDAはパロキセチンをカテゴリーDに分類し、警告文書を掲載しました。ただしカテゴリーDですので、既に投与中の場合で、投与することの利益が有害性を上回ると判断された場合には投与継続は禁忌とはされていません。日本でも添付文書上は注意として掲載されており、妊娠中の投与については利益が有害性を上回るかどうか慎重に判断することとなっています。
さらにその後Alwanらは、2007年にNew England Journal of Medicine誌に”Use of selective serotonin-reuptake inhibitors in pregnancy and the risk of birth defects”として、National Birth Defects Prevention Studyのデータベースに1997年から2002年までに登録された先天異常群9622名、健常対照群4092名による症例対照研究の結果を報告しました3)。
先天異常群中第1三半期におけるSSRI投与は408名であり、調整後オッズ比でSSRI使用により対照群と有意差の出た奇形は、無脳症:オッズ比 2.4、頭蓋骨癒合症:オッズ比 2.5、臍帯ヘルニア:オッズ比2.8などとなりました。
さらに同じ時期にアメリカの5つの施設で行われたBirth Defect Study(1993年から2004年まで)のデータベースを使用して、先天異常群9849名、健常対照群5860名と、Alwanらの報告とほぼ同じ規模の症例対照研究がNew England Journal of Medicine誌に”First-trimester use of selective serotonin-reuptake inhibitors and the risk of birth defects.”として報告されました8)両者の違いは、共変量として、Alwanらは人種、肥満、喫煙、収入、年齢、教育、アルコール、高血圧、葉酸の使用などを抽出し、一方でLouikらは、年齢、人種、教育、喫煙、アルコール、奇形の遺伝負因、BMI、DM、高血圧、不妊治療、葉酸使用などを抽出しており、Louikらは奇形の遺伝負因なども抽出しているところでしょうか。
結果はalwanらが報告した頭蓋骨癒合症(オッズ比0.8:CI 0.2-3.5 )、臍帯ヘルニア(オッズ比 1.4:CI 0.4-4.5)についてはSSRI曝露によるリスクの上昇は有意ではありませんでした。ただし個別の薬剤でみた場合、セルトラリンと中隔欠損のリスクの調整後オッズ比が2.0(CI 1.2-4.0)、パロキセチンと右室流出路狭窄(肺動脈弁狭窄症など)のリスクの調整後オッズ比が3.3(CI 1.3-8.8)と有意差がみられました。
そのほか有意差がみられた先天異常は、セルトラリンと肛門閉鎖症(調整後オッズ比 4.4:CI 1.2-16.4)、セルトラリンと肢欠損(調整後オッズ比3.9:CI 1.1-13.5)、パロキセチンと神経管欠損(調整後オッズ比 3.3:CI 1.1-10.4)、内反尖足(調整後オッズ比5.8:CI 2.6-12.8)などとなりました。
同時期の同規模の2つの症例対照研究で異なる結果が出たことからも、比較的まれなイベントを観察研究で統計的に抽出することがいかに困難かがわかります。
少し時期がとんで、2014年に抗うつ薬の先天性心疾患のリスクについてのコホート研究がHuybrechtsらによりNew England Journal of Medicine誌に掲載されました4)。この報告の新しい点は、対照群を抗うつ薬を投与されていないうつ病患者としたことと、うつ病の重症度などもpropensity scoreというものを用いて調整したことです。ただしうつ病の重症度の評価を、外来ないし入院中にうつ病と診断された回数の多さで代用しており、ここはその後の批判の対象となっているところです。きちんと評価された重症度ではないというところです。
アメリカの46州のMedicaidデータベースを用いて2000年から2007年までの妊娠第1三半期に抗うつ薬が投与された妊娠を抽出したものです。Medicaidは低所得者や妊婦などを対象とした公的医療給付制度で、データベースには年齢、性別、人種、診断名、処方薬、処方量、転帰などが登録されています。
このデータベースから期間内に約95万妊娠が抽出され、うち妊娠第1三半期における抗うつ薬処方は6.8%、うちSSRIが4.9%となりました。
結果ですが、うつ病を有する女性で投薬群、非投薬群で比較するとSSRIのpropensity scoreでの調整後相対リスクは 1.06(CI 0.93-1.22)、TCAで0.77(CI 0.52-1.14)、SNRIで1.20(CI 0.91-1.57)などであり、抗うつ薬を投与された群と非投与群とで有意差はありませんでした。
パロキセチンの右室流出路閉塞の相対リスクも1.07.セルトラリンの心室中隔欠損の相対リスクも1.04で有意差はありませんでした。
うつ病の重症度(厳密な方法で求めた重症度ではなく、批判もありさらに検証を要する部分ですが)も含めて交絡因子を調整すると有意差がなくなったというのはこの報告のポイントになりうるかと思います。
ただし飲酒や喫煙などのリスク因子が共変量として抽出されていないのは気になるところです。
Berardらの2016年のBMJ Open誌での報告5)では、Huybrechtsらの報告と同じく、精神疾患(うつ病ないし不安障害)罹患者において、投薬群と非投薬群とで大奇形リスクを比較していますが、Huybrechtsらの報告と異なり、疾患の重症度による調整は行っていませんでした。
Berardらの前向きコホート研究では、ケベック州の妊娠データベースが使用され、1998年から2009年までの単胎妊娠約290万症例が抽出されました。
この報告でも飲酒や喫煙などのリスク因子は交絡因子として抽出されていません(年齢、婚姻状態、福祉受給状態、教育レベル、住所、合併症(高血圧、糖尿病、喘息)などが抽出)。
うつ病ないし不安障害の既往があるのは全妊娠中18487名であり、うち妊娠第1三半期に抗うつ薬投与されたのは3640名でした。非投与の対照群と比較した結果、あらゆる大奇形リスクについては、SSRI(調整後OR1.07)、SNRI(調整後OR 1.10)、TCA(調整後OR1.16)いずれも非曝露群と比較して有意なリスク上昇は認めませんでした。
一方で、薬剤毎に見た場合、あらゆる大奇形リスクについてはシタロプラムが有意にリスク増加と関連(調整後OR 1.36:CI 1.08-1.73)、パロキセチンは心血管奇形(調整後OR 1.45:CI 1.12-1.88)、心房ないし心室中隔欠損(調整後OR 1.39:CI 1.00-1.93)。シタロプラムは筋骨格系異常と有意に関連(調整後OR 1.92:CI 1.40-2.62)、狭頭症(調整後OR 3.95:CI 2.08-7.52)とも有意に関連、TCAは目、耳、顔面、頸部の奇形と有意に関連(調整後OR 2.45:CI 1.05-5.72)、消化管奇形(調整後OR 2.55:CI 1.40-4.66)とも有意に関連との結果となりました。
Huybrechtsらのように重症度も関連する指標も含めて調整することができていたら結果がどうなっていたのか、興味があるところではあります。
続いて、これまでの報告でみられたような、比較対象を健常妊娠や、非投薬のうつ病妊娠群とするのではなく、同胞で非投薬群とする手法による解析結果7)です。この手法を用いると、養育環境はおそらくだいたい揃えることができるだろう(第1子か第2子かで調整は必要ですが)という利点があります。
Furuらの報告では、デンマーク、フィンランド、ノルウェーなど各国の国民健康台帳が使用され、1996年から2010年までの単胎出生したケースが抽出されました。
2303647名の出産があり、36772名の児が妊娠第1三半期にSSRIないしベンラファキシンに曝露しました。
同胞の出生数は2288名でした。
同胞ではなく、非投薬健常妊娠群を対照とした場合には、投薬群のあらゆる奇形リスクの調整後オッズ比はフルオキセチン、シタロプラムなどの抗うつ薬で有意に大きい結果となりましたが、非投薬の同胞を対照とした場合、あらゆる奇形リスク、心奇形リスク、右室流出路閉鎖リスク、いずれも抗うつ薬曝露同胞と非曝露同胞とで有意差は認められませんでした。
同胞の症例数が少ないため、薬剤毎の比較はできていません。
最後にSSRIの催奇形リスクについて、2018年に報告されたメタ解析結果をみてみます2)。この報告は、症例対照研究ではなく、コホート研究のみを解析対象としており、さらに、精神疾患罹患妊婦について抗うつ薬投薬群と非投薬群とで奇形リスクを比較したコホート研究のみを集めたメタ解析を行っている点で新しい報告となります。
このメタ解析は比較対象が健常妊婦ではないため(健常妊婦対照の解析結果も掲載されていますが)、より抗うつ薬の催奇形性リスクについて疾病要因の影響を軽減した解析である点で意義のあるものと思われます。
その結果は、あらゆる大奇形リスクについては、非投薬精神疾患群を対照とした場合、相対リスク1.04(CI:0.95-1.13)で有意差なし。心血管奇形リスクについても、相対リスク 1.06(CI:0.90-1.26)で有意差なしというものでした。また薬剤毎にみた場合でも、パロキセチンと心血管系奇形との関連については、対照を健常妊婦とすると有意差がでます(RR 1.35:CI 1.19-1.53)が、精神疾患罹患妊婦を対照とすると有意差がなくなり(RR 1.27:CI 0.89-1.80)、セルトラリンと心血管系奇形との関連についても対照を健常妊婦とすると有意差がでます(RR 1.42:CI 1.12-1.80)が、精神疾患罹患妊婦を対照とすると有意差がなくなる(RR 1.12:CI 0.92-1.35)というものでした。
健常妊婦を対照とした報告については、潜在的な交絡因子の混入リスク(疾病そのものの要因)もあり、純粋にSSRIの催奇形性であると結論付けることはできないのかもしれません。ただしこのメタ解析も、文献4の批判のある方法で重症度についての評価を行ったHuybrechtsらの報告が解析対象として含まれており、この結果の影響が大きいため、残念ながら結果の信頼性に疑問符がついてしまうところでもあります。
というわけで、いろいろとみてきましたが、結論はcontroversialということで、よくわかりません。controversialという言葉が使いたかっただけなのかもしれません。これからどうすべきかですが、文献4のように批判のある方法ではなく、妊婦のうつ病の重症度をきちんと評価したコホート研究により、文献4の結果の再現性があるかどうかを確認すべきだと思います。
精神疾患罹患群の投薬群、非投薬群での比較は現在のところコホート研究のみのメタ解析では有意差はみられてませんが、精神疾患罹患群の症例数が少ないだけで、真の結論は催奇形性のリスクが1%未満で存在する、ということかもしれません。
実際の現場では我々臨床医はリスクを考慮し、添付文書に従って、慎重に適応を考慮するということになります。
添付文書通りに、このようなリスクについての報告もあり、1%未満程度かと思われますが、心血管系奇形などの奇形リスクが増える可能性があります、という説明を行い、うつ病の治療を行わないことのリスクも考慮し、SDMを行うことになるでしょう(ここでは触れませんでしたが、妊娠後期のSSRI曝露によるPPHNリスクなどはまた別に考慮する必要があります)。
1)Alwan S, Reefhuis J, Rasmussen S, et al.Clinical and Molecular Teratology 2005;73:291.
2)Gao SY et al. BMC Med. 2018 Nov 12;16(1):205. doi: 10.1186/s12916-018-1193-5.
3)Alwan S et al. N Engl J Med. 2007 Jun 28;356(26):2684-92. doi: 10.1056/NEJMoa066584.
4)Huybrechts KF, et al. N Engl J Med. 2014 Jun 19;370(25):2397-407. doi: 10.1056/NEJMoa1312828.
5)Berard A. et al. BMJ Open 2017 Jan 12;7(1):e013372. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013372.
6)L Ban et al. BJOG . 2014 Nov;121(12):1471-81. doi: 10.1111/1471-0528.12682. Epub 2014 Mar 11.
7)Furu K, et al. BMJ. 2015 Apr 17;350:h1798. doi: 10.1136/bmj.h1798.
8)Louik C, et al. N Engl J Med. 2007 Jun 28;356(26):2675-83. doi: 10.1056/NEJMoa067407 -
うつ病とレジリエンス
2020年05月17日
レジリエンスというと、聞きなれない言葉かもしれません。大まかにいえば、逆境に対する抵抗力+回復力という複合的な概念のようです1)。
アメリカ心理学会の定義ではレジリエンスを「逆境やトラウマなどに直面しても、うまく適応していく過程」としています。
いかに病気になりにくく、なっても回復しやすくなるか、これは健康な生活を送る上で重要な要素といえます。
うつ病に関しても、いかにうつ病になりにくく(一次予防)、さらになっても回復しやすくするか、これは重要な研究対象となります。一次予防についてはまた別の場で触れる機会があればと思いますが、うつ病に対するレジリエンスを高める介入についての報告が出ましたのでみていきたいと思います2)。
ただしオープン試験であり、対照試験でもないため、エビデンスの質は低いものとなります。
Mayoクリニックで行われている、いかにレジリエンスを高めるかという手法の一例として、このような取り組みがあるんだな、くらいに理解いただければと思います。
レジリエンスに影響を与えうる心理社会的要因としては、ストレス状況下においても認知面で柔軟性が保持されていること(心理的な視野狭窄に陥らないこと)、さらにストレス状況下においても感情調節能力が保持されていること、ストレスに対処した過去の成功体験、社会的支援(家族や友人など)や仲間などのロールモデルの存在、生きることの意味を持つこと、生きがいをもつことなどが挙げられています2)。
これまでにレジリエンスを高めるためのプログラム(問題解決技法や注意トレーニング、リラクゼーション、ストレス接種など)の有効性についてのメタ解析3)が報告されており、効果量0.37とmildな効果があったことが報告されています。しかしこれらの報告は一体どんな方法で個々人のレジリエンスを測定したかという問題点もあります(解析対象となった13の介入試験では、アウトカムはうつ尺度やQOL、レジリエンス質問紙によるものなどとなっています)。
レジリエンスを測定するための質問紙はいろいろと考案されていますが、たとえば「あなたはひどいストレスで落ち込んでもすぐに回復できますか?」という質問に対して「そうです」と答えた人が客観的にもレジリエンスが高いということはできません。
あるいは、なんらかの介入(トレーニングなど)により介入群が有意にストレス尺度やうつ尺度などが改善したからといって、本当にその人のレジリエンスが良くなったといえるでしょうか?
その人自身の持つ回復力が向上したというよりも、単に介入手法そのものが回復効果を有しており、その効果によりこれら尺度が良くなったとはいえないかということに注意が必要です。
それでも学習効果があれば、その介入手法にレジリエンス改善効果があるのかもしれませんが、この問いに答えを出すには、介入後1年後や2年後などの長期経過後の予後が一つの指標になるのかもしれません。
では、どうやったらレジリエンスを測定できるのか、実際にストレスを与えてみるのか、例えば大昔の心理実験で行われたような、飢餓状態に人間を置くとか、そういう倫理的に問題がある心理実験を行い、評価尺度を用いて、確かにその評価尺度でレジリエンスが高いとみなされた人が、実際に与えられたストレス状況をうまく切り抜けていれば、その評価尺度は妥当だということになります。しかしそれは倫理的に難しいことになります。環境的要因、ストレスに対する保護因子(家族や周囲のサポートなど)はおそらく測定可能ですが、真のレジリエンスをどうすれば測定できるのかについては、妥当と思われる評価項目(例えば性格傾向や考え方、コーピングパターンなどがそれにあたるでしょうか)を用いて、前向き観察研究を行うなどして、ライフイベント発生時のストレス反応や回復状況などを測定し、実際のその評価項目の妥当性を評価するしかないかと思われます。
例えば、今回のテーマのうつ病では、病前性格や病前の社会的機能、認知機能、環境要因などがそれにあたるかもしれません。
実は、評価尺度の妥当性(つまりその評価尺度を考案するに至った病態仮説の妥当性)を評価するための前向き観察研究はあまり多くないのが現状です(たとえば最近では自殺の対人関係論5)など有名な仮説がありますが、このモデルが本当に妥当なのかについて検証した前向き研究はまだありません)。
またレジリエンスが高いことが、個々人の幸せと結びつくか、についてはまた別の問題となります。レジリエンスの高い人が、激しい受験戦争を勝ち抜いて、一流企業に就職し、レジリエンスが高いゆえに残業に追われる毎日を耐え抜き、家庭も顧みるゆとりもない生活を送ることが果たして幸せかどうか、ということになります。
今回の報告では、大うつ病患者を対象に、Mayoクリニックで行われている、ストレスマネジメントとレジリエンシー訓練(SMART)の効果が報告されました。
この訓練の元になったのは、”The Mayo Clinic Guide to Stress-Free Living”という冊子になります4)。
kindleでも販売していますので、興味のある方は手に入れてみてください。
Stress-Free Livingという言葉がなんとも魅力的でしたので、この本の概略を以下にまとめます。SMARTプログラムについて
注意トレーニング
SMARTプログラムの全ての構成要素の基本としてまずは注意トレーニングが行われます。
なぜ注意トレーニングを行うべきかの根拠としては、心には2つの状態(デフォルトモードと集中モード)があり、心がさまよっているデフォルトモードと、集中して気を取られずに存在している集中モードがあるとし、デフォルトモードで過ごす時間が長すぎるとストレスを感じやすくなるため、注意トレーニングが必要であるというものです。
一般的に、注意が外界に向けられているとき、より自然に集中モードになりやすく、注意が内向きになるとデフォルトモードに陥りやすくなると記載されています。
ただしデフォルトモードそのものの存在を害とするわけではなく、デフォルトモードにおいて心がさまよいう能力を持つことは、想像力や創造性に寄与し、記憶を統合し、感情を調整することに寄与しうるとされています。デフォルトモードの存在は、心の広がりに寄与しうる一方で、これが過剰になると、目的志向性の活動が妨害され、過去の悲しみや後悔、罪悪感、将来の不安などについての反復的な思考に陥りやすくなるため、デフォルトモードで過ごす時間を減らし、彷徨う心の思考の質を向上させることが重要であると説かれています。
まずは注意トレーニングにおいて、心を集中モードに切り替え、注意を外界に向けるトレーニングを行うことにより、デフォルトモードで過ごす時間を減らすことが最初のステップとなります。
注意トレーニングの最初のステップとして、自身の心の中にある純粋な子供の心に働きかけることが求められます。
子供の心は日常の中に遊び心と楽しみに満ちており、ありふれた日常の中に喜びを見出すものであり、自身の子供の心を動かすことが最初のステップとなります。
そのために二種類の注意を日常生活においてトレーニングすることとなります。1つ目はjoyful attention(喜びの注意)、2つ目はkind attention(親切な注意)となります。
joyful attention
jouful attentionの一例としてヒナギクの花の写真が提示され、その特徴を細かく観察することの意義が示されます。花びらの形状の違いや雌しべの色合いなど、物事を詳細に見分けることにより普段は気が付かないようなことを見出すことの楽しさ、日常の中に新規性を見出すことの重要性が説かれています。注意を向け、想像力を活用することにより喜びが生成しうる例が示されます。
このことは対人関係においても適応しうることであり、習慣化した関係性の中においても新規性を見出す4つのヒントが記載されています。
受け入れること(受け入れることが他者を変化させるための第1歩となる)、有限性の自覚(この瞬間は繰り返されず貴重なものである)、不和と対立をさけるための柔軟性、他者の精神状態を好転させるための4つのA(他者への注意、感謝、称賛、愛情)を与えることなどが、身近な対人関係において喜びの注意を向けるトレーニングとなります。kind attention
続いてkind attention(親切な注意)のトレーニングについてです。人は第3者についての第1印象を0.1秒程度で感じると言われています。
その印象には様々な感情が含まれており、時に恐れや嫌悪感となります。
ただしそのような感情は独断的であり、様々なチャンスを失うことにつながっているかもしれません。
第3者と出会ったときに、その相手がデフォルトモードの思考に陥っており、それ故にネガティブな感情に陥っている可能性も低くはなく、そのような可能性が50%以上はある可能性があります。
他者に対するkind attentinoとは、誰もが心の中で葛藤を抱えているのだという慈しみの心、ネガティブな判断を遅延させるための受容の心、他者を愛する人のことを想像し、自分もその中にいることを快適な範囲で思い描く愛情の心、他者が自身に対して引き起こした不都合な状況を許容する許しの心、の4つの心を第3者に対して抱くようにトレーニングすることとなります。
このような心をトレーニングすることのメリットは、他者を祝福することが自分自身を祝福することにつながること、他者に対するネガティブな感情が増幅して自分自身を襲うことを避けることができること、他者に対するポジティブな判断は自身の気分を高揚させることにつながりうること、kind attentionを持とうとすること自体が、注意トレーニングとなり集中モードとなることの助けとなりうること、kind attentionを持とうとすることが、断定的な判断を下すことを遅延させることができうること、などとなります。
以上が心を集中モードとすることの基盤となります。続いて注意することにより入ってくる情報について、以下のような構成要素により心の動きを制御し解釈を洗練させるようなトレーニングが行われます。
解釈を洗練させるためのトレーニング
構成要素としては1.Gratitude
少なくとも5名の人に対する感謝を思い浮かべる。不愉快な感情に押し流されそうになった場合でも、そのことを感謝に置き換えるトレーニングをする(例えば「なんて忙しい日なんだ」と思っても、「仕事をすることで多くの人の手助けができることに感謝しよう」など)。感謝することで欲望から解放されることにもつながりうる。また利己的な満足に固執せず、寛大さを身に着けることにもつながる。苦痛からの回復を早めることにもつながるかもしれない2.Compassion
誰もが大なり小なり苦しみを抱えて生きていることに思いをはせ、思いやりの気持ちを持つこと。思いやりの気持ちがあれば、時に不満を表現する人がいても、その表現自体が助けを求めるサインでありうることを想起させる助けになる。解釈の幅を広げ、物事が快適な方向に変化するための行動を起こすきっかけになりうる。思いやりは自分自身がどのように苦境を打開してきたかを思い起こさせるヒントにもなりうる。思いやりの気持ちは怒りを消去しうる感情になり、ストレスを減弱させる可能性がある。
3.Acceptance
自分を含めてすべての人が欠点のある人間であることを受容すること。不完全であることをありのままに受け入れ無理に変えようとしないこと。そのようにありのままを受け入れることから、改善しようとする動きが生じうる。また物事を客観的にありのままに捉えることの助けとなりうる。そのことによりこれから向かおうとする方向性に対してどのような障壁が存在しているかを把握する手がかりとなりうる。
4.Higher Meaning
自身が存在する意義について、個人的経験の中での意義を見出すのではなく、広い解釈を行う。例えば自身が存在する意義を、世界のほんの一部を少しでも良くし、次の世代が地球上での生活に価値を見いだせるように、できうる限りの痕跡を残すことであると位置付けることとするなど。またこの世界での生活は学びの場であり、失敗から学びを得るための場であると解釈することなど。このような解釈を行うことにより現在生きていることの意義をより有意義に感じることにつながりうる。
5.Forgiveness
許容する心は物事を善悪などの二分法的な考え方で捉えるのではなく、ありのままで受け入れることにより、良い方向へ変化をもたらすことにつながる。gratitude、compassion、acceptance、higher meaningのすべての基盤にもなりうる考え方で自分自身がより高い理想の下で生活することを目指すことを意味する。同時に許容するこことは精神的エネルギーの消耗を抑える効果も有する。精神的疲弊を避けることにつながりうる。
6.Celebration,Reflection and Prayer
瞑想や横隔膜呼吸法などのトレーニングSMARTプログラムの概略は以上となります。
これらのプロセスを例えば月曜日にはGratitude、火曜日にはCompassionなど曜日ごとに1つの要素を行うことが推奨されています。
SMARTプログラムは肯定的受容のプロセスと言えるのかもしれません。認知行動療法との違いは否定的な自動思考などを同定したりしないことになります。
日本の内観療法の考え方も取り入れられているのは興味深いところです。内観療法はレジリエンスを高める治療法ともいえるのでしょうか。
マインドフルネスなどの考え方も取り入れられた包括的なプログラムといえそうです。
SMARTプログラムを個人で行うのではなく、グループなど、セラピストと共に行い、セラピストから適宜トレーニング過程に対して肯定的評価が与えられることにより、さらに自己効力感が高まる効果もありそうです。最後のこのストレスフリープログラムが大うつ病患者に対して適応された小規模オープン試験の結果が報告2)されていましたのでみてみます。
大うつ病に対するSMARTプログラムの予備的試験
対象と方法
18歳から80歳までの大うつ病患者でHAM-D17 で8-24点までないしPHQ-9で6-19点ないしQIDSで6-20点の非重症例
双極性障害や物質乱用などの合併症を有する者は除外
対象者に対しては3-8名からなる集団で、1名の治療者によりSMARTプログラムが毎週1回月曜日の午後に1回あたり75分から90分のセッションで施行された。セッションは合計8回施行
主要評価項目はConnor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC)で、副次的評価項目はPerceived Stress Scale(PSS:20点以上で高ストレス)、HAM-D17 、PHQ-9、GAD-7
参加者は23名結果
完遂者は17名で年齢が若いことが脱落者との比較で有意差がみられた尺度であった
CD-RISCはベースラインの平均53.9点から8週後の時点で平均61.1点と有意に改善
PSSについてもベースラインの平均23.5点から8週後の19.4点まで有意に改善
HAM-D17についてはベースラインの平均14.3点から8週後の9.1点まで有意に改善
17名中11名が寛解(HAM-Dで7点以下)
17名中10名がその後の長期follow up(平均5.5か月)が可能でPHQ-9で5点以下の寛解を維持できていたのは10名中6名であった。コメント
オープン試験なのでなんともいえないところですが、うつ病の長期経過で回復後に閾値下の症状なく健康な状態で状態で過ごすことができた患者の割合が1年間で57%であったとの報告(文献6)がありますので、SMARTプログラムでの寛解維持率(平均5.5か月で6割)というのが、本当にレジリエンスを高めることができたのかどうかについては疑問です。
またCD-RISCも質問紙による主観的評価ですので、本当に客観的なレジリエンスを評価できているのか、疑問に感じるところではあります。
ただしSMARTプログラムの概念は日常診療の中の一工夫として取り入れることができるかと思います。
引用文献
1)田 亮介ら.精神経誌(2008)110巻9号 757-763
2)Ashol Seshadri et al. Prim Care Companion CNS Disord 2020;22(3):19m02556
3) Leppin AL, Bora PR, Tilburt JC, et al. PLoS One. 2014;9(10):e111420.
4)Sood A. The Mayo Clinic Guide to Stress-Free Living, Boston, MA:Da Capo Press;2013
5)Van Orden KA et al. Psychol Rev. 2010 April ; 117(2): 575–600.
6)藤田 晶子ら、臨床精神医学(2006)34巻5号;669-675