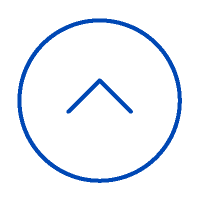-
どのように訳せばよいのか
▽まだ国内ではおそらくあまり広まっていない用語かと思われますが、self-disorderもしくはbasic self-disturbanceという概念があり、これの日本語をどうするかでちょっと悩みました。self-disorderについては2021年にLancet psychiatryで特集されていました(Lancet Psychiatry 2021; 8: 1001–12)。結局基底自己障害としました(近日発行予定の臨床精神薬理の総説にちょっと入る予定です)
▽その総説では全くself-disorderのことについては詳細は触れていないので、ここでちょっとまとめておきます。
▽欠点はEASE得点などをとるには随分とトレーニングとか必要みたいで、まだそう簡単にできるものではないもののようだということです。
▽概念としてはそんなに新しいものでもなく、Huberの基底症状概念に由来するものでもあり、以前から言われているものとなります。以下総説では文字数の関係でボツにしたself-disorderに関する部分を抜粋します。
*****************
▽初発精神病において、治療的介入の観点から統合失調症らしさの手がかりとなる症状を同定することは重要である。近年、そのような手がかりとして基底自己障害(basic self-disturbancesもしくはself-disorder)が注目されている(Lancet Psychiatry 2021; 8: 1001–12)。
▽基底自己障害はSchneiderの一級症状に含まれる被影響体験や考想伝播、考想奪取などの自我障害(ego disturbance)とは異なる概念であり、自己の感覚や自己と世界との関係性の微細な変化などの主観的体験の異常を表すものである。例えば、自己の存在感の希薄化による自己の一貫性や連続性の欠如、自己と環境の境界があいまいになる感覚や自己の内的体験の疎外感、思考や行動の主体性の低下などに伴う、身体感覚の異常(自分の身体が自分のものでないように感じる)、思考の流れの異常(思考が断片的に感じられる)などが含まれる。なお操作的診断基準における一級症状は主に体験内容に焦点を当てており、Schneiderが一級症状の本質として重視した、自己経験の質的変化としての自他境界の曖昧さという視点が見落とされている。従って初発精神病患者の見立てに際しては、患者の主観的体験の質的な変化に着目することが重要である(Lancet Psychiatry 2021; 8: 1001–12)、
▽基底自己障害の評価尺度としてHuberの基底症状概念を基に開発されたBSABS(Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms)(Gross G, Huber G, Klosterkötter J, Linz M: Bonner Skala für die Beurteilung von Basis symptomen. Berlin, Springer, 1987, p 1995.)や、ParnasらによるEASE(Examination of Anomalous Self-Experience)(Psychopathology 2005;38:236–258)などが知られている。
▽Henriksenらは診断カテゴリー毎のEASE得点の加重平均を報告した(Lancet Psychiatry 2021;8: 1001–12)。EASE得点については57項目のEASEの各項目を0点ないし1点の二値に変換し、診断カテゴリー毎に平均何項目自己の障害を有するかによって比較された。24報の結果が統合され、統合失調症(n=214)では平均20.7項目、統合失調症型障害(n=87)では平均19.7項目、双極性障害(n=21)では平均6.3項目、その他の精神病性障害 (n=21)では平均11項目、自閉スペクトラム症 (n=22)では平均7.4項目、健常対照群 (n=95)では平均0.8項目となり、統計的な検定はなされていないが、統合失調症圏において特異的にEASE得点が高いことを示唆する結果となった。
▽Nordgaardらは初回入院した統合失調スペクトラム症患者48名を対象に、ベースラインと5年後のEASE得点、機能的尺度(global assessment of functioning)、陽性症状、陰性症状などを評価した(Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci (2018) 268:713–718)。その結果、ベースラインのEASE得点が5年後の機能的尺度の改善度と有意に相関した一方で、ベースラインと5年後のEASE総得点は有意差がなかった。小規模試験のため再現性の確認を要するが、この結果は、基底自己障害が統合失調スペクトラム症の機能的予後の予測因子となりうる可能性を示唆する一方で、基底自己障害が時間的安定性の高い統合失調スペクトラム症の特性マーカーとなりうる可能性を示唆するものである。
▽Parnasらは初回精神科入院患者151名を前向きに5年間追跡し、ベースラインのBSABS得点、PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale)などを評価し、その後の統合失調スペクトラム症への診断変更の予測因子を検討した(World Psychiatry 2011;10:200-204)。その結果、ベースラインで非統合失調スペクトラム症と診断され、追跡可能であった38名のうち、14名が5年以内に統合失調スペクトラム症に診断変更された。診断変更群と診断非変更群でベースラインの特性を比較したところ、統合失調スペクトラム症への診断変更の最も大きな予測因子はベースラインのBSABS得点であった(オッズ比=12.00:95%信頼区間 (CI) 2.15-67.07)。ついで困惑気分が抽出され(オッズ比=6,11; 95%CI 1.34-27.96)、ベースラインのPANSS得点は統合失調スペクトラム症への診断変更の有意な予測因子ではなかった(陽性症状尺度オッズ比=1.13.95%CI 0.30-4.26、陰性症状尺度オッズ比=0.90、95%CI 0.23-3.59)。この結果は、基底自己障害が後の統合失調スペクトラム症への診断変更のリスク因子となりうる可能性を示唆するものである。
▽なお、Huberの基底症状と中安の初期統合失調症症状については共通点が多く(針間 博彦、西田 淳志:統合失調症ないし精神病性障害の前駆期/超ハイリスクの症候学:臨床精神薬理 13:23-36,2010)、初期統合失調症概念の統合失調症の中核症状としての重要性を示唆するものである
*********************
▽まだまだ研究はこれからというところですが、病態生理との関連でも議論されており、なかなか興味深いところです
-
総説
老年精神医学雑誌より執筆依頼をいただき、「せん妄はどれだけ認知症になりやすいか?」というテーマで総説を書かせていただきました。せん妄と認知症の関係性についての因果推論は困難ですが、現在までにわかっていることと課題についてまとめました。5月号に掲載予定となっています。
-
備忘録
・忘れないでおきたい小ネタをいくつか書き留めておきたいと思います。
診断分類の話とか
・診断カテゴリーの細かいことはなかなか覚えづらいのですが、専門医試験で聞かれることもあるみたいなので、無視もできないことになります。DSM-IVの身体醜形障害は身体表現性障害下に分類されていましたが、DSM-Vでは強迫症および関連症群下に分類されています。ICD-10では身体醜形障害は独立した病名として存在せず、身体表現性障害下の心気障害に含まれています。ICD-11では心気障害が心気症として強迫症または関連症群のカテゴリー下に移されました。またICD-11では身体醜形症として心気症から独立しました。適応障害はICD-11では適応反応症へ病名変更。このような変更点はまだまだたくさんあるのでまとめておこうかと思いましたが、気力がわきません。DSM-IV-TRで研修した身としては、病名の変更など、患者さんの利益にすぐにつながりにくいことについては、なかなかなじみにくいことではあります(多分専門が精神科以外の先生はもっと戸惑われると思います)
ALS plateauとreversal
・PRO-ACTデータベースには、様々な臨床試験におけるALSのデータが集積されており、それを用いて一定期間において進行が停止する(プラトーになる)もしくは改善(reversal)する割合がどの程度かについての報告(Neurology. 2016 Mar 1;86(9):808-12.)がありました。最近中国からの前向き観察研究の結果が報告(J Clin Neurosci. 2022 Jan 21;97:93-98)されたのですが、こちらの方が大規模データなので、小規模試験の結果を解釈する際に参考になるのでまとめておきます。特に10例程度の症例報告で一部に進行停止がみられたなどの報告がある場合に、その結果がどの程度確からしいのかについて批判的に吟味する際に役にたちそうです。
・PRO-ACTデータベースによると、ALSFRS-Rの変化量でみた場合、6カ月間では25%が進行せず(対象者数3132名)、12カ月では16%が進行せず(2105名中)、18カ月間では7%が進行しなかった(1218名中)。reversalについては、180日間で14%(1343名中)がALSFRS-Rの変化量が0を超えた(改善した)とのことです。。この結果に関する注意点は、PRO-ACTデータベースへの参加者で構成されており、主に無作為割付比較試験への参加者であるため、実際の患者層の状態変化を反映していない可能性がある点です。四肢発症型の118名を対象とした前向き観察研究(J Clin Neurosci. 2022 Jan 21;97:93-98)では、6カ月間でのreversalの割合が8.47%であり、3か月間でのプラトーの割合はだいたい20-25%程度と報告されています。これらの結果から得られることは、例えば10名を対象とした小規模試験を行う場合、この規模の試験ではそもそもが病気の進行について何か言える試験規模ではないのですが、予備的な結果として、6カ月間で5名が進行停止しましたという結果が得られた場合、非常に大雑把な検定をすると、統計的に有意な結果とはいえないということになります。
ADHD治療薬と物質乱用リスク
・ADHD治療薬、特に精神刺激薬(メチルフェニデートなど)と物質乱用リスクについてです。勉強会ではlancetの総説(Lancet. 2020 Feb 8;395(10222):450-462)を使ったりしていたのですが、その中において、精神刺激薬が物質乱用や依存の可能性を高めるかもしれないという懸念について、2014年の観察研究の報告(J Child Psychol Psychiatry. 2014 Aug;55(8):878-85.)が引用されていたのでまとめておきます。結論からいうと、3年程度の観察期間において、ADHD患者全体としては、非ADHD患者よりも物質乱用リスクは高かったものの、ADHD患者内で検討した場合、精神刺激薬を使用していた群は、使用していなかった群と比較して、物質乱用リスクは各種共変量(年齢、性別、服薬状況、精神疾患、社会経済状況など)についてCox回帰分析にて調整した結果、31%程度有意に低くなるとの結果でした。SSRIの使用の有無で物質乱用リスクを比較したところ、ハザード比は1.04と有意差はありませんでした。ADHD治療薬は犯罪率の減少にもつながりうるとの報告(N Engl J Med 2012; 367: 2006–14.)もあり、いずれも観察研究からの帰結ではありますが、長期的有益性を支持する結果といえそうです。しかし精神刺激薬については耐性などの問題もあり、その適応には慎重になる必要があります。
上市される割合はどのくらいか
・世界のバイオ技術関連企業などが設立した団体であるThe Biotechnology Innovation Organizationというところが、2011年から2020年までの臨床試験の成功率などを分野毎にまとめて公表しています(https://www.bio.org/clinical-development-success-rates-and-contributing-factors-2011-2020)。
・神経変性疾患領域でのここ最近の第3相試験の惨敗状況(NurOwn細胞やtofersen、レボシメンダン、aducanumabはさておき、その他の抗Aβ抗体、BACE阻害薬など)をみると、ここまで第3相からNDAに行く割合が高い(53.1%)とは思っておらず意外な数字でした。
・ここまで高い数字になっているのは、基礎から開発された薬剤のみならず、例えば注射薬の経口薬版とか(最近だとエダラボンの経口薬)の第3相試験も含んでいるからかなと思います。 -
シグマ1受容体のこと
・今年もよろしくお願いいたします。
・もともとシグマ1受容体のことがよくわからなかったのですが、益々わからなくなる論文(文献1)が出たので、記事にしておきます。シグマ1受容体が主に小胞体上に存在する細胞内受容体ということ。シャペロンとしての機能も有するようだということ。そのあたりはいいのですが、フルボキサミンがシグマ1受容体のアゴニストだから精神病性うつ病に有効かもしれないという考察があることが理解できてませんでした。
・フルボキサミンの膜透過性がどうなのかということですが、細胞内に入って細胞内の受容体に作用する物質として、ステロイドや甲状腺ホルモンなど疎水性物質があるようです。フルボキサミンは構造的にどうなのでしょうか。親水基があるので、細胞内にまでそう簡単に入っていくようにはみえないのですが。そもそも血液脳関門を透過するので、脂溶性が高いのでしょうか。そう思ってちょっと調べると文献2にフルボキサミンの膜透過性についての記述がありました。「フルボキサミンの酸解離定数は8.86くらいで、生理的pHの範囲内では極性を持ちにくく、イオン化しにくい塩基性物質なので、膜を透過しやすい」そうです。ということで、細胞内受容体に作用するという事は、ありのようです。
・続いて、精神病性のうつ病にフルボキサミンが効果があるのではないかという説があるようですが、これについても臨床的なエビデンスはありません。そもそもこのような話が出現した背景には、1990年代後半からの1つのグループからのいくつかの報告があります。いずれも単一のグループ(Zanardiら)からの小規模な報告であり、これらの報告についてもフルボキサミンの優位性を示したわけではないので(メッセージとしてはフルボキサミンのみならず、ベンラファキシンも、セルトラリンも単剤で精神病性うつ病に効果があるかもしれませんというメッセージ)、シグマ1受容体へのアゴニスト作用があるからといって、それがフルボキサミンにとって特別になんらかのメリットになっているとは読み取れないのです。
・1つ目の報告は文献3になります。この論文では、平均年齢50.6歳の精神病性のうつ病エピソード(DSM-III-R)患者59名を対象に、オープン試験で6週間、フルボキサミン300mgにて有効性を検証したものです。
・6週間でのresponse rateが主要評価項目でしたが、このresponseはHAM-D21で8点以下かつDimensions of Delusional Experience rating scaleで0点ということで、ほぼ寛解といってもいい定義になっていました。結果は、脱落がわずかに2名、response rate 84.2%とすごい数字が報告されました。精神病性うつ病に対して抗うつ薬+抗精神病薬での治療を行っても、ここまでの高い寛解率は介入試験では報告されておらず(例えばセルトラリン+オランザピン(STOP-PD試験)では12週間で41.9%(Arch Gen Psychiatry. 2009 AUG;66(8):838-47)、ベンラファキシン+クエチアピンでは7週間で41.5%(Acta Psychiatr Scand. 2010 Mar;121(3):190-200.)など)臨床的な感覚とかなり乖離を感じる数値となっています。
・2つ目の報告は文献4になります。この報告では、28名の精神病性の特徴を有する大うつ病(DSM-IV)患者が対象となり、フルボキサミンないしベンラファキシンに無作為割付され6週間観察されました。文献3と同じくresponseはHAM-D21で8点以下かつDimensions of Delusional Experience rating scaleで0点で定義され、寛解と言っていい定義になっていました。その結果、6週間でのフルボキサミンの反応率78.6%、ベンラファキシンは58.3%で有意差なく、どちらも効果が期待できそうだという結論になっています。
・さらに3つ目の報告(文献5)では、フルボキサミンは入っていませんが、セルトラリン(150mg/day)とパロキセチン(50mg/day)が、精神病性のうつ病エピソード(DSM-III-R)患者46名(大うつ病が32名、双極性うつ病が14名)を対象に、二重盲検で6週間、有効性が比較されました。responseの定義は文献3、文献4と同じくHAM-D21で8点以下かつDimensions of Delusional Experience rating scaleで0点で定義されました。その結果、6週間での反応率はセルトラリン群75%、パロキセチン群46%であり、OC解析では有意差なし(ITT解析では有意差あり)との結果でした。ここで注目すべきはセルトラリン群の反応率もかなり高い数字である点です。セルトラリンは文献6によるとシグマ1受容体に対しては機能的にはアンタゴニストとして作用すると解説されています。
・そういうわけで、シグマ1受容体アゴニストとされるフルボキサミンも、シグマ1受容体アンタゴニストとされるセルトラリンも、精神病症状を伴ううつ病に対して単一グループからの報告では、かなりの良好な治療反応率が報告されているわけで、治療反応性をシグマ1受容体で説明することはどうなんだろうと思っていたのです。
・ちなみにZanardiらは別にフルボキサミンがシグマ1受容体に親和性が高いので、精神病性うつ病に効果があったのではなどという主張はしていません。このような話がでてきたのは、かのStahl先生がこちらの論文(CNS Spectr. 2005 Apr;10(4):319-23. doi: 10.1017/s1092852900022641)でそのような議論をされたからではないかと思われます。
・そして益々わけがわからなくなったのが文献1の報告です。この報告では。SOD1変異ALSモデルマウスに対してシグマ1受容体のアゴニスト(PRE-084、SA4503)とアンタゴニスト(BD1063)が投与され、その効果が検証されました。その結果アゴニスト(PRE-084)もアンタゴニスト(BD1063)もいずれもモデルマウスの神経筋接合部機能を対照群と比較して有意に保存し、運動神経細胞数も有意に保持される結果となりました。シグマ1受容体に対して正反対の作用をするはずの両薬剤が、いずれも治療的効果を発揮したことの理由については、シグマ1受容体のリガンドの分類方法そのものに問題があるのではないかということが考察されています。
・この報告ではアゴニストとアンタゴニストの分類については、シグマ1受容体と、同じくシャペロン分子であり、シグマ1受容体と結合するBiP(binding immunoglobulin protein)との相互作用に対する影響で定義されていますが、このようにして分類した場合、同じアゴニスト同士でも機能が異なるものが生じるということです。具体例として、シグマ1受容体アゴニストのSA4503は、神経筋接合部においてカイニン酸による活性化およびブラジキニンによる活性化後に細胞質カルシウムイオン濃度を正常化したのに対し、同じシグマ1受容体アゴニストとされるPRE-084はいかなる有意な効果も及ぼさないことがあげられています。このような事実から、Gaja-Capdevilaらは、シグマ1受容体リガンドは、効果の微妙なバランスで異なる経路の活性を促進する可能性があり、アゴニストまたはアンタゴニストという従来の単純な分類は当てはめることができないのではないか、アンタゴニストとされるBD1063は実は機能的に部分アゴニスト作用を有しているのではないかとなどと考察されています。というわけで、セルトラリンも機能的には部分アゴニスト作用とされるような機能を発揮するのでしょうか。わかりませんが少なくともシグマ1受容体への作用については、単純にアゴニスト、アンタゴニストと言わず、もう少し活性化する細胞内シグナル経路により細かく分類した方がいいのかもしれません。
・ここ最近盛り上がっているのはフルボキサミンのCOVID-19に対する効果ですが、これについてもシグマ1受容体との関連で議論されており、2つの異なるグループからの介入試験の報告で有効かもしれないと言われているようですが、まだ第1種過誤の可能性はぬぐえず、結論はだせないと思われます。現在実施中の4つの大規模臨床試験の結果を待ちたいところです。
文献1:Núria Gaja-Capdevila et al. Front Pharmacol. 2021 Dec 10;12:780588. doi: 10.3389/fphar.2021.780588. eCollection 2021.
文献2:Front Pharmacol. 2021 Apr 20;12:652688. doi: 10.3389/fphar.2021.652688. eCollection 2021.
文献3:Gatti F, Bellini L, Gasperini M, Perez J, Zanardi R, Smeraldi E. Am J Psychiatry. 1996 Mar;153(3):414-6. doi: 10.1176/ajp.153.3.414.
文献4:R Zanardi 1, L Franchini, A Serretti, J Perez, E Smeraldi J Clin Psychiatry. 2000 Jan;61(1):26-9. doi: 10.4088/jcp.v61n0107.
文献5:Am J Psychiatry. 1996 Dec;153(12):1631-3. doi: 10.1176/ajp.153.12.1631.
文献6:Ann Gen Psychiatry. 2010 May 21;9:23. doi: 10.1186/1744-859X-9-23. -
これはどうなるのか
・Biogen社は同社の10月14日付press releaseにおいて、同社がAmerican Neurological Association Annual Meeting 2021において発表したTofersenの第3相試験結果を公表しました
・TofersenはSOD1変異家族性ALSに対する治療薬候補として開発されたアンチセンス・ヌクレオチド製剤であり、SOD1 mRNAに結合し、変異SOD1蛋白質の発現を阻害することにより、病態改善効果を期待するものです。
・この第3相試験(NCT02623699)では、108名のALS患者が対象となり、プラセボ対照で28週間、tofersenの有効性や安全性などが検証されました(tofersen群 72名、プラセボ群 36名)
・Tofersenは28週間で合計6回くも膜下腔内に投与されたようです。主要評価項目は28週間でのALSFRS-Rの変化量でした。
・既に結果が報告された(N Engl J Med. 2020 Jul 9;383(2):109-119)第1/2相試験では、最高用量において髄液中SOD1蛋白質濃度がプラセボに比較して33%減少しており、ALSFRS-Rの平均変化量もプラセボに比べて12週間で4点以上の差があり(症例数が少なく、有効性に関する議論はできない状況でしたが)、第3相試験はいけるんちゃうかなと思わせるものでした。Biogen社はSMAに対するスピンラザでも、アンチセンス・オリゴヌクレオチド製剤の実用化を実現しており、実績があるので、まあ大丈夫じゃろうくらいに思っていました。
・結論は残念ながら主要評価項目は達成できず、28週でALSFRS-Rのプラセボとの差は1.2点(p=0.97)でした。第1/2相での好ましい結果についてはsmall study effectとして解釈できるものであったのかもしれません。
・一方で、副次評価項目である髄液中SOD1蛋白質濃度はプラセボ群と比較して、急速進行群では38%、緩徐進行群では26%の減少ということで、そこまで大幅な減少とはいえないのかもしれませんが、概ね第1/2相試験の結果を再現するものでした。別の副次評価項目の血漿中ニューロフィラメント軽鎖量は急速進行群では67%、緩徐進行群では48%の減少ということで、こちらも望ましい結果ということになりそうです。他の副次評価項目の静的肺活量などは有効性について有意差までいかないもののtrendがみられたということです。症例数がそこまで多くはないので、検出可能な差は小さくはなく、definitiveなことは言えないのかもしれません。
・Biogen社といえば、aducanumabの前例(臨床的効果に基づく承認ではなく、アミロイドβプラークを減少させることができるという事実に基づく承認)があるので、今回のバイオマーカーの望ましい変化についてはどう判断されるのでしょうか。
・ただ、tofersenの場合には、もう1つ別の第3相試験(NCT04856982)が既に開始されていて、発症前のSOD1変異家族性ALS患者を対象にした試験が行われている最中です。FDAの判断はこちらの試験結果が出てからになるのかもしれません。神経変性疾患においては、発症後に原因物質候補を除去してもあまり治療的効果は期待できないということなのでしょうか。
・またアメリカ版の患者申出療養制度ともいえるExpanded Access Programにおいて、tofersenはなんと無料で提供されうるとの記載があり、これまでこの種の制度には高額の自己負担費用がかかるものと思っていたので驚きました。財源はどこから拠出されるのかについても興味があるところです。