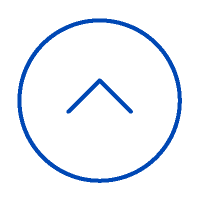-
症状クラスタリングと治療反応性(1)
2020年04月22日
どの抗うつ薬がどの症状に効くのか、とても興味のある話題です。
そんな問いに答えようと計画された解析により、既存の臨床試験結果を解析し、抗うつ薬によりどのような症状が改善しやすいのかについて報告された論文があります。
今回と次回で、そのような報告をとりあげてみたいと思います(今回はエキスパートコンセンサスについての話題が中心で、目的とする論文にたどり着けませんでした)。
現在よく使用される抗うつ薬にはSNRI、SSRI、NaSSaなどがあります。
今年4月1日号のJournal of Affective Disorders誌に抗うつ薬の使用についての日本のエキスパートコンセンサス(114名のエキスパートの回答結果のまとめ)が公表されました1)。
結果の概略ですが、中等度から重度うつ病に対する第1選択薬としては、ミルタザピン、デュロキセチン、エスシタロプラム、ベンラファキシンといった順序になっています。
また主要症状毎に適応薬剤をみていくと、不安が主な症状の場合には、エスシタロプラムが第1選択、ついでセルトラリン、興味の減退が主な症状の場合には、デュロキセチン、ベンラファキシンといったSNRIが第1選択、不眠が主な症状の場合には、ミルタザピンが第1選択、食欲減退が主な症状の場合には、ミルタザピンが第1選択、焦燥感(精神運動激越)、易刺激性が主な症状の場合には、ミルタザピンが第1選択、希死念慮が主な症状の場合にはミルタザピンが第1選択となっていました。
皆さんの臨床的実感と一致するでしょうか。これはエキスパートコンセンサスですので、エビデンスとはいえないものです。
このような薬剤選択の根拠は何でしょうか?
手元にある範囲で、いくつかの比較試験やメタ解析の結果をみながら、各薬剤の特徴について振り返ってみたいと思います。
まずはミルタザピンです。2010年に急性期うつ病に対するミルタザピンとSSRIの有効性を比較した15の介入試験のindividual patient dataによるメタ解析結果が公表されました2)。HAM-D17得点の変化でSSRI全体(フルオキセチン N=411、パロキセチン N=391、セルトラリン N=290、フルボキサミン N=199、シタロプラム N=139)とミルタザピン N=1484が比較されました。
その結果、6週間での脱落率はミルタザピン 31.3%、SSRI 27.8%であり、忍容性に大差なく、寛解率(HAM-D17得点が7点以下で定義)でみた有効性については、1週目(3.4% vs 1.6%)、2週目(13.0% vs 7.8%)、4週目(33.1% vs 25.1%)、6週目(43.4% vs 37.5%)のいずれもSSRIより有意に高い寛解率を示しました。ミルタザピンはSSRIよりも効果の立ち上がりが速い(最初の2週間ではSSRIよりも74%大きな寛解率を示した)ということができそうで、このことは2011年のCochrane reviewにおいても支持されています3)。
個別のSSRIとの比較については、2018年のネットワークメタ解析でのhead-to-headの介入試験のみでの解析結果を参考にすると4)(supplementary materialのセクション8.1.1参照)、フルオキセチンとフルボキサミンに対して反応性が有意に良好との結果になっています。
対SSRIでの文献2での6週時点での有意差はこの2剤との比較試験の結果にひきずられたのかもしれません。
というわけで、ミルタザピンは治療効果の発現が速そうだという印象です(単に鎮静がかかってHAM-D得点の一部がよくなったせいじゃないかと思っていた時期もありましたが、文献2のように寛解率を尺度にしても速いので、単にそれだけではないのかもしれません)。
また焦燥感(精神運動激越)、易刺激性についてですが、不安を伴う大うつ病に対するミルタザピンの有効性に関するメタ解析5)において、HAM-Dの項目9(精神運動激越)、項目10(不安の精神症状)、項目11(不安の身体症状)の合計点において、プラセボよりも有意に良好な改善度を示し、その効果はアミトリプチリンと有意差がなかったとの結果が報告されています。SSRIなどと比較したものは見当たらない(ご存じでしたら教えてください)のですが、鎮静作用を有することからも、焦燥感への効果を期待してというところかもしれません。
続いて鎮静作用とも関連するのですが、不眠を伴う場合もエキスパートコンセンサスではミルタザピンが第1選択となりました。不眠に対するミルタザピンの効果ですが、ミルタザピンのS体のみからなるエスミルタザピンの原発性不眠症に対する第2相試験の結果が報告6)されており、エスミルタザピン1.5mg以上の用量(ミルタザピンでは3mgの低用量)において、PSGによる総睡眠時間が25分以上延長し、睡眠の質も改善されたことが報告されています。
この鎮静作用については、用量依存性に軽減する可能性も報告されており7)、ほんとかどうかわかりませんが、文献7では高用量になるとミルタザピンのノルアドレナリン賦活作用が、抗ヒスタミン作用に拮抗する可能性も考察されています(そうではなくて単なる耐性かもしれません。投与初期には問題があっても、15mgの固定用量で8日間投与を継続すると運転パフォーマンスはプラセボと有意差がなくなるという報告9)もあります)。
ただし、ミルタザピンは半減期が23-33時間と長く、健常者への午後9時半15mg単回投与でも投与2日目の翌朝7時でのドライブシミュレータ試験でブレーキングの遅延がみられたなどの報告8)があり、特に投与開始初期に運転などへの影響がありうることに注意が必要です。
というわけで、確かに不眠を伴う場合にはいいのかもしれませんが注意を要します。
さらに食欲減退を伴う場合もミルタザピンが第1選択となりました。これについては、抗うつ薬と体重増加に関するメタ解析10)の結果がわかりやすいのではないかと思います。
116の試験のメタ解析結果で、投与開始初期(4-12週)と4か月以上の維持療法期とで抗うつ薬がどの程度体重増加をもたらすかを検討したものです。
短期的投与では多くのSSRI、SNRIが体重変化なし、むしろ減少することが多いのに対し、ミルタザピンの体重増加作用はアミトリプチリンなどの三環系抗うつ薬と並んで目立っています(4-12週間の投与で2kgくらい増える結果)。
さらに8か月以上の投与期間でみても有意な体重増加効果があることが報告されています。
この報告でもう1つ面白いのは、SSRIの体重変化です。投与開始4-12週では体重が全体としては減るのに対して、投与期間が長くなると、全てではありませんが、パロキセチンなど一部のSSRIも有意な体重増加を示しているところです。
セルトラリンなどは長期使用しても増えないようですが、これは臨床経験とも一致する結果です。
というわけで、食欲減退についてもミルタザピンが第1選択となるのはよくわかるところです。
希死念慮についてもミルタザピンが第1選択となりました。これは難しいところで、臨床試験では、希死念慮の重篤なケースは除外することがほとんどなので、本当にシビアなケースに適応できる結果なのかは慎重を要するところです。
例えば文献11)のような報告があり、大半がベースラインのHAM-D項目3の自殺尺度が2点以下の患者を対象とした15の短期(6週間)プラセボ対照比較試験のpooled analysisにより、HAM-D項目3の得点は2週目から有意差をもってミルタザピンが有意に良好であるとの結果でした。
また6週間の経過中HAM-D項目3の得点が3点以上になる割合も2週目以降ミルタザピン群でプラセボ群より低く、そのオッズ比は0.38と有意に低い結果でした。
一方で希死念慮が比較的重度といってもよいHAM-D項目3の得点がベースラインで3点以上の患者についての結果も、少数ながら解析されています。
全体でミルタザピン群35名、プラセボ群44名がエントリーされており、項目3が3点以上であり続けた割合は、1週目 38.9%(プラセボ群)対41.2(ミルタザピン群)、2週目 22.2%対6.5%、3週目 9.4%対6.5%、4週目 5.9%対0.0%、5週目 3.6%対0.0%などとなっていました。
症例数が少ないため、統計的有意差はでなかったそうですが、興味深い結果といえます。
ただし、このようなミルタザピンの結果については、臨床試験に参加した純粋な患者集団(併存症などのない)に対する結果であることに注意が必要です。
我々が向き合うリアルワールドでは、こうはいきません。文献13にあるように、高齢者を対象とした長期観察研究では、ミルタザピンは自殺企図率の最も高かった抗うつ薬となっています。なぜこのような結果になったかについてですが、これが観察研究ゆえ、自殺リスクの高い患者に対してミルタザピンが多く処方された結果ともいえます。そして結果的に防げなかった症例がカウントされているとも考えられます。
リアルワールドでは、臨床試験と異なり、アルコール依存やパーソナリティ障害、bipolarityなど様々な併存症や病態を有する患者が訪れます。そのような個々の患者の希死念慮とどう向き合うかは、単純な臨床試験の結果を超えた力量が必要となります。
続いて、興味の減退で選ばれた、デュロキセチン、ベンラファキシンです。SNRIが選ばれました。この結果について思い浮かぶのは文献12です。
デュロキセチンについての大うつ病を対象とした7つの介入試験(プラセボ対照、ないしSSRI対照)のpooled analysisです。SSRIと比較してHAM-Dの下位尺度のどの項目がデュロキセチンでは良好な治療効果が見込めるかということを解析したものです。
デュロキセチンとプラセボと有意差がみられ、SSRIとプラセボの有意差がでなかった項目は、精神運動激越, 全身の身体症状, 性的関心, 心気症の4項目でした。またデュロキセチンがSSRIより有意に改善したのは、仕事と活動, 精神運動制止,性的関心,心気症の4項目でした。
確かに興味の減退によさそうな感じです。
というわけで、今回のエキスパートコンセンサスの結果を受けてざっと自分なりにこれまでの報告を概観してみました。もっといい報告があるかもしれません。ありましたら教えていただきたいです。
今回の本題の症状クラスタリングの論文には到達できませんでしたが、これらの事項を踏まえて、次回の勉強会の記事で症状クラスタリングの論文をみてみたいと思います。1)Sakurai H. et al. J Affect Disord. 2020 Apr 1;266:626-632.
2)Int Clin Psychopharmacol. 2010 Jul;25(4):189-98.
3)Watanabe N et al. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD006528
4)Lancet. 2018 Feb 20. pii: S0140-6736(17)32802-7
5)Fawcett J et al. J Clin Psychiatry. 1998 Mar;59(3):123-7
6)Ruwe F et al. J Clin Psychopharmacol. 2016 Oct;36(5):457-64
7)Fawcett J et al. J Affect Disord 51 (1998) 267 –285 277
8)Ridout F. Hum Psychopharmacol. 2003 Jun;18(4):261-9.
9)Sasada K et al. Hum Psychopharmacol. 2013 May;28(3):281-6
10)Serretti A et al. J Clin Psychiatry. 2010 Oct;71(10):1259-72.
11)Kasper S et al. World J Biol Psychiatry. 2010 Feb;11(1):36-44
12)Mallinckrodt CH et al. Neuropsychobiology. 2007;56(2-3):73-85
13)Carol Coupland et al. BMJ 2011;343:d4551 doi: 10.1136/bmj.d4551 -
COVID-19パンデミックと精神医療
今回は、COVID-19パンデミックにおいて精神医療ができること、注意すべきことなどについて、おそらく現段階でアクセス可能な無料記事が比較的充実していると思われる、The Journal of Clinical PsychiatryのCommentaryより、重要と思われる情報を抜粋し、備忘録も兼ねてまとめておきたいと思います。
まず最初は、イタリア シエナ大学医学部のDr.Andrea Fagloliniらによる報告です1)。
シエナ大学は中央イタリア、ピサの斜塔などで有名なトスカーナ州に位置しています。
トスカーナ州の州都はフィレンツェです。
人口374万人強(2011年)のトスカーナ州に、4月15日現在で7666名(うち死亡556名)のCOVID-19陽性患者が確認されています。
人口比で島根県に置き換えると千数百名の患者が発生した状況に該当しますので、収容可能なベット数をはるかに超える患者数となっています(島根県でも同様の状況を早めに想定して、もしもの場合のためにホテルなど収容施設を県で確保してもらっておいたほうがいいのではないでしょうか)。
また非常事態において全従業員にマスクと同様にゴーグルも装着するようにしたことが記載されており、参考にしようと思います。
ちなみにイタリアでは4月15日現在1日あたり2500名を超える新規感染患者が報告され、500名以上の死者数が報告されていますが、新規患者数はピーク時の半分以下の数値となっており、緩やかにではありますが減少しているようです。
Fagloliniらによる報告では地域の中核機能を担う総合病院精神科において、何が起き、何をしてきたのか、現在までの経過がレポートされています。その概略は以下のようになります。Dr.Andrea Fagloliniらによる報告
”COVID-19 Diary From a Psychiatry Department in Italy”1月31日にローマで最初の3名の患者が発生した時には、まだシエナからは遠い場所での出来事と感じていました。
しかし2月中旬以降ロンバルディア州において急速に感染者数の増加が確認され始めてからは、状況が急変しました。3月22日までで4826名の医療従事者が感染しており、感染者数全体の9%が医療従事者でした。
これほどの状況の深刻さ、急速な感染拡大についてはほとんど想像していた人はいませんでした。
精神科についても、対応を速やかに行い、90%以上の外来診療が遠隔診療(ほとんどが電話)に切り替えられました。通常の外来診療と同じだけの時間を電話診療に費やしました。
WhatsAppやFaceTimeなどのアプリを使用可能な患者については、これらアプリを使用したビデオ診療も十分に機能し、電話よりも効果的でした。
一部の重症患者のみ、対面での診療が行われました。
マスクは乏しく、ゴーグルも無かったため、素材や滅菌の方法も含めて自作のマスク作成法についての情報を共有し(安全性は低下するものの、何もしないよりもよいだろうということで)、正規のマスクやゴーグルが入手可能になるまで、全従業員に少なくとも眼鏡ないし眼鏡がない場合にはサングラス、および自作のマスクを着用するように推奨しました。
会議については、すべてビデオ通話に変更され、外来についても椅子の間隔を離すなどして、人が話している場合は少なくとも2m、くしゃみや咳をしている場合は少なくとも3m、呼吸をしているだけの場合は少なくとも1.5mの距離がとれるようにされました。
精神科の入院患者も制限され、必要最低限、絶対必要な入院に限定されました。
大学病院は、救急部とすべての入院病棟を2つの主要なエリアに分割することを決定しました。COVIDエリアとNon-COVIDエリアで、病院内の異なる別々のエリアに配置されました。
精神科はnon-COVIDエリアでしたが、COVID陽性の精神疾患患者が入院した場合には、COVIDエリアに入院し、感染予防と管理のために職員を再教育し、リエゾンで対処しました。
北イタリアで、トスカーナ州よりもさらに感染状況が深刻な地域では、COVID陽性の精神疾患患者を、精神病棟に入院させる場合もあるようです。そのような患者は通常、身体症状よりも精神症状がより重篤なケースになります。
一般的には、多くのCOVID陽性の精神疾患患者については、遠隔医療により自宅での精神疾患治療を行っています。
入院患者でCOVID陽性の場合には、COVIDエリアに入院していますが、精神症状が重篤で、暴力的行動が顕著な場合には、COVIDエリアに保護室を設けて、そこで処遇しています。患者数が増加しているため、COVIDエリアの保護室が利用できない状況に備え、精神科病棟内の比較的大きな部屋をCOVID陽性患者のための保護室として使用できるように準備をしています。
精神科以外の部署の同僚たちは並外れた業務量と心理的負荷に直面しています。そのうち何人かは不安や疲弊状態、無力感に陥り、精神的な健康が損なわれています。この状況を打開するため、私たちは個別の心理的サポートを提供するプログラムを開始しました。
特にCOVIDエリアで勤務する医療従事者を対象に、業務のシフト終了時にWhatsAppで提供されるビデオセッションを通じて、心理的サポートプログラムが提供されています。
一部の同僚は不眠や不安を発症し、時にそれが警告症状やパニックに発展する場合もあり、さらに退職という選択肢をとる人もいました。そのような心理状態は、より合理的でない行動(マスク、ゴーグル、ガウンを着用しているときに注意を払わないなど)に結びついたり、ストレスにより生体の防御能を低下させうることを考えると、大きな苦痛であり危険でもあります。
このプログラムは、同僚たちがストレスを管理し、できるだけ多くの心理社会的健康を取り戻すことを支援する目的で行われています。
また、今後、より多くの医療従事者を支援することを目的としたグループプログラムを開始しようとしています。これは、コミュニケーションを促進し、話し、経験を共有し、仕事の終わりに恐怖や希望を表現することを目的としたものです。
病院で働く人たちは、マスクと防護服を着用したまま長時間病院内で過ごし、時には他人(同僚を含む)を感染源の可能性があると見なしていることもあります。
仕事が終わったら、イタリア国民全員が自宅で過ごすことが義務づけられているため、家に帰る以外の選択肢はありません。
そのため、仕事の終わりには、自宅にいながら、インターネットを介して、グループで社会的な接触を提供することの利益があると考えられます。遠隔通話により、経験を共有し、お互いを慰め合う場を提供することは、特に家に誰もいない人たちにとって有益であると考えています。
以上Dr.Andrea Fagloliniらによる報告でした
危機的状況において、他の部署の同僚を心理的に支援するための機能としての精神科医療の必要性がわかります。続いて、ワシントン大学医学部のDr. Ginger E. Nicolらによる、COVID-19パンデミックと精神医療についての総論的な解説2)になります。いくつかのポイントをかいつまんで引用します
Dr.Ginger E. Nocolらによる解説です。
"What Were You Before the War?"
Repurposing Psychiatry During the COVID-19 Pandemic.パンデミックの心理的影響
不確実な状況や恐怖に長期間暴露されることは、メンタルヘルスに永続的な負の影響を及ぼしえます。
2013年にPublic Health Preparedness誌に”Posttraumatic Stress Disorder in Parents and Youth After Health-Related Disasters”との論文が掲載されました3)
驚くべきことに、この論文のintroductionに現在の状況が予測されています。”専門家は来世紀中には、1800万人から1億人が罹患し、89000人から20万7千人が死亡するパンデミックが起きることを予測している”とあります(現段階での死者は世界中で13万人以上とされています)。来世紀どころか論文がでてから7年後にパンデミックが生じてしまいました。
パンデミックの災害としての特徴は、他の多くの自然災害と異なり(被災者が集合する)、被災者の分離、隔離、検疫を要する点です。そのため家族は引き離され、特に子供に対する影響に注意する必要があります。
カナダでのSARS流行後のPTSDの発生率は自然災害やテロと同程度(28.9%)であることが報告されています。
2009年のH1N1インフルエンザ流行における流行地域ないし2003年のSARS流行地域に在住していた398名の保護者へのアンケート調査(PCL-Cを用いて親のトラウマを測定し、PTSD-RIを用いて、親の報告により子供のトラウマ症状を測定した)により、隔離などを経験した親の25%がPTSDのリスクがあるとされ(非隔離経験者は7%)、隔離を経験した子の30%がPTSDリスクがあるとされました(非隔離では1.1%)。
このことはパンデミックに伴う隔離によるストレスによる親と子供に与える長期的影響を避けるため、コミュニケーションを促進するような迅速な介入が必要であることを示唆する結果といえます。研究的視点の重要性
同時に重要な着眼点として、パンデミックの脅威とその精神衛生への影響を後世のために記録する義務があります。
具体的には精神疾患を有する人々はどのように対処しているのか?孤立、不確実性、必要なケアへのアクセスの欠如に対して、どのような反応を示しているのか?どのような戦略が機能しているのか?などの観点からの研究に取り組む必要があります。
治療薬の探索と向精神薬
最近のCOVID-19関連基礎研究では、69種類のFDA承認薬が、治療薬候補として報告されており5)、そのうちのいくつかは向精神薬に属します。
例えば、COVID-19に関連した肺および心臓の損傷はサイトカインストーム6)に起因していると言われており、免疫反応を最小限に抑える治療法が探索されています。
抗うつ薬の一部は、シグマ-1受容体(S1R)アゴニストとして作用し、S1Rの活性化は細胞ストレスを緩和し(小胞体ストレスセンサーであるIRE1の活性を阻害することで)、サイトカインの発現を抑制するといわれています。S1Rアゴニストは齧歯類では心保護作用があり、炎症反応を抑制し、敗血症動物モデルでは生存率を高めています。(S1Rアゴニストとしてはフルボキサミンやアミトリプチリンなどでしょうが、私個人的には、細胞内レセプターであるS1Rと抗うつ薬との関連性において、現実的な治療的有効性についてはとても懐疑的な立場です)さらに、マウントサイナイ医科大学のDr. Joseph F. Goldbergは、”Psychiatry's Niche Role in the COVID-19 Pandemic”と題し4)、精神科医の役割について解説しています
Psychiatry's Niche Role in the COVID-19 Pandemic
アメリカでは多くの州や施設が、地域社会でパンデミックに関連した苦痛を感じている人のために、電話により精神保健の専門家にボランティアでサービスを提供するよう求めています。
カウンセリングサービスを提供する精神科医は、純粋なカウンセリング(主に能動的で共感的な傾聴によって定義される)とは別に、以下のような点に注意する必要があります。
(1)安全性のリスクと危険因子の評価(例えば、独居、経済的問題などの存在など)。ただし遠隔診療においては、アルコールやベンゾジアゼピンなどの使用障害についてのアセスメントが困難である問題がある
(2)病的水準の精神病理と非病理的レベルの苦痛の鑑別を行うこと。過去の病歴から現在再発し、より正式な介入を必要としている可能性があるかどうかの確認を行う。正常な不安状態(了解可能な範疇で無力化していない状態)と病的な不安状態(麻痺、非生産的な状態、無力化した状態など)を鑑別する。大きな人生の激変の後の「うつ病」については、悔しさやフラストレーションなどの情動変化を伴う場合よりも、無気力や絶望、失感情を伴う場合は、病的水準が高い可能性に注意する必要がある。
(3)外傷的出来事への暴露が将来の心的外傷後ストレス障害の素因となる可能性が高いかどうかを判断する。
(4)不眠症や不安感など、あまり病的ではない苦痛を伴う症状に対して、短期的な薬物療法が適切であるかどうかを判断する。クライシスワークの基本的な治療の焦点は、
(a) 電話での支援、教育、スキルの提供を行う。適切な場合には的を絞った薬物療法を提供することで、人々の当面の身体的・情緒的苦痛を管理すること。
(b) 目に見える問題により良く対処し、解決するための戦略を考案し、実行することを支援すること
となります。危機による「苦痛」には、一般的に不安、焦燥感、不眠、先入観、悲しみ、健康の喪失の恐れ、および孤立、孤独感が伴います。
身体的苦痛と自律神経亢進を軽減するための行動戦略には、リラクゼーションのテクニック、瞑想とマインドフルネス、運動、ヨガ、スピリチュアルな活動、(仮想的な)グループベースの支援などがあります。
具体的な問題解決の努力には、適応的な対処スキルを向上させ、日々の生活構造を維持すること、社会的な距離が離れている中で社会的孤立を最小限に抑えるためにインターネットの創造的な利用法を見つけること、育児、家庭教育、財政管理について戦略を練ること、不適応な対処スキル(例えば、悪い衝動の制御、物質使用や行動依存症、自傷行為、セルフケアの喪失)に対処することが含まれます力動的見地からは、ストレスや恐怖により一部の人において退行が生じ、好訴的となったり、様々な権利の要求を起こしやすくなることに注意が必要です。(未熟な防衛機制が発動しやすくなるということですね。お店で執拗に攻撃的に店員さんにマスクを求めたりする一部の人の心理はこれでしょうか)
最後に第1線で働く同僚の健康に対するリエゾン活動。および精神科医自身のセルフケアの重要性について触れ締めくくられています。
この論文でも触れてありましたが、隔離下においてはアルコールに関する問題には注意したいものです。しかし遠隔医療では、この問題への介入がより困難となることもまた課題です。
1)Fagiolini A et al. J Clin Psychiatry. 2020 Mar 31;81(3). pii: 20com13357.
2)Nicol GE et al. J Clin Psychiatry. 2020 Apr 7;81(3). pii: 20com13373
3)Sprang G et al. Disaster Med Public Health Prep. 2013;7(1):105-110
4)Goldberg JF. J Clin Psychiatry. 2020 Apr 7;81(3). pii: 20com13363
5) Gordon DE et al. A SARS-CoV-2-human protein-protein interaction map reveals drug targets and potential drug-repurposing. bioRxiv website. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.002386v3. March 27, 2020.
6). Mehta P, et al; Lancet. 2020;395(10229):1033–1034. -
エビデンスの質について
2020年04月14日
エビデンスには質があり、時に著名な雑誌に掲載された論文についても結果がmisleadingである可能性があることに注意が必要です。
臨床家は論文の質の良し悪しを慎重に見極める必要があります。
最近ではNew England Journal of Medicine誌にCOVID-19に対するremdesivirのcompassionate use(患者自身の申し出を起点とした未承認薬の投与。薬剤が生命リスクの高い疾患を対象としたものであり、代替的治療法がないものの場合、未承認薬であっても条件付で投与が承認されるもの。日本でいうところの患者申出療養制度ないし拡大治験。両者はちょっと違いがあり、申し出のあった薬剤が治験中であれば、患者申出療養制度ではなく拡大治験に組み込まれる。この論文に日本での患者さん(in Japanとあるので国内投与でしょう)が9名入っていて、日本での患者申出療養制度での投与承認はまだ6件しかなく、その中にCOVID-19は入っていないので、拡大治験でしょうか?海外で行われているExpanded accessに参加する方法もありますが、それだと海外にいかないといけないので、国内実施であれば、拡大治験だったのでしょうか?どういういきさつでcompassionate useという表現が使用されているのかは興味があるところです)についての症例報告がありました1)が、これはオープン試験で対照もなくblindingもされていないので、エビデンスの質としては低めということになります。現在進行中のプラセボ対照二重盲検試験の結果次第では、結論はどうなるかわからないというところです。
さらに観察研究により得られる帰結の脆弱性について、精神科が関連する領域での実例を挙げてみたいと思います。
2000年のLancet誌にスタチン使用と認知症リスクの関連を調べたnested case-control study(以下に述べる今回問題にしている論文と同じスタイルです)の報告がなされました2)。nested case-control studyは前向き研究でありながら、前向きの観察期間終了後にcase-control studyを行うというもので、コホート研究とcase-control studyの良いところ取りのような研究デザインになります。
nested case-control studyについてはネットで閲覧可能な嶋本先生による文献3)にわかりやすい解説があります。
このLancet報告2)では、スタチン使用により、認知症(タイプは区別しない)の罹患リスクが7割くらいも有意に減るというインパクトのある結果でした。この結果もよくみるとスタチン使用歴2年未満の結果が全体の罹患リスクの結果に大きな影響を与えているように見え、2年以上使用の結果はそれほどリスクを下げているようにみえないことから慎重な解釈が必要なことはわかるのですが、それでも有名雑誌に掲載された結果の影響は大きく、その後しばらくはスタチンで認知症を防ぐという風潮になったのは想像に難くありません。
しかし、そのような幻想は2年後に同じくlancet誌に公表された2つの介入試験の結果4)5)で打ち砕かれます。
HPS 2002およびPROSPER試験とよばれるプラセボ対照無作為割付比較試験です。特徴はどちらも非常に大規模であること(HPS 2002はシンバスタチン群とプラセボ群いずれも10000名以上、PROSPER試験はプラバスタチン群、プラセボ群いずれも約3000名)さらに、どちらも長期間であること(HPS 2002は5年、PROSPER試験は約3.2年)です。
ここまで大規模な介入試験の結果のエビデンスの質はとても高くなります。
HPS 2002試験のエントリー患者は40-80歳で冠動脈疾患,非冠動脈性閉塞疾患,糖尿病などで治療中の患者で、主要評価項目はすべての原因による死亡、冠動脈性心疾患による死亡などで、結果はシンバスタチンは全死亡、冠動脈性心疾患による死亡を10%程度有意に低下させるというものでした。認知症発症率も評価されており、0.3%ずつで有意差がありませんでした(自殺企図率も0.1%ずつで有意差なし、その他の精神疾患の発症率もスタチン0.7%対プラセボ0.6%で有意差なし)。
スタチンは動脈疾患のリスクを有する患者について、約5年間の使用で認知症の発生リスクを低減させることはなかったとの結論になります。
PROSPER試験では、70-82歳で動脈疾患の既往(冠動脈、脳血管性、末梢性)ないし喫煙や高血圧、糖尿病などを有しハイリスクの患者が対象となりました。主要評価項目は冠動脈疾患死ないし非致死性心筋梗塞ないし致死性ないし非致死性脳梗塞の発生率であり、プラバスタチンはこれらすべての発生率を約15%有意に減少させるとの結果でした。一方で認知機能の低下についても評価されており、MMSE、語想起課題、stroop testなどで測定した認知機能の悪化度は有意差なしとの結果でした。
スタチンは約3.2年間の使用で認知機能の低下を有意に防ぐ効果はなかったということになります。
以上2つの質の高い長期大規模臨床試験の結果により、現在ではスタチンが認知症を防ぐ効果は(少なくとも5年程度の使用では)ないとの結論になっています。
だからといって、観察研究の意味がないわけではありません。介入研究が困難なほど長期間にわたる暴露の結果がどうかについては観察研究に頼らざるをえません。
スタチンと認知症リスクについても、最近でも観察研究の結果が報告されて続けており6)、それはもはや介入研究では手が届かない10年単位の観察期間を設けた長期試験であったりします。
そこでは、エビデンスの質は低いものの、高用量のスタチンでは認知症発症リスクが低かったなどの報告もみられています。
より長期の経過をみていくことの意義は、アルツハイマー型認知症のアミロイドβ仮説において、アルツハイマー型認知症発症の15-20年前からAβ pathologyが徐々に脳内で進行しているとの仮説があるためです
この仮説を検証するには、MCIレベルの患者への介入では時すでに遅く(最近の抗Aβ抗体による第3相試験がことごとく失敗しているように)、もっと早期からの介入が必要ではないかとの推測になります。
スタチンは基礎実験でAβを減少させるとの報告7)があり、そうであれば、HPS 2002ないしPROSPER試験の15年予後などはとても興味があるところです。
HSP 2002については最後の患者のエントリーから23年くらいたっているため、もし予後がわかれば、何か興味深いデータが得られるかもしれません。
このように観察研究と介入試験では結果が異なることがよくあります。この差の原因の1つはIncident biasとして説明されています。
そもそも観察研究においては、スタチンを内服した群とそうでない群とで、性質が異なる(健康に対する意識が高いなど)だろうというものです。
おそらくはこのような取り除けないbiasの影響により観察研究の結果が影響を受けてしまったのではないかと考えられています。
以上エビデンスの質が重要であるとの一例をみてみました。
さて、前置きが長くなりましたが、今回の本題です。観察研究では、結果についてどう考えればいいのか、解釈に困る論文がでることもしばしばあります。
今回の論文はコホート研究の結果ですので、エビデンスの質は高いわけではなく、数年後にはひっくり返っている結果かもしれませんが、いったいどうしてこうなったのか。考えてもわかりません。
どう解釈すればいいのか、いいアイデアがあったら教えていただきたいです。
困った論文はこちら”Associations of Benzodiazepines, Z-Drugs, and Other Anxiolytics With Subsequent Dementia in Patients With Affective Disorders: A Nationwide Cohort and Nested Case-Control Study.”8)です
気分障害患者において、ベンゾジアゼピン、Z-drugsないしその他の抗不安薬使用とその後の認知症発症リスクについてのnested case-control studyになります。内容はざっと以下のようになります背景
ベンゾジアゼピン系薬剤は、その抗不安作用、催眠作用のため多くの国で処方されているが、長期使用に伴う有害事象が注目を集めている。
長期使用による認知症リスクについては、2018年にメタ解析が出版され、5本のコホート研究と10本の症例対照研究が解析対象となり、全体としてあらゆるベンゾジアゼピン系薬剤の使用による認知症発症のオッズ比は未使用と比較して1.38と有意差をもって上昇するとの結論9)であり、さらに初発症状バイアス(疾患の発症初期にベンゾが処方されやすくなるバイアス)やうつや不安併存などの交絡因子を考慮してもなおわずかに有意であるとの結論であった10)。しかし、recall biasなどが問題となる症例対照研究がメタ解析の対象として多く含まれており、用量と発症リスクの関連を調べたいくつかの報告の結果は一定しておらず、用量と発症の関係、長時間作用型と短時間作用型とのリスクの違い、暴露期間によるリスクの違いなどはよくわかっていない。
コホート研究での結果は、結論が一定していない。
これまでの報告では、ベンゾジアゼピンを処方するに至った適応症に関連する交絡因子の調整が不適切であった。気分障害は認知症リスクと関連していると言われているが、しばしばベンゾジアゼピン系薬剤が併用される。また多くのコホート研究による報告のほとんどが高齢者集団を対象としており、終末期におけるベンゾジアゼピンの使用もしばしば行われているが、終末期状態であることについての解釈は行われていない。
今回、併存症による交絡を最小化するために、気分障害患者を対象に、ベンゾジアゼピンとZ-drugsを使用した場合に将来の認知症リスクがどうなるかについてコホート研究を行った。さらにベンゾジアゼピンのタイプ(長時間か短時間か)、Z-drugsかどうかで認知症リスクが違うかどうかについても検証した。
対象と方法
デンマークで、1996年1月から2015年12月までの間で、気分障害(F3)で最初に受診した患者 N=245541
the Danish Psychiatric Central Research Registerもしくはthe Danish National Patient Registryもしくはthe Danish National Prescription Registryなどの患者登録データベースを使用しICDコードで気分障害、認知症患者を同定。処方データベースで処方内容、量、期間を同定した。
前向きコホート研究、nested case-control studyを行った。
共変量として、うつ病のタイプ(bipolar、軽度反復性、中等度反復性、重度反復性、持続性抑うつ障害など)、診断時期、アルコール乱用歴、物質使用障害歴、糖尿病、心血管疾患、抗精神病薬処方の有無、抗うつ薬処方の有無、教育歴(低、中、高、不明)、性別、年齢、婚姻状態を抽出結果
気分障害患者の75.9%(N=171287)がベンゾジアゼピンないしZ-drugsを使用
うち63.1%(N=148620)はエントリー前に1度以上ベンゾないしZ-drugsの処方歴あり(prevalent user)
55.7%の患者はベンゾジアゼピンとZ-drugの両者を処方
フォローアップ期間の中央値は6.1年
9776名が認知症と診断
調整後のnested case-control studyでは、ベンゾジアゼピンないしZ-drugs処方により認知症リスクの有意な上昇なし。長時間作用型、短時間作用型いずれも有意差なし
一方コホート研究においては、ベンゾジアゼピン処方はエントリー後2年間において、認知症リスクを低減させた(調整後ハザード比 0.82)、Z-drugs使用も有意に認知症リスクを低減(調整後ハザード比 0.82)。エントリー後2-20.1年までの結果は認知症リスクについて有意差なし(ベンゾジアゼピン処方による調整後ハザード比 0.97)、Z-drugs使用の調整後ハザード比 0.96
コホートでの解析ではベンゾの通算用量や期間と認知症リスクとの有意な関連はなかった。一方でnested case-control研究での解析結果では、最も通算用量の少ないベンゾジアゼピンを処方された群は、全く処方されたことのない群と比較して、わずかな認知症リスクの上昇がみられた(オッズ比 1.08)。
一方で最も通算用量の多い処方を受けた群は有意に認知症発症リスクが低い(オッズ比 0.83)結果となった。このパターンはすべてのタイプ(ベンゾ、Z-drugs、短期作用型、長期作用型)の薬剤でみられた。
議論
前向き研究として過去最大規模の観察研究の結果
Nested case-control studyの結果では通算低用量のベンゾ使用歴でわずかに認知症リスクの増加、一方通算高用量のベンゾ処方はむしろ認知症リスクを下げる結果となった
コホート研究の解析結果で2年間の認知症リスクが低い結果については、気分障害と診断された患者について、最初2年間は臨床家が認知症と診断しにくいことと関連している可能性がある。
認知症発症率について、うつ病の重症度やアルコール乱用などの交絡因子について調整したstudyはこれまでになく、その点で新しい知見となる
意外なことにベンゾの通算処方量が最高に属する群は認知症リスクの低下と関連するとの結果となった。これは過去にスイスでの症例対照研究で報告された傾向11)と類似している。今後の検証課題となるコメント
最も通算用量が多い、というのがどのくらいか明示されていなくて、具体的にどのくらいかがよくわからなかったです。supplementary figure S1ではtotal defined daily dose(DDD)で1500くらいが最大になっているので、たとえばジアゼパムのDDDは10mg、ロラゼパムは2.5mgなどとWHOが決めているので、これの1500倍の総処方量が最高通算処方量クラスということになるのでしょうか。結構な量ですね。
今回の割と規模の大きなコホート研究では、ベンゾジアゼピンやZ-drugsが認知症リスクの増加と関連するという明らかな証拠は得られませんでした。
それどころか、通算ベンゾ処方量が多いと、リスクが減る結果になっています。
この論文のエビデンスの質は高くありませんので、この結果をそのままうのみにすることはできませんし、今後否定される可能性もありますし、ベンゾ長期使用の有害性を考慮すると、到底実用的な結果ではありません。きっとなんらかの要因により、このような結果になっているのかと思いますが、それについては論文の考察でも触れられておらず、私にはわかりません。コロナウイルスが落ち着いてからの勉強会で専攻医のみなさんと議論できればと思います。
1)N Engl J Med. 2020 Apr 10. doi: 10.1056
2)Jick H et al. Lancet. 2000 Nov 11;356(9242):1627-31.
3)嶋本 喬 日循協誌 1992 第26巻第3号 198-199.
4)Heart Protection Study Collaborative Group. Lancet. 2002 Jul 6;360(9326):7-22.
5)Shepherd J et al. Lancet. 2002 Nov 23;360(9346):1623-30
6)Chang CF et al. Medicine (Baltimore). 2019 Aug;98(34):e16931
7)Dhakal S et al. Int J Mol Sci. 2019 Jul 19;20(14). pii: E3531.
8)Osler M et al. Am J Psychiatry. 2020 Apr 7:appiajp201919030315
9)Lucchetta RC et al., Pharmacotherapy 2018; 38:1010–1020
10)Penninkilampi R et al. CNS Drugs. 2018 Jun;32(6):485-497.
11)Fakienne A. Bietry et al. CNS Drugs (2017) 31:245–251 -
産後うつ病に関する話題
2020年04月10日
はじめに
GABA A受容体のアロステリック調節剤、および産後うつ病の発症メカニズムについて興味深い話題になります。
日本では未承認ですが、2019年5月にFDAが産後うつ病に対してbrexanoloneを承認しました。brexanoloneはGABA A受容体のアロステリック調節剤になります。産後うつ病はDSM-Vでは産後4週までに発症のうつ病エピソードと定義されていますが、実際には産後4週を越えての発症もありうるものです。またその半数がすでに産前からうつ病エピソードを発症しているとされ、この場合、周産期うつ病とよぶのが妥当とされています。
発症率は10-15%といわれています。
産後3日以内にみられる悲しさ、惨めさなどの感情はマタニティーブルーと呼ばれ、多くの母親が経験するものです。通常は2週間以内に軽快しますが、産後うつ病になると症状が数週間から数か月間続き、日常生活に支障をきたします。
平成29年7月に日本産婦人科医会がマニュアルを作成しており、産後うつ病の早期発見、包括的な介入を目指してシステム作りが進んでいます。
2018年のLancet誌に産後うつ病に対する新規治療薬候補としてbrexanoloneの第3相試験の結果が公表されました1)。後述しますが、産後うつ病の病態仮説としてGABA系の異常が提唱されています。
プロゲステロン代謝物であり、GABA A受容体のアロステリック調節作用を有するallopregnanoloneが産後に減少することが報告されており、brexanoloneはAllopregnanoloneの静注可能な可溶体とのことです。
Lancet論文1)では、2つの第3相試験(study1とstudy2)の結果がまとめて報告されました。study2よりもstudy1の方がより重症度が高い群がエントリーされています。
第3相試験の概略は以下の通りとなります。******
対象患者
18-45歳の妊娠28週目(第3期)以降産後4週以内に大うつ病を発症(DSM-IV)しスクリーニング時点で産後6ヶ月以内のもの。HAM-Dで20-25点(study 2)ないし26点以上(study 1)
方法
プラセボ対照無作為割付比較試験
投薬中と投薬後4日間のみ授乳中止患者はBrexanolone 90ug/kg毎時群(N=45(study 1)、N=54(study 2))、60ug/kg毎時群(N=46(study 1))、プラセボ群(N=46(study 1)、N=54(study 2))の3群に無作為割付。
Brexanolone 90ug/kg毎時群では、最初4時間は30ug/kg毎時で静注、4-24時間は60ug/kg毎時、24-52時間は90ug/kg毎時、52-56時間は60ug/kg毎時、56-60時間は30ug/kg毎時で投与。
Brexanolone 60ug/kg毎時群は24時間-56時間が60ug/kg毎時
投薬期間は60時間の持続静注のみ
主要評価項目はHAM-Dの変化量。評価は投与開始7日目と30日目の2回。
結果
脱落率はstudy 1では18%、study 2では7%。副作用出現率や脱落率は群間で有意差なし
投与開始60時間でのHAM-Dの変化量はstudy1(より重症な群)では90ug群では19.5点、60ug群では17.7点、プラセボ群は14.0点で実薬群はいずれもプラセボより有意に改善。Study2では60時間後のHAM-Dの変化量は90ug群は14.6点、プラセボでは12.1点で有意差あり(速効性があることがわかります)
30日後では、study 1では有意差あり。Study 2では有意差なし(より軽症群がエントリーされており、プラセボの改善も大きかった)
study1とstudy2を併せた結果では投与60時間後、30日後いずれもbrexanolone投与はプラセボより有意にうつ症状を改善するとの結果になりました。*****
この結果を受けて、FDAは産後うつ病に対してbrexanoloneを承認しました。
めでたしめでたしというところですが、どうもすっきりしません。
そもそもGABA A受容体アロステリック調節剤といえば、そのまんまベンゾジアゼピンではないですか?
じゃあベンゾと何が違うのか?依存性はないのか(Brexanoloneは単回投与なのでその心配はなさそうですが、2019年9月に経口投与可能な類似薬剤SAGE-217の大うつ病に対する第2相試験の結果が公表されており2)、こちらは依存性、耐性も心配しなければいけなさそうです)そのあたりがとても疑問なところでした。
その疑問に対する現段階での回答にあたるような論文3)がでていましたので、読んでみました。内容の概略は以下のようになります。
*****
神経ステロイドについて
神経ステロイドの概念はBaulieuにより1980年代に提唱された、コレステロールやステロール前駆体より中枢神経において合成される内因性ステロイドである
その後内因性および外因性ステロイドは中枢神経において多様な生理作用を有することがわかり、神経活性ステロイド(NAS : neuroactive steroid)と呼ばれるようになった。
合成NASにおいては、特定の受容体への親和性を特異的に強めることができるGABA A受容体について
GABA A受容体については、α1-6、β1-3、γ1-3、δ、ρ1-3、π、Θのサブユニットが存在することが知られている。
GABA A受容体は2つのαサブユニット、2つのβサブユニット、さらにもう1つのγやδなどいずれかのサブユニットから構成されることが多いシナプス後膜に存在して、周期的(phasic)な抑制作用を発揮するGABA A受容体はγ2サブユニットを含む。一方で、シナプス外に存在し、持続的な(tonic)抑制をもたらすGABA A受容体はδサブユニットを含むことが多い
ベンゾジアゼピンはGABA A受容体のベンゾジアゼピン結合部位に結合し、アロステリックにGABA A受容体のGABAに対する感受性を高める
NASの結合部位はベンゾジアゼピンと異なる
δサブユニットを含むGABA A受容体の方がNASにより活性化されやすい。NASはδサブユニット含有GABA A受容体、γサブユニット含有GABA A受容体双方に作用する
一方ベンゾジアゼピンはδではなくγサブユニットを含む周期的抑制に関与するGABA A受容体に作用する
GABA A受容体とNAS
様々な神経活性ステロイドのGABA A受容体への作用には3種類ある第1群はSAGE-217、 Brexanolone、Allopregnanoloneなどのpositive allosteric modulator(PAM)であり、GABA A受容体のGABAへの感受性を高めるよう作用する
第2群はpregnenolone、DHEASなどのnegative allosteric modulatorであり、GABA A受容体のGABAへの感受性を弱め、さらに第1群のNASの効果と競合し、PAMに対して抑制性に作用する
第3群はGABA A受容体に対する固有活性がわずかないし無い群である
GABA A受容体とNAS、ベンゾジアゼピン
ベンゾジアゼピンに抗うつ作用がみられず?(コメント:これについては断言はできないところです。理由は後述します)、NASが抗うつ作用を有するのは、NASがδサブユニット含有GABA A受容体にも作用することによることかもしれない
一方で抗不安作用については、αサブユニットを含むGABA A受容体が関与しているとの報告があり、NASの抗不安作用はαサブユニット含有GABA A受容体を介したものかもしれない。ベンゾジアゼピンもαサブユニット含有GABA A受容体に作用するため、ベンゾの抗不安作用もαサブユニット含有GABA A受容体を介したものではないかといわれている
神経ステロイドの抗うつ作用について
内因性の神経ステロイドはアストロサイトや神経細胞などでストレスなどに反応して産生亢進することが知られている。ストレスを受けて数分後には脳内Allopregnanoloneが増加し、その後2時間以上増加した状態が持続することが実験的に報告されている。
さらに、これらのストレス刺激は、グルタミン酸NMDA受容体刺激をもたらすことがしられており、ストレス暴露中にNMDA受容体遮断を行うと内因性神経ステロイド増加が抑制されることが知られている
低濃度のNMDA投与は海馬CA1錐体細胞での神経ステロイド産生を促進する。
以上の結果は、神経ステロイドがストレス反応性に産生されるstress modulatorであることを示唆している
急性ストレスの場合には、神経ステロイド産生は増加するが、慢性ストレス下においては、 Allopregnanoloneとその前駆体DHPが減少することが知られている。一方でpregnenoloneやprogesteroneは減少しない
慢性ストレス下の動物モデルにおいて、 Allopregnanolone産生を亢進させると行動異常が正常化することが知られている
慢性ストレスは、 Allopregnanolone減少をもたらし、うつ症状につながるのかもしれない
大うつ病患者の髄液中および血中Allopregnanolone減少が報告されている
いくつかの報告では、うつ病の治療成功後にAllopregnanolone濃度が改善したことを報告している
さらにうつ病死後脳研究において、前頭前野の錐体細胞において1型5AR(神経ステロイド合成に関与する酵素)の発現が50%減少していたことが報告されている。うつ病を合併するPTSD患者においても同様のAllopregnanolone濃度減少を示唆する報告がある。
男女で酵素活性の欠損に性差が存在するとの報告があり、男性では5AR活性の低下が、女性では3α-hydroxysteroid dehydrogenaseの異常が報告されている
産後うつ病と神経ステロイド
産後うつ病では神経ステロイドの変化を伴うと考えられている。
多くの女性が妊娠後に一過性の気分変動を経験し、産後に持続的な気分障害と伴う産後うつ病の罹患率は15%との報告がある。その発症時期は妊娠第3期から産後6か月までの報告がある
妊娠期間においては、 Allopregnanoloneなどの神経ステロイドは劇的に増加し、出産とともに急激に減少する。一方で、GABA A受容体δサブユニット発現量についても変化するが、妊娠期間中は発現抑制され、産後神経ステロイドの減少と同時に発現増加するが、発現増加までラグが存在する。
そのため、このラグが存在する間において神経細胞の過剰興奮状態がもたらされ、高ストレス状態ないしうつ状態がもたらされるのではないかとの仮説が存在する。
これらは動物モデルでの現象であり、産後神経ステロイド投与で産後の行動異常が是正されたという。
またδサブユニット発現をノックアウトないしノックダウンしたモデル動物においては、非妊娠期間では正常な行動を示すが、産後においては顕著な行動異常(ストレス様行動や仔殺し)を呈することが報告されている、さらにNAS投与により行動異常の是正が報告されている
依存性リスク
よくわかっていない
*****
論文の概略は以上となります。ベンゾジアゼピンとの違いがよくわかりました。また産後うつ病の病態仮説についても大変興味深いものです。依存性、耐性についての検証は今後の課題というところでしょうか。
SAGE-217の今後の動向が気になります。
ところで、この論文3)中に、ベンゾジアゼピンは抗うつ作用がないとの一文がありましが、これについてはそう言い切ることもできません。またそうでないというエビデンスも不十分です。というのは、昔の論文で、あまり知られてはいないかもしれませんが、1995年にこういう論文”Treatment of depressive outpatients with Lorazepam, alprazolam, amytriptyline and placebo”4)がでているのです。
結果は6週間で実薬群はいずれもプラセボと有意差をもって有効であったというものでした(ベンゾとアミトリプチリン有意差なし)。
評価項目はHAM-Dなどであったため、それは当然だろうとも思えます。というのもHAM-Dには不眠や不安、焦燥などの項目が入っており、当然ベンゾはそれらを解消してくれることが期待できるはずです。
しかしながら、HAM-D下位尺度の改善度の図もあり、HAM-D1(抑うつ気分)、HAM-D2(罪責感)、HAM-D3(自殺)、HAM-D7(仕事と活動)などの項目もプラセボと明確な差があるようなのです。
これをどう解釈すればいいのか。その後の検証もあまりないようなので、なんともいえませんが、少なくとも実用的な結果ではないことは確かです。ベンゾを長期間用いることは、それこそ依存性、耐性、離脱症状などのため薬漬けとなるリスクがあり、全く推奨できません。
その点においてもSAGE-217が今後どのような評価になるのか、興味深いところです。
1)Meltzer-Brody S et al. Lancet. 2018 Sep 22;392(10152):1058-1070.
2)Gunduz-Bruce H et al. N Engl J Med. 2019 Sep 5;381(10):903-911
3)Zorumski CF et al. Neurobiol Stress. 2019 Sep 27;11:100196. doi: 10.1016
4)G Laakman et al. Psychopharmacology (1995) 120:109-115 -
新型コロナウイルス感染症に関した話題
4月1日にアメリカ睡眠医学会のWebinarが行われました。
この時すでにアメリカでは新型コロナウイルスが猛威を振るっており、社会的不安が高まる状況の中で、睡眠専門家がどのようにセルフケアすべきかについて、メリーランド大学の睡眠生理学者のEmerson Wickwire博士が講演しました。Zoomで行われ、アメリカ東部時間の正午から開催で、日本時間の午前4時開始だったので、私は待ち構えていたのですが、結局寝落ちしてしまいました。しかしその後ありがたいことにYoutubeで無料公開されたので、誰でも見ることができます。
興味がある方は”Self-Care for Sleep Professionals During Difficult Times”で検索してみてください。内容は、いかに不安と向き合い、不安を減弱し、睡眠に入りやすくするか、そして終息後に向けて、というものでした。
内容の多くは第3世代認知行動療法がベースにするマインドフルネスの概念などから引用されたもので、馴染みのある内容でしたが、あらためて聞いてみて、実際にwhat if・・よりもwhat is・・に注目するという辺りは、私自身の最近の入眠困難にも効果があった気がします。CBT-iなど、どんなものか耳学問では知っていても、いざ自分がとなるとなかなか自分に対してはうまくはいかないものです。
内容のアウトラインを以下に書いてみます。緊張からの開放
目を閉じて、自身の身体の緊張している部位を感じます。
次に、ストレスをクールダウンさせるための呼吸を3回行います。腹式呼吸で行い、横隔膜が下がり腹部が膨らむことを意識します。
4秒で息を吸い、8秒で吐く。それも合計3回繰り返します。
これにより緊張から解放されます。心の柔軟性を開放し、不安を減らす
次に心の柔軟性を開放します。心が柔軟性を失うと、慢性的な不安に取りつかれたり、慢性的なうつ状態に陥ったりします。
不安の一部は恐怖から生じます。
恐怖は不確実性が存在するとより強まります。
不確実性を無くすことから始めましょう。
まずは不安に思うことを書き出します。
次に自分がどうしたいかを明確にします。
さらにさまざまな代替案を考えます。ブレインストーミングの手法を用います。より自分自身が不安にならない方法を考えます。
たとえば、収入を失うかもしれないという不安であれば、まずファイナンシャルプランナーと話し、ついで公的扶助について調べ、さらに上司に悩みを打ち明けるなど。
ついで考え出した案について、賛否両面から評価します。最後に行動します。
不安を防ぐには、ネガティブな考えに陥る材料を遮断し。不確実な情報源からの情報を遮断し、信頼できる情報源のみから情報を得ることが重要です。ワイドショーやtwitterなども、不要な不安を煽られるならば遮断しましょう。
覚醒を制御する
覚醒を制御するためには、儀式的なプロセスを構築することが望ましいです。
例えば、仕事が終わりメールを遮断することが最初の段階となります、次いでTVを見るなどするリラックスする時間帯をつくり、TVを切ることで次の段階に進みます。睡眠前段階では、歯磨きなどを行います。歯磨きを終えることで次の段階に進み睡眠に入るようにします。
このように一連の流れを儀式化、習慣化することにより、覚醒を制御しやすくなります。
ポジティブな感情を増やす
認知行動療法の基盤でもありますが、感情と行動と思考は相互に影響しあっており、どれかを変えることで、お互いを変化させることができるとの仮説があります。
どんな小さなポジティブな感情であっても、行動や思考を変化させうるとの考えに基づきます。逆にちょっとした行動や思考がポジティブな感情を産み出しうることとなります。
最初のステップは、現実は何かに集中することです。もし・・だったらではなく、現実は何かに集中します。もし・・だったらは多くの不安を産み出します。例えばもし感染が広がったらどうしようとか、もし彼氏が浮気していたらどうしようとか、そういう考えではなく、現実のこと、現実に起きたことのみに集中します。
30秒だけ、視覚以外の感覚を用いて、何が聞こえるか、どんなにおいか、どんな味か、どんな感触か、を描写します。
これにより、ポジティブな感情への感性を高めます。
続いて、3つから5つの、ちょっとした感謝できる事実の出来事を思い浮かべます。
例えば、朝がとても静かな時間だったとか、子供と一緒に葉の上の水滴探しをしたとか、家族と歩くときに日差しを感じられたとか、誰かと一緒に過ごせたこととか、ちょっとした日常の中の感謝できることをでいいのです。寝付くときに、頭の中をぐるぐると不安が渦巻く状況においても、この手法は適応できます。頭の中を、もしも・・ではなく、現実の出来事で埋めていきましょう。そうするといつの間にか眠りに入るでしょう。
他にもいくつかのtipsがありましたが、専門家が話すとなんとも説得力のあるお話でした。明日にでも緊急事態宣言が出されようかという状況の中、少しでも皆さんが心身ともにご健康であることを願います。
最後に、私自身が参考にしているサイトをご紹介します。
もちろん行政機関からの情報は重要ですが、これからどうなるのか、どのように注意すべきかという科学的な根拠と指針が示されているという点で、参考になりました。モデルに基づいた数式からの解析ですが、多くの専門家が信頼できる情報源として認めるところと思います。(基本再生産数3.0を仮定しているので、実際よりも多く見積もられているかもしれません)
佐藤彰洋教授による情報です。
https://www.fttsus.jp/covinfo/considerable-discussion/
ここから得られる情報で重要な点は、仮に基本再生産数が3.0であり、このモデルが妥当であれば、直接接触の機会を8%まで減らしても、その後ダラダラと感染者数が横ばいな状況が続いていくということです。
人と人との接触機会を減らすことに躊躇してはならないというメッセージが伝わります。