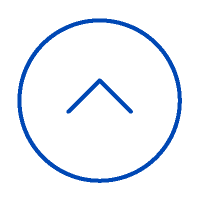-
CYP遺伝子多型と向精神薬
2020年12月01日
・11月25日付JAMA Psychiarty誌にCYP2D6とCYP2C19の遺伝子多型に関連して、活性型に応じてどの程度曝露量(時間ー濃度曲線のAUCなどで定義)が異なるかについてのメタ解析結果が公表されていましたので(文献4)、まとめておきます。いくつか臨床的にも注意すべき結果があります。本文中何故か誤植が何カ所か残ってたりして気になりましたが
・ゴーシェ病治療薬のサテルガ(グルコシルセラミド合成酵素阻害薬)については、投与前にCYP2D6遺伝子型を確認し、CYP2D6遺伝子多型が通常活性型(EM:Extensive Metabolizer)ないし中活性型(IM:Intermediate Metabolizer)の場合に投与可能とされています。CYP2D6遺伝子多型検査は保険収載されておらず、CYP2D6遺伝子多型検査を先進医療として実施している医療機関もあります。
・またタモキシフェンはCYP2D6で代謝され抗腫瘍作用を発揮するため、日本人の約6割を占めるIM群では、用量調整が必要ではないかと考察されています(文献1)
・以前の記事でも触れましたが、CYP2D6、CYP2C19に関しては、各酵素の代謝活性に応じて低活性型:PM(Poor Metabolizer)、中活性型:IM(Intermediate Metabolizer)、通常活性型:EM(Extensive Metabolizer)、超高活性型:UM(Ultra-Rapid Metabolizer)に分類されています。
・日本人におけるCYP2D6およびCYP2C19の各活性型の頻度については次の通りです。
・CYP2D6の単一遺伝子変異の解析結果によれば,日本人にはCYP2D6*1 (42.3%)、*2(9.2%),*5(6.1%),*10(40.8%)などが検出されており(文献2)、活性型の頻度はPMは*5/*5で1%未満、IMは*1/*10、*2/*10、*5/*10、*10/*10であり、日本人では50-60%程度、EMは*1/*1、*1/*2、*1/*5、*2/*2、*2/*5であり40%程度と報告されています。
・日本人のCYP2C19のPMと推定される遺伝子型は,3種類(*2/*2,*2/*3,および*3/*3)が確認され,これらの遺伝子型の頻度の合計は18.8%とPMの頻度(約20%)に近いことから、これらの遺伝子型がPMの大半を説明しうるとされています(文献3)。通常活性型(EM)は*1/*1で30-40% 中活性型(IM)は*1/*2ないし*1/*3で40-50%程度と報告されています。
CYP2C19およびCYP2D6の活性型と抗うつ薬および抗精神病薬曝露量の関係について
背景
・向精神薬の有効性は不十分であるが、新規薬剤の開発はなかなか早急にはのぞめないので、現在使用しうる薬剤について、その用量を最適化することが重要である
・薬物の代謝能力は個々人で異なるが、最近のメタ解析では、抗精神病薬や抗うつ薬の効果用量関係において、至適用量が存在することが指摘されており、効果を最大化するためには最適な用量を用いることが重要である。
・最近の5000名以上の患者からのデータの解析結果によると、エスシタロプラム10mg、セルトラリン100mg、リスペリドン4mg、アリピプラゾール20mgで治療した場合、1/3以上の患者において、治療至適血中濃度域を外れた血中濃度になっていることが報告されている。
・CYP2D6およびCYP2C19はその代謝活性に応じて低活性型:PM(Poor Metabolizer)、中活性型:IM(Intermediate Metabolizer)、通常活性型:NM(Normal metabolizers=Extensive Metabolizer)、超高活性型:UM(Ultra-Rapid Metabolizer)に分類されている
・PMとIMでは、血中濃度が上昇しやすく、副作用が起こりやすいといわれている。一方でPMとUMではより治療の失敗につながりやすく、1年以内での変薬につながりやすいことが指摘されている
・抗精神病薬や抗うつ薬の用量設定については、CYP多型による活性型の違いを考慮していない。PMでは治療上投与さるる用量がNMよりも低用量にすべきと考えられ、FDAや欧州医薬品局、DPWG(Dutch Pharmacogenetics Working Group)などではアリピプラゾールについてCYP2D6のPM群では用量を低く設定することを推奨している。
・しかし実際にどの程度用量を減量すればよいのかについては、十分なデータがない。そこで今回これまでの報告についてsystematic reviewとメタ解析を行った
方法と対象
・抗うつ薬と抗精神病薬(エスシタロプラム、セルトラリン、フルオキセチン、フルボキサミン、パロキセチン、ノルトリプチリン、ミアンセリン、ミルタザピン、クロザピン、クエチアピン、オランザピン、リスペリドン、アリピプラゾール、ハロペリドール)が投与された試験について、被検者のCYP2D6とCYP2C19の遺伝子型(1%以上の頻度を有するもの)が解析されており、NM、IM、PMに分類されていること。
・各活性型で3名以上の被検者が存在すること。薬物曝露量が、(a)用量により正規化された定常状態の血漿中濃度、(b)用量により正規化された時間-血漿中濃度曲線の面積、(c)薬物の総クリアランス量の逆数、のいずれかによって測定されているもの
・各薬剤について、PM群、IM群、もしくはPM群+IM群について、各群の平均薬物曝露量をNM群の平均薬物曝露量で割って平均比率(RoM)を抽出した。これによりPM群ないしIM群ないしPM群+IM群がNM群の何倍薬剤に曝露されたかの指標が得られる
結果
・94 studies(N=8379 )が解析対象となった
CYP2D6遺伝子多型と薬物曝露の関係
・CYP2D6遺伝子型による分類で、NM群との差が比較的大きかったものとして、アリピプラゾールはPM+IM群対NM群のRoMは1.48(CI 1.41-1.57)と有意差あり。ハロペリドールはPM群対NM群でRoMは1.68(CI 1.40-2.02)と有意差あり。リスペリドンはPM+IM群対NM群のRoMは1.36(CI 1.28-1.44)と有意差あり。パロキセチンはIM対NM群でRoMは3.50(CI 2.52-4.85)(ただしわずか3 studies、N=41と小規模の結果)と有意差あり。
・NM群との差がより小さかったものとしては、CYP2D6遺伝子型による分類で、ハロペリドールはIM群対NM群でRoMは1.14(CI 1.05-1.25)。ベンラファキシンはIM+PM群対NM群でRoM 1.19(CI 1.09-1.29)
・その他Nは少ないものの有意差がみられたものとして、クエチアピンではPM群対NM群でRoM 1.32(CI 1.10-1.58 N=198, 1 study)、ミルタザピンではIM群対NM群のRoM 1.39 (CI 1.23-1.57)、パロキセチンではPM群対NM群でRoM 5.13(CI 3.82-6.87 N=73, 2 studies)などとなった
CYP2C19遺伝子多型と薬物曝露の関係
・エスシタロプラムではPM群対NM群のRoM 2.63(CI 2.40-2.89)、セルトラリンではIM群対NM群のRoM 1.38(CI 1.27-1.51)、エスシタロプラムについては、IM群対NM群のRoMは統計的有意差なし
・その他studyが2以下で有意差がみられたものとして、クロザピンではPM群対NM群のRoM 1.92(CI 1.32-2.79 N=78, 2 studies)、セルトラリンではPM群対NM群のRoM 2.70(CI 2.15-3.39, N=577, 2 studies)、ベンラファキシンではIM群対NM群のRoM 1.19(CI 1.11-1.31、N=669, 1 study)、ベンラファキシンのPM群対NM群のRoM 2.13(CI 1.54-2.93 N=443, 1 study)
まとめ
・アリピプラゾールについてはCYP2D6遺伝子多型において日本人で約半数を占めるIM群においてNM群と比較して曝露量が約50%多くなる可能性がある。
・クロザピンについては、CYP2C19遺伝子多型において日本人で約20%存在するPM群においてNM群と比較して曝露量が2倍になる可能性がある
・ハロペリドールについては日本人はPM群が1%以下と少ないため、CYP2D6遺伝子多型による曝露量の違いはあまり気にしなくてもよさそう
・リスペリドンはCYP2D6遺伝子多型において日本人の約半数を占めるIM群において曝露量が30%程度多くなる可能性がある
・エスシタロプラムはCYP2C19遺伝子多型において、日本人で約20%存在するPM群においてNM群と比較して曝露量が約2.6倍になる可能性がある。日本人の約半数のIM群はNM群と比較して曝露量が40%近く多くなる可能性がある
・ミルタザピンについては、CYP2D6遺伝子多型において、日本人で約半数を占めるIM群において、NM群と比較して曝露量が1.5倍になる可能性がある
・パロキセチンについてはNが少ないものの、CYP2D6遺伝子多型において日本人の約半数を占めるIM群において曝露量が約3.5倍になる可能性がある
・セルトラリンについては、CYP2C19遺伝子多型において、日本人で約20%存在するPM群においてNM群と比較して曝露量が2.7倍になる可能性がある。約半数を占めるIM群においてはNM群と比較して曝露量が40%近く多くなる可能性がある
・ベンラファキシンについてはCYP2D6遺伝子多型の影響をあまり受けないようである(20%未満)
コメント
・パロキセチンとエスシタロプラムのCYP2C19のPM群(日本人の約20%)におけるRoMの大きさが気になるところです。エスシタロプラムは用量依存性にQT延長をきたしうるので、特に高齢者において要注意かもしれません。
文献1)Ota T. et al. Int J Med Sci. 2015 Jan 1;12(1):78-82. doi: 10.7150/ijms.10263. eCollection 2015.
文献2)立石智則 心電図 2006:26 :201-210
文献3)久保田隆廣ら 薬物動態 2001:16(2):69-73
文献4)Milosavljevic F. et al. JAMA Psychiatry. 2020 Nov 25. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.3643. Online ahead of print. -
リスク評価ツールは自殺リスクを予測しうるか
2020年11月24日
・結論から言えばNOですし、リスク評価ツールをそのように使用してはならないというのがNICEガイドラインなどの説くところですが、今回はちょうど12月号のlancet psychiatryにこれと関連した話題(文献2)も出たので、このあたりの話をまとめておきます。
・まずは文献1のリスク評価ツールの自殺関連事象(自殺企図+自殺既遂)の陽性的中率についてです
・文献1では自殺リスク評価ツールを第1世代から第3世代までに分類しています。第1世代は慣用的なBeck Hopelessness Scale(BHS)やBeck Depression Inventory (BDI)など。第2世代は髄液中の5-HIAAなどの生物学的指標。第3世代は統計学的に作成された指標(Manchester Self-Harm Rule (MSHR), Edinburgh Risk Rating Scale (ERRS)など)とのことです。
・この統計学的に作成された指標とはなんぞやということですが、文献3がわかりやすく、あらかじめ自傷行為で入院した患者を対象に、その後一定期間観察研究を行い、自傷行為再発のリスク因子を複数抽出し、因子毎にオッズ比に応じて重みづけしスコアリングするものです。例えば文献3のThe Repeated Episodes of Self-Harm (RESH) scoreでは、性別や年齢、手段、診断など多数の因子の中から、ロジスティック回帰分析により自傷行為再発に関して有意な因子として抽出された、これまでの自傷行為回数、エピソード間の間隔、最近12か月間の精神科診断、最近12月間の入院歴の4つの因子について、それぞれをオッズ比で重みづけをし、スコアリングするというシンプルなわかりやすい指標となっています。
リスク評価ツールの陽性的中率(文献1)
背景
・臨床家はどのような患者が自殺で死亡するのか、あるいは自傷行為を繰り返すのかを予測したいと考えている
・多くのリスク評価ツールがあり、例えばBeck Depression Inventory(BDI)やSADPERSONSスケールなどの心理学的尺度(第1世代)、デキサメタゾン抑制試験(DST)や髄液中5-ヒドロキシインドール酢酸(5-HIAA)濃度などの生物学的検査(第2世代)、ReACT自傷行為ルールやRESHスコアなどの統計モデルに基づいた尺度(第3世代)などが提唱されている。
・しかしこれらの尺度による予測精度は不正確であり、NICEガイドラインでは、将来の自殺や自傷行為を予測するためにリスク評価ツールを使用しないことを推奨しており、これらツールの使用を、リスク評価目的ではなく、患者にどのようなケアが適切かのニーズ評価目的として使用するように推奨している。
・リスク評価ツールの陽性的中率についてメタ解析を行ってみた
対象と方法
・縦断的コホート研究を解析対象とした。
・自殺のリスク評価について心理学的尺度ないし生物学的尺度ないし第3世代尺度を用いるもので、ハイリスク患者を同定し、追跡期間中の自殺関連事象(自傷行為や自殺既遂)をアウトカムとして評価しているもの
・70 studies(52が心理学的尺度、17が生物学的尺度、1つが両方)。成人が43 studies、思春期のみが4 studies、両方が9 studies。
・多くが最近の自傷行為ないし希死念慮を有する患者を対象(37 studies)としたもの、精神疾患患者を対象としたものが 29 studies、その他が4 studies。精神疾患を対象としたもののうちわけは気分障害が12 studies、初発精神病ないし統合失調症が3 studies、PTSDが1 study、退役軍人が2 studies、囚人が2 studies。
・追跡期間は6か月以下(18 studies)、10年以上が5 studies、1年が最頻で 19 studies
結果
・心理学的尺度については全体のpooled positive predictive value(PPV:陽性的中率)は自傷行為+自殺で38.9%、自傷行為のみが27.5%、自殺が3.7%
・生物学的尺度については、自傷行為のみのPPVが14.7%、自殺のPPVが14.5%
・第3世代尺度については自傷行為ないし自殺のPPVが38.7%
・自殺に関して最も良好なPPVは髄液中 5-HIAAであり、PPVが21.1%であった
・個別の心理尺度で自傷行為または自傷行為+自殺のPPVが最も高かったのはBeck Hopelessness ScaleとBuglass and Horton Scaleで,29.1%,28.8%と同程度であった。第三世代尺度の中で自殺+自傷行為のPPVが最も高かったのはエジンバラリスク評価尺度(Edinburgh Risk Rating Scale)であり,27.6%であった
・陽性尤度比は感度/(1-特異度)で表され、1に近い数値の場合、その検査は臨床的に意義がなく、10以上だと臨床的に有用とされている。
・自傷行為で受診した患者の12か月間の自傷行為再発率として16.3%を採用し、これを検査前確率とすると、 Beck Hopelessness ScaleとBuglass and Horton Scaleの陽性尤度比は2.1、第3世代尺度についての陽性尤度比は3.3程度となり、心理学的尺度の陽性尤度比は2から3程度であり、検査としての臨床的有用性は乏しいと言える
コメント
・自殺に関して髄液中5-HIAAの陽性的中率が21.1%というのはかなり高いように思えますが、引用文献をみると1980年くらいから2000年くらいまでの古い研究が大半で最近の報告がないのが気になるところです。
イギリスでの自殺リスク評価(文献2)
背景
・イギリスでの自殺者数は毎年約6000人でありここ10年間増加傾向にある
・自殺者の4人に1人以上が最近の精神保健サービスへの接触歴があることが報告されている
・リスク管理が重要であり様々なリスク評価のツールが使用されている。しかし自殺リスク評価ツールの自殺予測に関する有用性のエビデンスは限られている
・リスク評価ツールの予測能力には大きな差があり、臨床での使用が推奨されるほど診断精度で十分な結果が得られているものはない
・イギリス、オーストラリア、ニュージーランドのガイドラインでは、評価ツールを自殺関連リスクを評価するために使用することや、治療決定するために使用することを推奨していない。その代わり、個々のニーズとリスクの包括的な心理社会的評価を行い、治療計画を伝えるべきとされる。
一方でアメリカなど一部の国では、リスクの層別化と評価手法の普及を提唱している。・リスク評価ツールの使用についての大規模研究は少なく、現場レベルでの評価ツール使用についての経験的知識に関する研究も限られている
・今回、イギリスにおいて精神保健サービスの現場でどのリスク評価ツールが使用されているか、またそれらがどのように評価され、改善される可能性があるかについて調べた
対象と方法
・リスク評価ツールについてのレビュー、オンライン調査、臨床家へのインタビューを行った
・使用しているリスク評価ツールについては、イギリス85カ所の国民保健サービス(NHS)拠点に対して調査を行った。
・オンライン調査では、臨床家やサービスの利用者(患者)、支援者らが対象となり、臨床家に対しては評価ツールをどのように見て、どのように使用しているか、評価ツールを使用するためにどのようなトレーニングを受けているかなどを尋ねた。患者や支援者に対しては評価の経験やツールへの認識などを尋ね、全員に対してリスク評価ツールの改善点についての意見を求めた
・臨床家への電話インタビューについては、精神保健サービスを受診してから12ヵ月以内に自殺で死亡した人が登録されているNCISHデータベースを使用し、2015年1月1日から2015年12月31日までの間に自殺で死亡した患者の診療を担当したことがあり、最後の接触時(自殺の3か月以内)に低リスクと判断された患者の臨床家20~30名が対象となった
NHSに対する調査の結果
・リスク評価ツールに関して、調査対象となった85カ所の国民保健サービス(NHS)拠点全てから回答がえられ、156のリスク評価ツールが回答された。その中で主に使用されているツールが特定された
・評価ツールの3分の1以上は各地域で考案されたものであった。20%はelectronic patient recordを活用したRio risk screenを用いていた
北アイルランドではすべてのNHSで2段階プロセスを採用しており、最初にすべての患者を対象とした標準化されたリスクスクリーニングツールを使用し、その後に包括的な臨床リスク評価および管理ツールを使用していた。・85個中72個(85%)はチェックリスト形式であり、全てのツールにおいて特定されたリスクをより詳細に説明できるようにテキストボックスで記録するオプションが含まれていた。
・ほとんどのツール(94%)では、患者の将来の行動を予測し、リスクを高、中、低などのように層別化するよう構成されていた。
・患者を積極的にケアに参加させることについては59%のツールにおいて推奨しており、評価されたリスクについて患者の確認を得ることから、患者との協働作業についての詳細まで様々な程度で記載されていた。
・62%のツールでは臨床家が、患者、支援者双方からの意見を聴取することを推奨し、協働作業の詳細について解説していた
オンライン調査の結果
・オンライン調査は358人が対象となり。うちわけは患者42名、支援者26名、臨床スタッフ290名(看護師109名、医師または精神科医34名、管理者48名、心理士22名、作業療法士7名、ソーシャルワーカー8名、その他医療従事者62名)であった
・患者42名中15名はデータ不足のため分析から除外。残りの27名中20名(74%)は、アセスメントの際に支援者や家族が同席する機会を与えられなかったと報告した。9名(33%)は危機時の連絡先に関する情報を提供されていなかった。12名(44%)はアセスメントのプロセスに批判的であった
・批判的な意見では、評価の非人間的な性質が強調されており、自分の感情や意見が無視されているとの意見が述べられていた。ある患者は「調査フォームは政府の調査のように感じる」と述べ、別の患者は「自殺についての質問は評価ではすぐに流されてしまう」と自殺についてのアプローチを批判した。「自殺について真正面から取り組み、もっと詳しく質問する必要があると思う。一度の質問だけでは十分ではない」との意見もあった。
・6人(22%)の患者は、リスクを評価する際のスタッフのアプローチに一貫性がないと感じていた。「決められた手順がなく、その場しのぎのものであり、受診する職員に依存する。スタッフのためのトレーニングをもっと充実させる必要がある」との意見もあった
・26人の支援者の回答のうち20人が分析対象となった。9人(45%)が、安全性について話し合われた際に患者との評価に出席したと報告し、同じく45%が、ミーティング中に自分の意見が認められたと感じていた。
・しかし際立った課題として、支援者が患者の支援計画や安全計画に参加することが不足していることへの不満と失望であり、それは家族では手に負えないとケアチームに解釈されているとの感覚につながっていた。
・ある支援者は、「コミュニケーションは私からケアチームへの一方通行であり、自宅で深刻化する状況をどのように管理すべきかについての議論または情報がなかった」と述べた。
・潜在的なリスクについて意見を述べる機会がないことへの懸念も指摘されている。「安全計画には支援者の意見はほとんど含まれていないのに、自殺願望のある子どもの世話を24時間365日していた。ケアや危機管理計画についてほとんど知らされておらず、うまくいかなかったときにはそれに従うことを期待されていただけで、実際に考えたり、考慮したりすることなく、全体が『チェックボックス』のように見えた」との意見もあっ
・臨床スタッフへの調査結果として、臨床医は、ツールの要約結果について、他の医療チームに問題点を伝えるのに有用なものと回答した。また、評価ツールの使用は、患者との信頼関係を築き、率直な会話を促進し、現在および過去のリスク要因を探ることができる貴重な機会であると捉えていた。
・「リスク評価ツールはリスクとレジリエンス要因について考えるための良い枠組みを提供するが、臨床経験に取って代わるものではない。患者に関する情報は臨床病歴に基づいており、広範な環境要因は含まれていない傾向がある」との意見がみられた
・定期的なトレーニングの重要性を指摘する意見もあった
・課題として評価ツールが長く煩雑な場合、重要な患者の詳細を見落としてしまう可能性があるという懸念が表明された。またツールが長すぎると、関連性の低い分野については記入するのを躊躇してしまうとの意見もあった
・またリスク評価ツールは、それを実行する個人の介入能力を上回るものではなく、誤った安心感を持たないようにということを指摘する意見もあった
電話インタビューの結果
・電話インタビューでは、22名の臨床スタッフが対象となり、精神科医(13名)のほか、看護師、ソーシャルワーカー、心理士(9名)が参加した
・インタビューした臨床スタッフは全員、ツールを予測手段としてではなく、リスクに関しての判断を分類するためのガイドとして使用していると感じていた。
・ある臨床医は、「あなたの仕事は誰が死ぬかを予測することではなく、患者が提示した問題に有益な方法で関与することである」とコメントしている。
・臨床医はツール自体を意思決定の判断役とするのではなく、臨床判断に基づいて治療計画を通知し、策定するためにツールを使用していた。
・リスクサマリや系統的記載は、入院患者と地域ケアの間の移行を容易にするなど、ケアチームに良いコミュニケーション源を提供するものと捉えられていた。
・徹底的な病歴を収集し、その情報を一つの文書にまとめることは、患者との率直な議論を促進するために有用であると考えられた。
・一方で治療関係にはオープンな会話が必要であり、チェックリストが流動的な会話を奪ってしまうため、オープンな会話が妨げられている可能性があるという問題も示された。
リスク評価ツールの改善点についての意見
(1)臨床スタッフ
・スコアリングシステムやレーティングシステムを削除すること
・一貫性の向上と簡潔化
・全ての専門用語を解説し、患者や支援者にとって評価ツールを使いやすいようにすること
・継続的なトレーニングとスーパービジョンを通じてスタッフの自信を高めること
(2)患者
・チェックリストに頼らない個別化されたアプローチをすること
・希死念慮に焦点をあてること。スタッフが自信をもって難しい質問を扱えるよう促すこと
・クライシスプランや安全計画の共有を含め、家族や支援者を巻き込むこと
・地域の支援選択肢やヘルプライン、24時間対応のサービスに関する情報提供
(3)支援者
・危機的状況に陥る前、または危機的状況に陥った時に、家庭での状況管理の方法や、何を想定すべきかについての情報や助言を得ることができること
・患者を支援するための技術と知識を獲得するための訓練が提供されること
・支援者が孤立感を感じないようにすること
・患者の同意がある場合には、家族とのより一貫性のある相談体制と情報共有。リスクの高い行動について家族や支援者と話し合うこと
まとめ(文献4より引用)
(1)リスク評価ツールは、将来の自殺行動を予測する方法と見なすべきではない。これはNICEの自傷行為ガイドラインと一致している。(2)ツールを使用する場合は、シンプルでアクセスしやすく、より広範な評価プロセスの一部として考慮されるべきである。治療方針は点数によって決定されるべきではない。
(3) リスクツールは自殺の予防にはほとんど役に立たないというコンセンサスが広まっている。本研究は、臨床的判断を重視し、関係性を構築し、現在の状況、既往歴、社会的要因に関する情報を収集し、共同で開発した管理計画を充実させることにより、臨床的なリスク評価プロセスを改善する方法を提案するものである
(4)リスク評価のプロセスは精神保健サービス全体で一貫している必要があり、スタッフはリスクの評価、策定、管理の方法について訓練を受けるべきである。
(5) 家族や支援者は、潜在的なリスクについて意見を述べる機会を含め、アセスメントのプロセスに可能な限り多くの 関与を持つべきである。管理計画は、可能であれば共同で作成されるべきである。
(6) リスクの管理は個人的で個別化されたものでなければならないが、同時にシステム全体のアプローチとしてすべての人に対する標準的ケアの質を高めるものであるべきである。監督、委任、紹介経路がすべて安全に管理されていることが保障されるべきである
コメント
・今回の報告の結果を踏まえて日本精神科救急学会のガイドライン(https://www.jaep.jp/gl_2015.html)をみると、家族などへの支援やケアの項目などもきちんと整理されており、素晴らしい内容であることがわかります。
・課題は実践的なトレーニングの充実ということになるでしょうか
引用文献
文献1:Carter G, Milner A, McGill K, Pirkis J, Kapur N, Spittal MJ. Br J Psychiatry. 2017 Jun;210(6):387-395. doi: 10.1192/bjp.bp.116.182717. Epub 2017 Mar 16.
文献2:Lancet Psychiatry. 2020 Dec;7(12):1046-1053. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30381-3. Epub 2020 Nov 12.
文献3:J Affect Disord. 2014 Jun;161:36-42. doi: 10.1016/j.jad.2014.02.032. Epub 2014 Mar 12.
文献4:The assessment of clinical risk in mental health services. National Confidential Inquiry into Suicide and Safety in Mental Health (NCISH). Manchester: University of Manchester, 2018. -
残念なニュース
・非常に期待され、個人的にも期待していたBrainStorm社の自家間葉系幹細胞移植であるNurOwn細胞の第3相試験ですが、同社の11月17日付press releaseにより主要評価項目を達成できなかったことが公表されました。
・189名のALS患者を対象に行われたこの第3相試験の主要評価項目はALSFRS-Rの変化率が治療開始後に治療開始前と比較して1.25点/月以上の改善度を示した反応群の割合でした。
・NurOwn投与群では34.7%、プラセボ群では27.7%で統計的有意差はみられませんでした。
・副次評価項目の28週間でのALSFRS-Rの変化量はNurOwn群 -5.52点、プラセボ群 -5.88点でこれも有意差なしでした。
・その他サブグループではどうなるかということも掲載されていましたが、事前に計画されていた層別化であればいいのですが、結果がでてから都合の良いようにサブグループを選んで、検定を行うことは禁忌ですので、触れないようにしておきます。
・髄液中の神経栄養因子などのマーカーの有意な上昇と神経炎症に関わるマーカーの有意な低下は観察された(プラセボ群では観察されなかった)とのことです
・再生医療関連のALS臨床試験としては、まだ第2相以前ですが同種幹細胞由来アストロサイトの移植(AstroRx)、Mayoクリニックなどで行われている自家脂肪組織由来間葉系幹細胞移植などが進行中です。NurOwn細胞は幹細胞移植のトップランナーだっただけに、残念度が大きいです。
・孤発性ALSに関しては、Ionis社のION541(ataxin-2 mRNAに対するアンチセンス・オリゴヌクレオチド製剤)の臨床試験など期待できる材料もありますので、今後の進展を待ちたいところです
引用元
https://ir.brainstorm-cell.com/2020-11-17-BrainStorm-Announces-Topline-Results-from-NurOwn-R-Phase-3-ALS-Study -
ルマテペロン
2020年11月14日
・2019年12月にアメリカで統合失調症治療薬として承認されたルマテペロンの薬理作用と臨床試験の報告をまとめてみます。
・基礎実験の報告だけみるとなんだかすごい薬のように思えますが、実際はどうなのでしょうか?
・特記すべきこととしては、PETで線条体D2受容体占有率が約40%とされているlumateperone tosylate 60mg(ルマテペロンとして42mg)の投与量において、臨床的有効性が報告されていることです。そのためEPSリスクが低いことが期待されます。
・またルラシドンと同様にヒスタミンH1受容体阻害作用およびセロトニン2C受容体阻害作用がほとんどなく、体重増加や過鎮静が起こりにくいことが期待できることもあります。
・薬理学的特徴としては、基礎実験の結果からは、シナプス前ドパミンD2受容体には部分アゴニスト作用を有すること、D1受容体への作用が比較的高いこと、セロトニントランスポーター阻害作用を有していることなどです。
・シナプス前ドパミンD2受容体に対しては部分アゴニスト作用を有するため、多くの抗精神病薬がシナプス前ドパミンD2受容体を阻害し、ドパミン合成なども阻害し、黒質線条体経路における錐体外路症状発現リスクをさらに増加させるのと異なり、ルマテペロンは黒質線条体ドパミン神経におけるドパミン代謝を変化させず、そのため錐体外路症状が起こりにくいことが期待されること。さらにはD1受容体への作用を介して、側坐核のグルタミン酸神経系の神経伝達を高めることが期待でき、統合失調症のグルタミン酸仮説で言われているNMDA受容体の機能低下を補い、治療的に作用しうることが期待できることなどが言われています。
・果たしてそのような結果が臨床試験で見られたのでしょうか?まずは基礎実験からの報告(文献1)を要約してみます。
薬理学的特徴
・Tmax 3~4時間
・主にCYP3A4で代謝
・半減期は13時間で、ルマテペロンと同等の活性を有する活性代謝物の半減期は約20時間。1日1回投与でOK
・セロトニン2A受容体への親和性が強い(Ki=0.54nM。D2受容体(Ki=32nM)、D1受容体(Ki=52nM)への親和性もあり。セロトニントランスポーターへの親和性もドパミン受容体と同等程度に有する
・抗ヒスタミン作用は極めて弱く、セロトニン2C受容体への親和性も低い(Ki=173nM)。体重増加の副作用がほとんどないことが期待される。この点はルラシドンにも似ている
・シナプス前D2自己受容体(刺激によりドパミン合成が促進)に対しては、多くの抗精神病薬と異なり部分アゴニストとして作用し(シナプス前D2受容体活性のマーカーである線条体でのチロシンヒドロキシラーゼのリン酸化などの指標を変化させないことから)、シナプス後D2受容体にはアンタゴニストとして作用(in vitroで用量依存性にGSK3βのリン酸化を増加させる)
・低用量では選択的なセロトニン2A遮断薬として機能し、高用量でドパミン系やセロトニントランスポーターへの作用が顕在化する
・中脳辺縁系および中脳皮質経路に対して選択的な作用を発揮する。齧歯類での実験では、内側前頭皮質でのドパミン放出を増加させ、D1受容体との間接的な相互作用を介して、側坐核におけるNMDA受容体のリン酸化を引き起こし、グルタミン酸系の神経伝達を高めることが期待される(統合失調症のグルタミン酸仮説ではNMDA受容体の機能低下が想定されており、この点でグルタミン酸系の神経伝達を高めうることは治療的に作用する可能性がある)。またドーパミンD2受容体を含む前頭前野および側坐核神経細胞のシグナル伝達物質であるGSK3のリン酸化を増加させることが確認されている。
・一方で線条体におけるドーパミン放出やNR2BとGSK3のリン酸化、線条体におけるドーパミン代謝やチロシン水酸化酵素活性などは増加させず、運動機能障害(齧歯類におけるカタレプシー)についても増加させないことが報告されている
・抗精神病薬は陽性症状への有効性が期待できるが、線条体D2占有率が80%以上に達した場合には錐体外路症状が生じうるとされる。しかしルマテペロンは上記のような経路選択性により、運動機能障害を引き起こすことなく、精神病や幅広い症状に対して効果的な作用を発揮する可能性がある。(コメント:シナプス前ドパミン自己受容体への部分アゴニスト性からこのような選択性が生じうるとされる)
・ルマテペロンは強力なセロトニン2A受容体拮抗作用と、ドパミン受容体下流のリン酸化蛋白質経路の調節作用を有している。ドーパミン受容体リン酸化蛋白質調節剤(DPPM)として、ルマテペロンは中脳辺縁系/中脳皮質経路選択性を有し、シナプス後D2受容体アンタゴニストとシナプス前D2部分アゴニストの2つの特性を併せ持っている。
・また、D1受容体の細胞内シグナル伝達の下流に位置する、中脳辺縁系のグルタミン酸作動性NMDA受容体のリン酸化を促進し、グルタミン酸経路の神経伝達を促進することが期待される。
・そのため理論的には、運動機能障害を呈することなく統合失調症に伴う陽性症状、陰性症状、認知症状に対する有効性が期待される。また、抗精神病薬の中では珍しく、セロトニン再取り込み阻害作用を有しており、抗うつ作用を発揮することも期待されている
PET試験より
・線条体D2受容体占有率は、 lumateperone tosylate 40mg投与時には39%。 lumateperone tosylate 10mgの低用量では、皮質のセロトニン2A受容体占有率がほぼ飽和し(前頭前野では平均88%)、線条体D2受容体占有率は平均12%であった。
・高用量( lumateperone tosylate 40mg)では、線条体のセロトニントランスポーター占有率が31%。40mgまで増量すると、完全に飽和したセロトニン2A受容体系の上にドーパミン受容体とセロトニントランスポーターを含む占有率が増大するが、シナプス後ドパミンD2受容体の占有率は中等度であった
・統合失調症患者に対して有効用量である60mgのlumateperone tosylateを1日1回経口投与して2週間後の線条体D2受容体占有率は平均40%であり、他の抗精神病薬が有効性を達成するために必要とする線条体D2受容体占有率の範囲よりも低かった。
ルマテペロンの第3相試験(文献3)
対象と方法
・対象:18-60歳の統合失調症患者(DSM-5)、BPRS40点以上(陽性症状尺度2つ以上で4点以上)の精神病症状急性増悪患者。最近4週間以内で急性増悪したもの、CGI-Sで4点以上、PANSS totalで70点以上、これまでに抗精神病薬治療への治療反応歴があること
・プラセボ対照無作為割付比較試験
・試験期間:4週間
・lumateperone tosylate 60mg(ルマテペロン42mg相当) N=150
・lumateperone tosylate 40mg(ルマテペロン28mg相当)N=150
・プラセボ N=150・主要評価項目はPANSS totalスコアの平均変化量
・副次評価項目はCGI-S、PANSS positive,negative,general、Calgary Depression Scale for Schizophrenia(CDSS)など
結果・完遂率は42mg群 85.3%、28mg群80%、プラセボ群 74%
・42mg群はPANSS totalにおいて4週後にプラセボ群より有意に改善(プラセボ群とのLeast-squares mean differenceは-4.2点 )。28mg群は有意差なし
・PANSS totalで30%以上の改善を反応とすると42mg群 36.5%、28mg群 36.3%、プラセボ群 25.5%
・PANSS postiveは42mg群、28mg群ともにプラセボ群より有意に改善
・PANSS negativeは有意差なし
・PANSS generalは42mg群で有意差あり
・CDSSは有意差なし
・有害事象については42mg群の64.7%、28mg群の56.7%、プラセボ群の50.3%に出現
・プラセボ群の2倍以上もしくは5%以上でみられた副作用は、傾眠(42mg群 17.3%、28mg群 11.3%)、鎮静(42mg群 12.7%、28mg群 9.3%)、疲労感(42mg群 5.3%、28mg群 4.7%)、便秘(42mg群 6.7%、28mg群 4.0%)
・錐体外路症状はいずれの群も5%未満
・体重増加は42mg群 0.9kg、28mg群 0.6kg,プラセボ群 0.7kgで有意差なし
コメント
・やはりこの第3相試験でもプラセボ群がベースラインから10点くらい改善しています。ここ最近の臨床試験ではだいたいその傾向(ブレクスピプラゾール、ブロナンセリンパッチ、ルラシドンなど)があり、unblinding biasがないためかもしれません(安全性が高い薬剤の場合、評価者に副作用によりプラセボとの違いがなんとなくわかってしまうこととがないため、そうでないために生じるunbliding biasが混入しない:文献3)
・抗H1作用がほとんどないのに傾眠が有意に多かったのは何故でしょうか。どのような説明ができるのかわかりません。
・またセロトニントランスポーター阻害作用を有するもののCDSSは有意差がありませんでした。いろいろな作用部位がある薬剤において理屈では期待される作用がみられない(例えばボルチオキセチンの抗不安作用が期待されるほどないなど)のはよくあることで、そう簡単にはいかないということなのだと思います。
・体重増加は期待通り有意なものはありませんでした。また確かに錐体外路症状は少なく、安全性はかなり期待ができそうです。その点文献1にもありますが、高齢者やBPSDに対する処方としても適応となりうるかもしれません。
引用文献
文献1:Davis RE, Correll CU. ITI-007 in the treatment of schizophrenia: from novel pharmacology to clinical
outcomes. Expert Rev Neurother. 2016;16(6):601-614.doi:10.1080/14737175.2016.1174577
文献2:Correll CU, et al. JAMA Psychiatry. 2020. PMID: 31913424
文献3:Holper L, Hengartner MP.BMC Psychiatry. 2020 Sep 7;20(1):437. doi: 10.1186/s12888-020-02839-y. -
抗精神病薬とうつ症状
2020年11月07日
・福島県立医大の三浦先生らが抗精神病薬とうつ症状の改善について興味深い報告をされました(文献1)。その内容の概略と感想を書きます。
・この報告の素晴らしいところは、メタ回帰分析を行い、うつ症状の改善度とその他の症状の改善度との相関を調べているところです。最後にコメントしますが、その結果から面白い考察も可能かと思います。
・これまでにも統合失調症の急性期試験を解析対象として、抗精神病薬とうつ症状の改善度についての報告はいくつかされています。有名なものとしては、文献2のネットワークメタ解析の結果(Fig.2D)がありますし、文献3の2009年のLancet誌の報告も第1世代と第2世代の比較という点で注目されました。またCATIE試験の事後解析としてうつ症状の効果についての報告(文献4)もありますし、うつ症状が主体の統合失調症患者に対するオランザピンとジプラシドンの直接比較試験(文献5)、アミスルプリドとオランザピンの直接比較試験(文献6)、急性期におけるうつ症状に対するリスペリドン、ハロペリドールに対するアミスルプリドの優位性を報告したpooled analysisの結果(文献7)などもあります。
・今回は統合失調症急性期患者を対象としたプラセボ対照試験を解析対象とし、抗精神病薬のうつ症状への効果について、その他の症状の改善度との相関なども含めて解析されたものです。
統合失調症治療における抗精神病薬の抗うつ作用
方法と対象
・統合失調症と関連疾患についてプラセボ対照無作為割付比較試験を抽出。非公表も含む。
・クロザピンは除外(わずか1つの小規模(N=16)試験しかないため)、筋注製剤、LAIも除外
・主要評価項目はMADRSないしHAM-DないしCDSSにより評価されたうつ症状尺度の平均変化量。もしこれら尺度が使用できなければPANSSのAnxiety/Depression項目ないしBPRSのDepressionクラスターを効果量評価のため使用
・副次評価項目は症状重症度、CGI-S、QOL、あらゆる理由による中断率、忍容性欠如による中断率、有効性欠如による中断率など
・メタ回帰分析により交絡因子を同定。抗精神病薬が第1世代か第2世代か、neuroscience-based nomenclature(向精神薬の国際分類法による命名:M1:D2遮断薬(ハロペリドールなど)、M2:D2およびセロトニン2受容体遮断薬(クロルプロマジン、ルラシドン、オランザピン、ジプラシドン、ゾテピンなど)、M3:D2およびセロトニン1A部分アゴニスト(アリピプラゾール、ブレクスピプラゾールなど)、M4:D2、セロトニン2、ノルエピネフリン、α2アンタゴニスト(アセナピン、パリペリドン、リスペリドン)、M5:D2およびセロトニン2アンタゴニストおよびNET再取り込み阻害(クエチアピン))、出版年(1999年以前か、2000年から2009年までか、2010年以降か)、国、サンプルサイズ(400より多いか少ないか)、平均年齢(30-35歳、35-40歳、40-45歳、45-50歳)、含まれた疾患(統合失調症+統合失調感情障害か統合失調症のみか)、評価尺度(HAM-DかMADRSか、CDSSかPANSSかBPRSか)などについてうつ症状改善度との相関の有無を調べた。
結果と議論
・35RCTs(N=13890)
・平均年齢39.2歳、平均介入期間5.7週間(3-7週)
・ルラシドン 7RCTs、オランザピン 7 RCTs、パリペリドン 6 RCTs、クエチアピン 5 RCTS、ブレクスピプラゾール 4 RCTs、ハロペリドール 4 RCTs、リスペリドン 4RCTs,アセナピン 3 RCTs、アリピプラゾール 2 RCTs、ジプラシドン 2 RCTs、カリプラジン 1 RCT、クロルプロマジン 1 RCT
・クロルプロマジン、ハロペリドール、ジプラシドンを除いて、抗精神病薬はプラセボより有意なうつ症状改善効果を有していた
・うつ症状改善のSMDの平均値は、アリピプラゾール -0.40、パリペリドン -0.39、カリプラジン -0.36、クエチアピン -0.32、オランザピン -0.31、アセナピン -0.30、リスペリドン -0.24、ルラシドン -0.21、ブレクスピプラゾール -0.19など。ジプラシドン、ハロペリドール、クロルプロマジンは有意差なし。
・メタ回帰分析の結果、HAM-DないしMADRSないしCDSSで評価されたうつ症状の改善度は、PANSSないしBPRS totalスコアの改善度、陽性症状、陰性症状、CGI-Sの改善度と有意な相関関係を有した。陰性症状の改善度との相関係数が最も大きかった。しかしPANSS総合精神病理評価尺度の改善度とは有意な相関を示さなかった
・うつ症状の改善度と参加者の平均年齢、性別比とは有意な相関はみられなかった
・出版年度が1999年以前では抗精神病薬のうつ症状改善効果はプラセボと比較して有意差がなかった。2000年以降では有意となった。
・第2世代抗精神病薬、M2-M5群であることは有意なうつ症状改善と関連した。第1世代、M1群はプラセボと有意差がなかった
・錐体外路症状がうつ症状と関連する可能性は注意が必要であり、その点においてCDSSはうつ症状と陰性症状、錐体外路症状の分離に最も優れていると言われており、CDSSを用いることが望ましそう
・急性期に対する介入では、第2世代抗精神病薬によりうつ症状は有意に改善すると言えそう。ただし効果量は0.19~0.4とsmallからmedium。このうつ症状の改善は陰性症状の改善、陽性症状の改善+使用する抗精神病薬のクラス(第2世代)により部分的に説明できるかもしれない。
・初発ではなく、罹病期間がある程度長い患者のため、前治療薬などの影響などもある可能性があり、その点が除外できない。初発精神病で検証できるとよい
コメント
・ハロペリドールは陽性症状の改善は有意でしたが、うつ症状の改善は有意なものではありませんでした。ハロペリドールは陰性症状の改善が有意ではなかったことと関連があるかもしれません。しかしジプラシドンについては陰性症状の改善が有意であったにも関わらずうつ症状の改善は有意ではありませんでした。M2に属するオランザピンやルラシドンは有意なうつ症状改善効果を示していることから、サンプル数が少ないためか、なんらかのその他の要因が関与しているためと思われます。・陰性症状の評価尺度がPANSS negativeであれば純粋に陰性症状を抽出できていない可能性があり(抽象的思考の困難、常同的思考については陽性症状とも関連した尺度であるため)、評価尺度としてはSANSやPANSS FSNSなどが望ましいといわれています。
・うつ病でみられるような、ベースラインの重症度が高いほど、プラセボに対する薬剤の優位性が高くなるとの関連性は、統合失調症のうつ症状についてはみられませんでした。この結果が一番興味深いものでした。
・ベースラインのPANSS 不安/抑うつ尺度が高いほど、有意に抗精神病薬のうつ症状に対する治療効果は小さくなる傾向があり、ここを覆しうる抗精神病薬が登場すれば興味深いものです。クロザピンだとどういうデータがでるのかは知りたいところです。自殺リスクを減少させると言われているため、もしかしたらクロザピンについてはベースラインのうつ症状が高いほど、うつ症状に対する治療効果が高いという結果になるかもしれません。
・patient level dataを用い、薬剤毎に解析を行うと、ベースラインのうつ症状の重症度が高いほど、うつ症状の改善効果が高い薬剤がみつかるかもしれません。そのような薬剤があれば真に統合失調症のうつ症状に有効な薬剤と言えるのかもしれません。
・細かいことを言えば、統合失調症のうつ症状には、awakeningによるものや、post-psychotic depression、陽性症状に伴う二次的なものなど様々な亜型がありうるため、一括りに議論しにくいものかもしれません。
引用文献
文献1:Miura I, Nosaka T, Yabe H, Hagi K. Antidepressive Effect of Antipsychotics in the Treatment of Schizophrenia: Meta-Regression Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. Int J Neuropsychopharmacol. 2020 Nov 5:pyaa082. doi: 10.1093/ijnp/pyaa082. Online ahead of print. PMID: 33151310
文献2:Huhn M. et al, Lancet. 2019 Sep 14;394(10202):939-951. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31135-3. Epub 2019 Jul 11.
Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis
文献3:Second-generation versus fi rst-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis Stefan Leucht, Caroline Corves, Dieter Arbter, Rolf R Engel, Chunbo Li, John M Davis lancet Vol 373 January 3, 2009
文献4:J Clin Psychiatry. 2011 Jan;72(1):75-80. doi: 10.4088/JCP.09m05258gre. Epub 2010 Sep 21. Impact of second-generation antipsychotics and perphenazine on depressive symptoms in a randomized trial of treatment for chronic schizophrenia. Addington DE, Mohamed S, Rosenheck RA, Davis SM, Stroup TS, McEvoy JP, Swartz MS, Lieberman JA.
文献5:J Clin Psychopharmacol. 2006 Apr;26(2):157-62. A 24-week randomized study of olanzapine versus ziprasidone in the treatment of schizophrenia or schizoaffective disorder in patients with prominent depressive symptoms. Kinon BJ, Lipkovich I, Edwards SB, Adams DH, Ascher-Svanum H, Siris SG.
文献6:Eur Psychiatry. 2006 Dec;21(8):523-30. Epub 2006 Nov 20. A double-blind randomised comparative trial of amisulpride versus olanzapine for 2 months in the treatment of subjects with schizophrenia and comorbid depression. Vanelle JM, Douki S.
文献7: Eur Neuropsychopharmacol. 2002 Aug;12(4):305-10. Amisulpride improves depressive symptoms in acute exacerbations of schizophrenia: comparison with haloperidol and risperidone. Peuskens J, Moller HJ, Puech A.