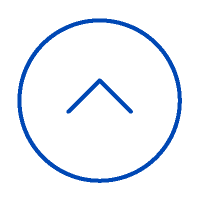-
ここ最近の勉強会のこと
2022年06月12日
・ここ最近の振り返りという事でまとめておきます。院内勉強会で扱ったものについてはまた後日まとめたいと思います。専攻医勉強会では統合失調症の急性期治療に関連した内容に入り、いくつかの論文をまとめたスライドで話を進めています。急性期治療に関するスライドに含めた論文は、以下のようなものになります。
1.Huber et al. Schizophrenia Bulletin, Volume 6, Issue 4, 1980, Pages 592–605
・まだ統合失調症の診断にSchneiderとBleulerの基準も用いられていた1950年代からの調査も含めて長期臨床経過を分類した論文。最近でも引用されることがあるようです。2.井上 新平ら「統合失調症の臨床疫学」:臨床精神医学 34(7):855-861.2005
・いわずとしれたDOSMed試験などの長期経過のまとめられた論文3.Maren Carbon, Christoph U. Correll Dialogues Clin Neurosci. 2014 Dec; 16(4): 505–524
・これも専門医試験に出題されうる経過の図(各病相間の移行割合など)が入っているのでとりあげました。4.BAPガイドライン J Psychopharmacol. 2020 Jan;34(1):3-78. doi: 10.1177/0269881119889296. Epub 2019 Dec 12.
・CHR、初発精神病などにわけて詳しくエビデンスが解説してあるのがいいです5.M. Huhn et al. Lancet. 2019 Sep 14;394(10202):939-951. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31135-3. Epub 2019 Jul 11
・有効性に関する解析については、文献25の論文にもあるように、プラセボ反応率が年代によって変化しているので、appendixのプラセボ反応率で調整したネットワークメタ回帰分析の図の方がよりバイアスが少ないと思われること。一方で副作用については客観性が高い指標も多いため、副作用については有用と思われることから多く引用しました。6.Harringan et al. J Clin Psychopharmacol. 2004 Feb;24(1):62-9. doi: 10.1097/01.jcp.0000104913.75206.62.
・QT延長について調べた論文。ベースラインにQT延長がなく、通常使用する用量の範囲内では、その薬剤の代謝に関わるCYP阻害作用のある薬剤と併用していてもそこまで心配しなくてもよさそうというもの7.EUFEST study : Lancet. 2008 Mar 29;371(9618):1085-97
・オープンラベル試験ですが、各薬剤の継続率に差があることと、継続できさえすれば有効性指標についての経時変化はほぼ変わらないことなどが示されています。8.PAFIP study:Int J Neuropsychopharmacol. 2020 Apr 23;23(4):217-229. doi: 10.1093/ijnp/pyaa004.
・これもオープンラベルですが継続率の違いや、初回エピソードにおける性機能障害の副作用について詳細な図があるのが注目点となります9.McEvoy et al. Am J Psychiatry. 2007 Jul;164(7):1050-60. doi: 10.1176/ajp.2007.164.7.1050.
・早期精神病における二重盲検試験10.Emsley R, Rabinowitz J, Medori R; Early Psychosis Global Working Group. Schizophr Res. 2007 Jan;89(1-3):129-39. Epub 2006 Nov 7.
・初発精神病における二重盲検試験11.Green AI et al; HGDH Study Group. Schizophr Res. 2006 Sep;86(1-3):234-43. Epub 2006 Aug 2.
・初発精神病における二重盲検試験。オランザピンの体重増加が強烈です。その他の薬剤もですが初回エピソードでは副作用が出やすいことを示唆するものです。12.Moller et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2008 Nov;11(7):985-97. doi: 10.1017/S1461145708008791. Epub 2008 May 9
・初回エピソード統合失調症における二重盲検試験。ハロペリドールのEPSの出現のしやすさなど。13.Cheng et al. J Psychopharmacol. 2019 Oct;33(10):1227-1236. doi: 10.1177/0269881119872193. Epub 2019 Sep 5.
・初回エピソード統合失調症における二重盲検試験。リスペリドンと比較したアリピプラゾールの特性がいろいろな指標の経時変化で示されています14.Kim et al. NPJ Schizophr. 2021 May 25;7(1):29. doi: 10.1038/s41537-021-00158-z.
・早期統合失調症におけるアリピプラゾールとD2アンタゴニストの比較のメタ解析など15.Zhu et al. Lancet Psychiatry. 2017 Sep;4(9):694-705
・初回エピソード統合失調症のネットワークメタ解析。初回エピソードに対する試験そのものが少ないため、比較対象となる薬剤の種類やデータが乏しく、確定的な結果が出せない現状がわかります。16.Hiroyoshi Takeuchi et al. Neuropsychopharmacology (2019) 44:1036–1042; https://doi.org/10.1038/s41386-018-0278-3
・初回エピソードと2回目のエピソードで同じ薬剤を使用しても有効性が異なることを報告したもの。貴重な報告です。17.APA guideline 2020:https://psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890424841
・BAPガイドラインに比べてざっくりとした記載の印象ですが、各薬剤の副作用比較の図とかはわかりやすいです。ネット公表版では図の一部が欠落してて不完全です。18.Hitoshi Sakurai et al. Pharmacopsychiatry. 2021 Jan 12. doi: 10.1055/a-1324-3517
・日本臨床精神神経薬理学会のエキスパートコンセンサスです19.Hiroyoshi Takeuchi et al. Hum Psychopharmacol. 2021 Nov;36(6):e2804. doi: 10.1002/hup.2804. Epub 2021 Jul 9.
・日本臨床精神神経薬理学会の治療アルゴリズムです20.Lee et al. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2020 Aug 31;18(3):386-394. doi: 10.9758/cpn.2020.18.3.386.
・韓国でのアルゴリズムです21.日本神経精神薬理学会 統合失調症薬物治療ガイドライン 2015(2017年改訂)
22.日本神経精神薬理学会 統合失調症薬物治療ガイドライン 2022
・2017年改訂版でのCQ1-4が無くなってしまったことと、そのかわりになる論文が文献23で示されています。23.Hui et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2022 Apr 22:pyac002. doi: 10.1093/ijnp/pyac002. Online ahead of print.
・Asian Network of Early Psychosis Wriing Groupによる素晴らしいガイドライン。10年予後で有名なDr.Huiらのグループが精力的に初回エピソードと治療中断可能性の問題に取り組んでこられてきたことがよくわかるものです。24.CU Correll et al. NPJ Schizophr. 2022 Feb 24;8(1):5. doi: 10.1038/s41537-021-00192-x.
・各ガイドラインの比較の系統的レビュー25.S. Leucht et al. Am J Psychiatry. 2017 Oct 1;174(10):927-942. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.16121358. Epub 2017 May 25.
・プラセボ反応率が年々違うことや、プラセボ反応率に影響しうる要因などを解析したもの。結果はなかなか興味深いです。26.Schneider-Thoma et al. Lancet. 2022 Feb 26;399(10327):824-836. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01997-8
・維持療法期のネットワークメタ解析。主要評価項目の解析にBayesian NMAを使用しており、そのため文献27と結果が一部異なります。27.Giovanni Ostuzzi et al. World Psychiatry. 2022 Jun;21(2):295-307. doi: 10.1002/wps.20972
・維持療法期のネットワークメタ解析。文献26と比べてサンプルサイズが50未満の試験は除外するなどinclusion criteriaの違いはありますが、主要評価項目の解析にFrequentist NMAを用いており、文献26との結果の違いの原因となっています。28.JE Thomas et al. Curr Neuropharmacol. 2015;13(5):681-91. doi: 10.2174/1570159x13666150115220221.
・ルラシドンやアセナピンなどのアカシジア出現頻度を以前からの第2世代薬と比較したものです。抗コリン作用が乏しい分、出現しやすいのかと思います。29.Carbon M. et al. World Psychiatry 2018 Oct;17(3):330-340. doi: 10.1002/wps.20579.
・アリピプラゾールの遅発性ジスキネジア出現リスクが頭一つ抜けて有意に少ないことをmoderation analysisで示したものです。30.H Taipale et al. Lancet Psychiatry. 2021 Aug 30;S2215-0366(21)00241-8. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00241-8
・プロラクチンと乳癌リスクに関してのnested case-control研究。長期投与に際して重要な結果かと思います31.Pillinger et al. Lancet Psychiatry. 2020 Jan;7(1):64-77.
・抗精神病薬の代謝系副作用についてのネットワークメタ解析です。中性脂肪などのデータは他にないものになります。32.H. Wu et al. Wu et al. Schizophr Bull. 2022 May 7;48(3):643-654. doi: 10.1093/schbul/sbac001
・抗精神病薬と体重増加に関するdose-response meta-analysisです。dose-response meta-analysisは恣意的な操作が入っている解析ではありますが、図がきれいでいいですね。33.J Greger et al. J Clin Psychopharmacol 2021;41: 5–12
・後方視的なチャートレビューのため質は高くはないのですが、長期的な代謝系副作用についての報告です34.S. Leucht et al. Am J Psychiatry. 2020 Apr 1;177(4):342-353. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.19010034. Epub 2019 Dec 16.
・各抗精神病薬の短期的有効性に関するdose-response meta-analysisです35.S. Leucht et al. JAMA Psychiatry. 2021 Nov 1;78(11):1238-1248.
・維持療法期におけるdose-response meta-analysis36.H. Taipale et al. Lancet Psychiatry. 2022 Apr;9(4):271-279. doi: 10.1016/S2215-0366(22)00015-3. Epub 2022 Feb 16
・大規模コホートによる抗精神病薬の用量と再燃リスクについての報告で、0.9~1.1DDD投与した場合と比較して0.6DDD未満だと明らかに再燃リスクが増大することを示し、かつ再燃を繰り返すたびに抗精神病薬の用量が増えていくことをWithin-individual modelで示した観察研究です。37.J. Tiihonen et al. JAMA Psychiatry. 2019 May 1;76(5):499-507.
・大規模コホートによる単剤療法と併用療法の再入院リスクをwithin-individual analysisで比較した報告です。観察研究なのでバイアスリスクはありますが、このような解析は大規模コホートならではとなります。38.I. Bighelli et al. Lancet Psychiatry. 2021 Nov;8(11):969-980. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00243-1. Epub 2021 Oct 12.
・再燃予防における心理的介入のネットワークメタ解析です。通常治療のみと比較して、家族関係介入などが大幅に再燃リスクを減らしている結果は重要なものです。39.Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 15;11(11):CD008712
・CBT対その他の心理的介入の再発・再燃リスクの比較40.三宅 誕実ら 臨床精神薬理 15:1099-1107,2012
・統合失調症におけるうつ症状の総説です41.S. Leucht et al. Lancet. 2009 Jan 3;373(9657):31-41. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61764-X. Epub 2008 Dec 6.
・2009年の古いメタ解析ですが、第1世代と第2世代の比較を引用しました42.B Galling et al. Acta Psychiatr Scand. 2018 Mar;137(3):187-205. doi: 10.1111/acps.12854.
・統合失調症における抗うつ薬増強のエビデンスです。有効性は乏しいものですが、統合失調症における抗うつ薬の使用は少なくとも全体として陽性症状などを有意に悪化させることはなさそうです。43.M. Krakowski et al. Am J Psychiatry. 2021 Mar 1;178(3):266-274. doi: 10.1176/appi.ajp.2020.20010052. Epub 2021 Jan 21.
・統合失調症と攻撃性に関する比較試験です44.L Citrome et al. Psychiatr Serv. 2001 Nov;52(11):1510-4. doi: 10.1176/appi.ps.52.11.1510.
・これも統合失調症と敵意、攻撃性に関する試験です。45.A. Serretti et al. Int Clin Psychopharmacol. 2011 May;26(3):130-40. doi: 10.1097/YIC.0b013e328341e434.
・性機能障害についてのメタ解析です。46.Yaara Zisman-Ilani et al., JAMA Psychiatry. 2021 Nov 1;78(11):1183-1184
・SDMについて47.中込和幸 臨床精神薬理 14:688-703,2011
・アドヒアランスについての総説です・今年に入って2月と6月に維持療法期間における抗精神病薬の有効性に関するネットワークメタ解析の報告が2報(26と27)でて、細かいところで結果がかなり異なる部分があり、inclusion criteriaの違いかと思って、frequentist NMAでいろいろやってみたのですが違いを再現できず、Prof. Stefan Leuchtにメールで聞いてみたら筆頭著者のDr. Schneider-Thomaにつないでいただき教えていただきました。一言でいえばFrequentist NMAとBayesian NMAの違いということらしいです。昨年に引き続き親切に教えていただいてありがとうございます。
-
耳鳴のこと
2022年05月29日
・耳鳴は原因がはっきりしている場合(口蓋ミオクローヌス、聴覚系の脱神経、蝸牛有毛細胞の喪失、耳毒性薬剤(アミノグリコシド系抗菌薬,プラチナ製剤,サリチル酸,ループ利尿薬,抗マラリア薬,マクロライド系抗菌薬など)など)には介入可能な場合もあるらしいのですが、なかなか原因がはっきりしない場合も多いみたいです。耳鳴再訓練療法(TRT)などが行われ有効性が報告されていますが、薬物療法についてはどうなのかということで、ネットワークメタ解析の結果が報告されました(文献1)
対象と方法
・薬物療法ないし栄養サプリメントによる耳鳴への有効性を評価したRCT・ネットワークメタ解析(頻度論)
・主要評価項目は耳鳴重症度変化、副次評価項目は反応率、QOLなど
・反応の定義は様々で、Tinnitus Handicap Inventory(THI)でベースラインの1/3以上の改善、VASで50%以上の改善、ベースラインから15dB以上の耳鳴の減少、全般的改善度4点以上、THI36点未満、THIで10点以上の改善、tinnitus handicap questionnaire scoreで20点以上改善など
結果
・36 studies(n=2761)、平均治療期間 11.9週間(2-24週)
・耳鳴重症度の改善についてプラセボと有意差がみられたのはアミトリプチリン、acamprosate、ガバペンチン+リドカイン皮内注射(intradermal lidocaine injectionと書いてあったので訳に間違いはないと思うのですが、場所が気になります)であった。
・反応率については鼓室内デキサメタゾン注入+メラトニン経口投与,メラトニン経口投与+sulodexide,メラトニン単独投与,アミトリプチリン経口投与,acamprosate経口投与,亜鉛補給,ガバペンチン経口投与+リドカイン皮内注射がプラセボ群に比べ有意に高い反応率となった
・QOL、脱落率についてはプラセボと有意差なし
議論
・重度の耳鳴知覚は、体性感覚系の痛み知覚に見られるのと同様の神経伝達物質分泌異常を引き起こし、それはGABA作動性抑制の低下と関連するとの報告がある。カルシウムチャネル蛋白に結合して広く抑制作用を発揮するガバペンチンはGABA系作動薬と類似の効果が期待できる。
・アミトリプチリンは、GABAやα1アドレナリン受容体など複数の神経伝達系を介して、中枢体性感覚系の侵害受容に役割を発揮することが報告されている。
・特定の原因または治療可能な起源のない耳鳴患者は、脳の複数の領域で有意に過活動であることが報告されており、異常な過活動を抑制する戦略は、耳鳴りの重症度を減らすために有益な効果を発揮する可能性がある。例えば、acamprosateは、グルタミン酸作動性のNMDA受容体阻害とGABA系促進作用(この部分原文がGABA抑制と間違いがありましたので修正しています)により、治療的効果を発揮する可能性がある
・メラトニンは、ドーパミン拮抗作用(Cell Mol Neurobiol. 2001 Dec;21(6):605-16)と抗酸化作用を併せ持つといわれている。耳鳴関連聴覚辺縁系ドーパミン作動性経路は、前頭前野、primary temporal、側頭頭頂連合野および辺縁系内に位置し 、耳鳴知覚経路と脳内構造を共有しているので、耳鳴治療への新規アプローチと考えられる.酸化ストレスと抗酸化酵素の不均衡は、耳鳴の病因のひとつと考えられている。メラトニンのような抗酸化物質の補給は、耳鳴治療に有効である可能性がある
・鼓室内ステロイド注射(デキサメタゾン)は理論的には蝸牛損傷に由来する初期段階の耳鳴に対する有望な治療方法である。今回のネットワークメタ解析では原因不明の耳鳴を対象としたため鼓室内ステロイド注射単独ではプラセボとの有意差がみられなかったが、メラトニン投与と組み合わせることで有意な治療効果が期待できる結果となった
コメント
・メラトニンにはいろいろな作用があるようで、強力な抗酸化作用があることは知っていたのですが、この点ラメルテオンはどうなのでしょうか?抗炎症作用を示唆する動物実験はあるようですが、なかなか答えがみつかりません。
文献1
J.-J. Chen et al. / EClinicalMedicine 39 (2021) 101080 -
統合失調症の病態生理
2022年05月18日
2年ぶりに勉強会でこの話題に触れることになったので、以下の論文などを参考に内容をアップデートしました
1.Dopaminergic dysfunction and excitatory/inhibitory imbalance in treatment-resistant schizophrenia and novel neuromodulatory treatment
Wada M. et al. Mol Psychiatry. 2022 Apr 20. doi: 10.1038/s41380-022-01572-0. Online ahead of print.・ゆるゆるLINE抄読会で慶應の中島先生にシェアいただいた論文です。ドーパミン仮説からExcitatory/Inhibitory Imbalance仮説に至る全体的な流れを構成するのにものすごく引用させていただきました。現段階では統合失調症および治療抵抗性統合失調症の病態生理に関する最も優れた総説で大変勉強になりました。この場を借りてお礼申し上げます。
2.Prefrontal and Striatal Dopamine Release Are Inversely Correlated in Schizophrenia
W. Gordon Frankle et al. Biological Psychiatry May 14,2022DOI:https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2022.05.009・これも中島先生に教えていただいた論文です。1991年にPETを用いた研究(Am. J. Psychiatry 1991, 148, 1474–1486.)により前頭葉でのドーパミン伝達の減少と線条体におけるドーパミン伝達の過剰にドーパミン仮説が修正されましたが、今回、統合失調症患者にアンフェタミンを投与し、2種類のトレーサーを用いてPETで同時に複数の関心領域と背側尾状核のドーパミン放出量の変化についての相関関係が検討されました。その結果、dorsolateral prefrontal cortex、medial prefrontal cortex、parietal cortex、enthorinal cortex、anterior cingulate cortexなど複数の部位におけるドーパミン放出量の変化と背側尾状核におけるドーパミン放出量の変化の間に逆相関関係が観察されました。健常者ではこのような逆相関関係は観察されませんでした。1991年以来の仮説が検証されたことになります。
3.Striatal dopamine mediates hallucination-like perception in mice
K. Schmack et al. Science. 2021 Apr 2;372(6537):eabf4740. doi: 10.1126/science.abf4740.・マウスの幻聴体験を間接的にdetectしたかもしれないという論文です。40 dbの背景ノイズ中で様々な大きさのシグナル音を提示して、そのシグナル音を探知した場合には探知(Hit)側のポートを突いて、音を探知しなかった場合には別のポート(Correct reject)を突き、正しい選択をした場合には予測不可能なランダムな時間後に水の報酬が与えられるシステムが作成されました。マウスは中央のポートを突くことにより、自ら新たな試行を開始するようにされました。このシステムで数週間トレーニングを実施し、十分なトレーニングを実施し正確な選択ができるようになってから5%の確率で正しい選択をしても水がでないように設定されました(無報酬課題)。この無報酬課題において、invested timeを測定(「あれ?正しい選択をしたのに水がでてこないぞ」と次の課題に行かず水を待っている時間)し、このinvested timeがマウスの自信の程度とみなされました。つまり、自信をもって間違える=幻聴を体験している?とみなされたということです。
・報酬処理に関与することが知られている腹側線条体と知覚処理に関与することが知られている背側尾部線条体の細胞に、アデノ随伴ウイルスベクターでドーパミン蛍光センサーであるGRABDAを発現させ、ファイバーフォトメトリーを用いたこれらの部位のドーパミン量を定量化し測定した結果、両部位のドーパミン放出量は、invested timeの大きい誤選択課題時に有意に多いことがわかりました。さらに背側尾部線条体のドーパミン神経にチャネルロドプシン2を発現させたトランスジェニックマウスを作成し、背側尾部線条体のドーパミン放出を刺激したところ、刺激施行しドーパミン放出を増加させた時には、無刺激施行時と比較して、有意に誤選択率が上昇し、その上昇はハロペリドールにて改善したということです。線条体のドーパミン放出の増加と幻聴の関連性を示唆する結果かもしれません。
4.Muscarinic Cholinergic Receptor Agonist and Peripheral Antagonist for Schizophrenia
Stephen K. Brannan et al. N Engl J Med 2021; 384:717-726・背側線条体でのドパミン放出はアセチルコリンM4受容体により調節を受けることが知られています。M4受容体を介した薬が開発されれば錐体外路症状のない抗精神病薬が期待できることとなります。M1/M4受容体のアゴニストであるxanomelineは小規模RCTで統合失調症患者の症状改善に有効な可能性を示唆する結果が得られていましたが、消化器系などの副作用のため開発は中断されていました。そこで副作用軽減のため末梢性ムスカリン受容体アンタゴニストであるtrospiumと組み合わせた臨床試験が行われました。5週間で投薬群はプラセボ群と比較して有意に陽性症状尺度などで改善効果がみられ、消化器系の副作用も顕著ではなかったようです。期待通りパーキンソニズムも有意なものはありませんでした。今後どうなるのか注目されます
5.Pimavanserin for negative symptoms of schizophrenia: results from the ADVANCE phase 2 randomised, placebo-controlled trial in North America and Europe
Bugarski-Kirola D et al. Lancet Psychiatry. 2021 Nov 30:S2215-0366(21)00386-2. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00386-2. Online ahead of print・セロトニン仮説は下火ですが、健常者へのLSD投与による自我障害を示唆する結果の報告(J Neurosci. 2018 Apr 4;38(14):3603-3611. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1939-17.2018. Epub 2018 Mar 19.)を引用していたことに関連して、セロトニン2A逆作動薬のピマバンセリンの臨床試験の結果についても紹介しました
6.Top-down control of hippocampal signal-to-noise by prefrontal long-range inhibition
Malik et al. Cell. 2022 Apr 28;185(9):1602-1617.e17. doi: 10.1016/j.cell.2022.04.001・グルタミン酸神経系の異常が、内側前頭前野→視床結合核→海馬→腹側被蓋野の流れで、ドーパミン神経系の活動亢進をもたらすということが報告(J Neurosci. 2001 Jul 1;21(13):4915-22 )されており、グルタミン酸系の異常がドーパミン系の異常の上流に位置することが示唆されていましたが、今回前頭前野から海馬への直接的なトップダウン制御がGABA神経の長距離投射により行われていることがわかったという報告になります。長距離投射GABA神経は海馬CA1のVIP介在神経を抑制し、物体位置の符号化のための信号についてのsignal-to-noise比を向上させ、物体によって生じる空間情報を増大させ、探索行動に関連するネットワークダイナミクスを促進しているということのようです。
7,Current findings and perspectives on aberrant neural oscillations in schizophrenia
Hirano et al. Psychiatry Clin Neurosci. 2021 Dec;75(12):358-368・九大の平野先生らの総説となります。ゆるゆるLINE抄読会で平野先生に教えていただきました。統合失調症におけるgamma oscillationの異常からExcitatory/Inhibitory Imbalance仮説まで、統合失調症のelectrophysiologicalな病態についての現状理解と今後の展望が解説されています。十分な理解はできていないのですが、特に論文中figure.3の40 Hz(70dB)のauditory steady-state response(ASSR)時のEEGから得られた誘導ガンマ帯域 oscillationの図はとても美しい結果で感動しました。ご紹介いただきありがとうございます。
8.Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia
Trubetskoy et al. Nature. 2022 Apr;604(7906):502-508. doi: 10.1038/s41586-022-04434-5. Epub 2022 Apr 8.・過去最大規模の統合失調症に関するゲノムワイド関連分析になります。ヒトの単細胞発現データからは、大脳皮質や海馬の興奮性グルタミン酸作動性ニューロン(錐体細胞CA1、CA3細胞、歯状回顆粒細胞)や皮質抑制性介在ニューロンで高発現する遺伝子に、強く統合失調症との関連が濃縮されていることが分かりました。Excitatory/Inhibotory Imbalance仮説を支持する所見かもしれません。
9.The shallow cognitive map hypothesis: A hippocampal framework for thought disorder in schizophrenia
Musa et al. Schizophrenia (2022) 8:34 ; https://doi.org/10.1038/s41537-022-00247-7・海馬を舞台としたshallow cognitive map hypothesisですが、海馬でのabberant salience仮説とも関連があり、海馬での統合失調症の病態に関する総説としても優れており、引用させていただきました。
-
CHR-P
2022年05月09日
・統合失調症の専攻医勉強会を進めるにあたって、この分野は避けて通れないので、何年か前から少しずつまとめていた論文集の見直しと、ここ2年ほどで新たに出版された論文を付け加えるアップデート作業をしていて、疾患概念について知らなかった点に気がつきました。
・今までCHR-P(Clinical High Risk for Psychosis)とUHR-P(Ultra High Risk for Psychosis)はほぼ同じ概念だろうと思ってあまり気にしてなかったのですが、厳密には違うようです。
・Dr. Fusar-Poliによれば、CHR-PはUHR-Pかつ/またはbasic symptoms(基底症状)を含む概念ということで、UHR-Pよりも幅広い概念のようです(Fusar-Poli et al. JAMA Psychiatry. 2020 Jul 1;77(7):755-765)。
・さらにUHR-Pとは何か?ということですが、オーストラリアでYungらによりARMS(at risk mental state)の概念が1990年代後半に提唱され、ARMSの基準を満たす前駆状態のことがUHR-Pと呼ばれたようです。アメリカでもこの考え方を導入し同時期にCOPS(Criteria of Psychosis-Risk Syndrome)の概念が定められました。ARMSとCOPSは似ていますが細かいところで診断基準が異なっており、詳細は辻野尚久先生らの総説(発症危険状態の評価:臨床精神医学 41(10):1407-1412, 2012)をご参照いただければと思いますが、この2つの概念が出てからは、だいたいCOPSかARMSのことをUHR-Pと呼ぶようです(Fusar-Poliら 2020)。
・ARMSないしCOPSにはそれに対応する操作的診断基準と構造化面接法が定められており、ARMSに対してはCAARMS、COPSに対してはSIPS/SOPSが対応します。CHR-Pに関するメタ解析などに含まれるstudyでは、SIPSを用いたものの比率が一番高いようです。
・さらに基底症状を軸にした診断基準としてはドイツのケルン早期発見研究で用いられた予測的基底症状(COPER)および認知的基底症状(COGDIS)があり、それに対応する評価尺度としてずボン基底症状評価尺度(BSABS)、その英語版のSPI-Aなどがあるようです。このあたりの詳しいところは針間博彦先生の総説(臨床精神医学 41(10):1395-1405,2012)をご参照ください。
・というわけで、細かいところですが、CHRに関する論文を読むときに、このあたりの用語の違いをおさえておくと混乱が少なくなるのでいいかと思います。CHR-Pに関する系統的レビューなどに含まれる論文では、CHRの診断的評価にCAARMSを用いたのか、SIPSを用いたのか、それともSPIなどか、それ以外かなどにわかれており、どの基準を用いたかで、オーストラリアからの報告なのか、北米なのか、それ以外なのか、ということも読みとれます。
・CHRの論文を読んでいて気になるのはcomobidityの多さです。UHR患者の90%が何らかの非精神病性の精神疾患を合併しているとの報告(Early Interv Psychiatry. 2021 Feb;15(1):104-112 )もあり(一番多いのは不安障害)、機能的予後はUHR症状が改善しようがしまいが、有意差はないとの報告もあることから(Am J Psychiatry. 2011 Aug;168(8):800-5)、これら併存疾患で機能的予後が規定されているような気がしなくもないです。
・CHRに含まれる患者群は多種多様であることを踏まえて、どのように介入するかは個別に検討する必要がありそうです。
-
いじめと内在化障害など
2022年04月30日
・内在化障害、外在化障害というと児童思春期の分野で時々でてくるワードになります。
・例えば、ADHDに対するペアレント・トレーニングの有効性に関するコクランレビュー(Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;2011(12))では、2011年と少し古いのですが、ペアレント・トレーニングは子の外在化問題(攻撃性、反抗的態度、反社会的行動など)の改善には有意な効果は認めないものの、内在化問題(過度の不安や恐怖、抑うつ、心身症状など)の改善については、有意な効果(SMDで-0.48)を認めると報告されています(nが小さくエビデンスとしては成熟したものではないですが)
・今回、学校でのいじめ対策が内在化障害に対してどの程度の効果を有するかというメタ解析がでました(文献1)
いじめ対策は内在化障害の改善に有効か
背景
・うつ病や不安障害などの内在化障害は小児期において最も頻繁に診断される精神疾患の一つであり、若者の障害と負荷の最も頻度の高い要因となっている・縦断的研究では,内在化障害は小児期から成人期まで連続性があり,内在化障害は他のあらゆる精神疾患と比較して生涯有病率が高く、発症年齢の中央値は、不安障害は11歳と言われている。あらゆる精神疾患の生涯発症者の半数は14歳までに、4分の3は24歳までに発症していることから(Arch Gen Psychiatry. 2005 Jun;62(6):593-602),小児期の介入で標的となり得る修正可能なリスク要因を特定することが重要である。
・いじめの被害は、内在化障害の最も抽出しやすい危険因子の1つであると思われる。18歳でうつ病になるケースの29.2%は、青年期初期のいじめ被害が原因かもしれないとの報告があり(BMJ. 2015 Jun 2;350:h2469.)、13歳時点でいじめ被害を受けていない子どもと比較して、仲間から頻繁にいじめ被害を受けている子どもは、18歳時点でのうつ病発症の調整後オッズ比が2.32と報告されている
・いじめ防止は若者の精神的健康のために重要な課題である
・ユネスコ(2019)の調査によると、世界の子どもの32%が過去1カ月間に1日以上いじめの被害を経験し、若者の7.3%が過去1か月間に6日以上のいじめを経験している(UNESCO, 2019: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483)。大半の子供が学童期を通じて低頻度のいじめを経験するが、一部の子供では慢性的でエスカレートするいじめを経験することがあり、このようないじめが、より内在化障害のリスクを高めるといわれている( Journal of Community Psychology, 48, 1751–1769. 2020)
・国際人権法の観点からは、学校で安全に過ごす権利、いじめに伴う攻撃や被害に遭わない権利は、すべての子どもに与えられるべきである(Convention on the Rights of the Child 1989; Universal Declaration of Human Rights 1948)。
・いじめには様々な形態があるが、小児期の身体的、精神的、言語的いじめについては学校が主な舞台になると言われている。そのため学校におけるいじめ対策が重要である
学校でのいじめ対策の有効性
・いじめに対する12の国と65の学校ベースの介入プログラム(うち4つの主要なプログラム(KiVa, Olweus Bullying Prevention Program, NoTrap!, Viennese Social Competence Program )は複数の地域で複数回評価されていた)のいじめ加害および被害の減少に対する有効性を評価したメタ解析(International Journal of Bullying Prevention, 1, 14–31. 2019)によると、個別のプログラムでは、主なものではOlweus Bullying Prevention Programがいじめ加害の減少に最も効果量が大きく、NoTrap! Programが最もいじめ被害の減少に有効であった。
・いじめ対策の有効性には地域間格差が存在した。いじめ加害対策については香港、北アメリカやスカンジナビアで行われているものの効果量が大きく、いじめ被害対策についてはオーストラリア(https://apo.org.au/node/66537 )、スイス、スカンジナビア、北アメリカなどの順で効果量が大きかった
・プログラム全体として、いじめ加害を19-20%減少させ、いじめ被害を15-16%減少させると報告されている
・Fraguasらは、学校でのいじめ防止プログラムが精神的健康に及ぼす効果を評価した無作為割付試験(N=20)をメタ解析で評価し、介入を受けた集団全体の精神的健康に対する効果量 cohen’d= 0.205(95% CI 0.277-0.133)と報告した(JAMA Pediatrics, 175, 44–55. 2021)。ただし精神的健康の尺度は、QOL、自尊感情、自責感、社会的スキルなど様々な尺度が用いられており、内在化障害については評価されていない。またいじめ被害者の減少が、精神的健康の改善を媒介するのかどうかなども評価されていない
方法と対象
・4-19歳を対象に学校で実施されたいじめ防止のための介入を評価した研究
・いじめの定義を明確にし、主要評価項目としていじめの加害または被害の変化を測定し、介入後の副次評価項目として内在化障害を測定したもの
・介入群と介入を行わない対照群が設定されていること。無作為割付試験ないし非無作為割付で群間の介入前後での内在化障害に対する効果の比較を行った試験
メタ解析での効果の指標としてはHedge’s gを 用いた結果
・27 studies
・各試験のサンプルサイズは、対象を絞った介入の24人から、学校全体の介入における7,741人まで。
対象学年は、1~6年生が48%、7~12年生が52%。参加者の平均年齢は10.5歳。59%が、学校スタッフまたは教師によって介入が行われた。全校的な介入を含む研究が70%、対象を絞った介入が26%、全校と対象を絞った両方の要素を含む研究が3.7%。
51.9%(n=14)がクラスター無作為化試験、11.1%(n=3)が個別無作為化試験、29.6%(n=8)が非無作為割付試験、7.4%(n=2)がクロスオーバー試験・22の試験のうち15(68%)で効果量が0より大きく、介入が内在化障害の軽減が有効であることを示唆する結果であった。ただし全体として効果量はg=0.06(95%CI, 0.0284~0.1005)であり、対照群と比較して有意差はあるものの、いじめ防止介入は全体としては内在化障害の改善に対してほとんど効果がないことが示された
・うつ症状に対する効果量は0.06(95% CI, 0.014 ~ 0.107)、不安症状については0.08(95% CI, 0.11 ~0.158)であった
主にいじめ被害者らを対象とした標的型介入の効果量=0.01(95%CI, ー0.094~0.109)で対照群と比較して有意差なし,全校型介入では0.08(95%CI, 0.036~0.117)で対照群と比較して有意差あり。しかし,標的型と全校型介入の効果を直接比較した場合,群間差は有意ではなかった。議論
・学校を拠点としたいじめ防止介入が、内在化障害に与える効果は全体として有意ではあったが、効果量はとても小さく臨床的に意義のある効果とはいいがたい。またいじめ被害者などを対象とした標的型の介入が対象者の内在化障害の改善に対照群と比較して有意差がなかったのは意外な結果であり、いじめ発生後の心理的問題の解決が学校ベースの介入のみでは容易ではないことを示唆するものかもしれない
・主としていじめ被害者らを対象とした標的型の介入において有意な効果がみられなかったのは、その介入方法に一貫性がなく、6つの試験のうち、介入の実施も教師や学校職員によるものが3つ、臨床心理士実習生や心理学生によるものが2つなど経験豊富な専門家による介入が行われたとは言い難いことも原因かもしれない。標的型の介入については、より専門的な知識を有する者が一貫性のある介入を実施すべきであるといえるかもしれない。
・あるいは単に対照群の改善度も大きく、それゆえに介入群と有意差がつかなかったという可能性もある(個人的にはこれが一番可能性高いのではと思っています。included studiesの詳細を見たわけではないのですが、標的型の介入については、倫理的にいじめ被害者も含まれる対照群に何もしないというわけにはいかないので)
・というわけで、一次予防も大事ということもいえそうです。
CNS10-NPC-GDNF
・ついにこんな試験が始まるのかと注目の臨床試験なのですが、アメリカのCedars-Sinai Medical Centerで、ALSに対するCNS10-NPC-GDNFの第1相試験が開始予定となっています。
・このCNS10-NPC-GDNFとはなんぞやというとこですが、神経前駆細胞です。神経前駆細胞なので、おそらく臍帯血から採取されており、同種移植になりますので、免疫抑制剤も必要でしょう。
・何がすごいかというと、移植部位です。これまで脊髄実質に神経幹細胞を移植する臨床試験は行われてきました。
・有名なのがNeuralstem社の同種神経幹細胞移植であるNSI-566です。第2相試験までいったのですが、発症2年以内の15名の患者がエントリーされ、頸髄のC3からC5の間の領域に両側性の幹細胞移植を受け、3名では腰髄領域にも移植を受けました。椎弓切除術を受けなくてはならないので、かなり侵襲性の高い治療になります。結果は残念ながら有意な進行遅延効果はみられませんでした。そこで立ち消えになったかと思ったら、2020年4月にNeuralstem社がSeneca社に社名変更して、第3相試験を始めますみたいなことを公表したまま、その後音沙汰がない状況になっています。
・そこで今回のCNS10-NPC-GDNFです。神経栄養因子を分泌するように分化誘導した(アストロサイトになるとか?)神経幹細胞で、なんと移植部位は大脳の一次運動野です。脳に直接細胞移植されることになります。上位運動神経細胞の周辺に移植する臨床試験はこれまで行われたことがなかったので、初の試みになります。
・良い結果になることを願います。
elicit
・慶應の中島先生がオープンチャットでelicitの話題をシェアされてて、どんなもんなんじゃろうと思って使ってみてものすごくびっくりしました。
・なんだかAIをベースにした論文検索システムだとか。質問を入れると、その質問の答えに該当する論文をピックアップしてくれるどころか、質問に対する答えをその論文のアブストラクトから?抽出して簡潔に表示してくれます。
・この答えの部分が、まるで中に人間が入っているんじゃないかと思うくらい、うまいことまとめられています。最新の情報を手に入れるにはpubmedがいいのでしょうが、大雑把に自分の手に入れた知識などの普遍性や正確性などを検証するための目的にはとても便利だと思います。
・今後AIにGRADEシステムを教え込んだら、もう勝手にガイドラインを作ってくれる時代が来るのではないかと思わせる、そんな可能性を感じさせてくれるelicitです。研究者を対象にしているみたいですが、臨床疑問にもホイホイ答えてくれるので、臨床家にも全然お勧めです。
文献1:Carolina Guzman-Holst et al. J Child Psychol Psychiatry. 2022 Apr 26. doi: 10.1111/jcpp.13620. Online ahead of print.