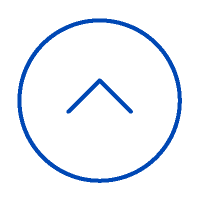-
ウルソはどうか
・7月に引き続き9月3日付The New England Journal of Medicine誌にALSの臨床試験についての話題が掲載されました(文献1)。
・Amylyx社のALS治療薬候補AMX0035の第2相試験(CENTAUR試験:NCT03127514)です。・AMX0035は既存薬の組み合わせでウルソのタウリン抱合体であるタウロウルソデオキシコール酸(taurursodiol)1gとフェニル酪酸ナトリウム(尿素サイクル異常症治療薬)3gの合剤(最初3週間は1日1回投与、その後1日2回投与)になります。
・タウロウルソデオキシコール酸は漢方薬の原料である熊胆(ゆうたん:熊由来の動物性生薬)の主成分でもあるということです。
・発症18カ月未満のdefinite ALS患者(孤発性ないし家族性)137名が対象となり、2:1の割合でAMX0035とプラセボに無作為割付され、24週間経過観察されました。
・主要評価項目はALSFRS-Rの変化率であり、副次的評価項目としては筋力、呼吸機能、人工換気導入までの期間などでした。
・主要評価項目は、AMX0035群平均-1.24点/月、プラセボ群平均-1.66点/月で統計的に有意にAMX0035はALSFRS-Rの変化率を改善することを示唆する結果が得られました。副次的評価尺度については統計的有意差が得られたものはありませんでした。
・最初のALS治療薬としての承認薬剤のリルゾールはどうなのか?リルゾールの承認に向けた臨床試験が行われたのは1992年頃であり、この頃にはALSFRS-Rは国際的な症状評価尺度としては使用されていなかったため、比較対象となりうるデータを見つけることができませんでした。
・国内2番目のALS治療薬として承認されたエダラボンについては、投薬期間の24週間でのALSFRS-Rの変化量は、エダラボン群では平均-5.70点、プラセボ群では-6.35点との結果が報告されています(プラセボに対して約10%の改善効果)。一方でAMX0035は同じ期間でプラセボ比約25%の改善度を示しています(試験の規模が違うことと、両薬剤で対象となった患者の患者背景が異なるため、単純な比較はできませんが)。なかなか良い数字のように見えます。
・試験の規模がそこまで大きくないことと、副次的評価項目で有意差がみられなかったことは気になりますし、毎度のことながら第3相で結果がひっくり返る薬剤を多くみてきたので、全然楽観視はできないのですが、この結果を受けてアメリカALS協会では、早くもFDAに対して1年以内のAMX0035の早期承認を求める嘆願活動を開始しています(https://www.als.org/stories-news/als-association-i-am-als-call-amylyx-fda-make-promising-new-drug-available-our-als)・タウロデオキシコール酸については、実はドイツで既に第3相試験が動いています(NCT03800524)。440名のALS患者を対象にタウロウルソデオキシコール酸2g/dayを18カ月投与し、プラセボと比較してどうなるかについて臨床試験が進行中です。順調にいけば結果は2021年6月には判明しそうなので、こちらの結果もどうなるか要注目というところです。
・最近のALS臨床試験の気になる動向としては、Biogen社が新たなアンチセンス・オリゴヌクレオチド製剤であるBIIB105の第1相試験(NCT04494256)の開始をアナウンスしたことです。
・この製剤の注目すべき新しい点は、これまでは直接的に有害性を発揮する蛋白質の発現を阻害するためのアンチセンス・オリゴヌクレオチド製剤が使用されてきたのと異なり、BIIB105は病態に間接的に関与している蛋白質の発現を抑制することにより、病態改善を図ろうという治療戦略である点です。
・BIIB105がターゲットするRNAはataxin 2 RNAであり、孤発性ALSにおいてはataxin 2発現量を減少させるとTDP-43蛋白症に関連した病態の改善効果が期待できることが報告されていることによるものです。
・これは2017年のNatureに報告されたモデルマウスでの基礎実験の報告(Nature. 2017 Apr 20;544(7650):367-371. doi: 10.1038/nature22038. Epub 2017 Apr 12.)を臨床応用するものであり、ヒトでの効果がどうなるのか期待されます
引用文献
1)September 3, 2020 N Engl J Med 2020; 383:919-930 DOI: 10.1056/NEJMoa1916945
-
gene silencingの2報
・7月9日付The New England Journal of Medicine誌にSOD1変異家族性ALSに対するgene silencing療法についての2報が報告(文献1、文献2)されました。
・SOD1遺伝子変異に起因したALSは家族性ALSの約20%、孤発性ALSの約1-2%と言われています。
・今回報告された治療法については、いずれも既によく知られている手法であり、手法そのものの新規性はないのですが、ヒトに対して行われた結果という点が新しいこととなります。特に文献1のmicroRNAをエンコードするアデノ随伴ウイルスベクターを投与してSOD1遺伝子発現を阻害する手法については2018年にモデルマウスでの報告がなされたばかりでしたが、2年足らずの間にヒトに対する実際の投与が行われたことになり、急速な進展を感じます。
・もう1つ(文献2)は2019年の製薬会社売上高世界20位の大企業(世界20位の売上高でも日本企業と比較すれば2位相当となります)Biogen社のALS治療薬候補Tofersenの第1/2相試験の結果となります。
・Biogen社の薬で有名なものとして脊髄性筋萎縮症治療薬のスピンラザ(選択的スプライシングを制御するhnRNAのmRNA前駆体への結合を阻害するアンチセンス・オリゴヌクレオチド製剤)があります。
・薬価が1バイアル949万円となり、これでも十分高いのですが、最近発売承認され、史上最高に高い薬として有名になったゾルゲンスマ(1バイアル 1億6707万円:アデノ随伴ウイルスベクターに正常SMN1遺伝子をエンコードするもの)と比較すると、ゾルゲンスマが単回投与でかつ静注可能なのに比較して(それでも手が滑ってこぼしてしまったりしたら1億6千万がパーですから、手が震えそうです)、スピンラザは髄腔内投与が必要で侵襲性も高く、4回目以降は4か月に1回(乳児型の場合)の投与が必要となる点でいろいろと異なるため、この価格差ということのようです。
・もっともゾルゲンスマが単回投与である理由は、投与後にアデノ随伴ウイルスに対する抗体が形成され、免疫反応が賦活されるからということで、単回投与後も肝機能障害が起きたり(その結果ステロイド剤を投与しないといけなかったり)することもあるようです。
・命はお金には替えられないということで高額であってもその治療効果は何物にもかえがたいのは理解できるのですが、最新号のMuscle & Nerve誌に脊髄性筋萎縮症1型に対してスピンラザとゾルゲンスマを併用して良好な治療効果が得られる可能性があるとの報告(Harada et al., Combination molecular therapies for type 1 spinal muscular atrophy. Muscle Nerve. 2020 Jul 25)が掲載されました。両者併用だと、2年間で薬代だけで2億6千万円というものすごいお値段になってしまいます。
・ゾルゲンスマを販売しているノバルティス社は、ゾルゲンスマを開発したベンチャー企業であるAveXis社を2018年4月に9300億円で買収しています。第3相試験まで到達していたゾルゲンスマが前途有望であると見込んで買収したものと思われますが、これまた桁違いの金額です。
・話を元に戻します。SOD1変異ALSに対するgene silencing療法のうちmicroRNAを注入する治療法ですが、2名の患者(22歳男性と56歳男性)に対して単回投与(髄腔内)が行われました。変異SOD1遺伝子由来のmRNAをブロックするmicroRNAは、ALS発症に関連する多くの変異をカバーできるように設計されたものということです。
・22歳の患者については、一過性に右下肢筋力の改善効果を認めたものの、呼吸機能は改善せず、投与後15.6か月で死亡しました。
・一方で、あらかじめ免疫抑制剤を投与された後にウイルスベクターを投与された56歳の男性については、1年以上安定した状態を維持しているということです。
・今後ウイルスベクターによる中枢神経に対するgene silencing療法は免疫抑制剤とセットにして行われるようになるのかもしれません。
・一方でもう1つのgene silencing療法であるアンチセンス・オリゴヌクレオチドを用いた治療法ですが、ALSに対してはもう第3相試験まで進んでいます。
・今回の報告は第1/2相試験の結果についての報告となります。
・第1/2相試験では、SOD1変異ALS患者50名に対して、プラセボ対照で行われ20mg、40mg、60mg、100mgの4つの異なる用量で髄腔内投与されました。
・主要評価項目は安全性と薬物動態であり、副次的評価項目は85日目の髄液中SOD1濃度の変化でした。50名中48名が5回すべての投与を受けました。
・腰椎穿刺に伴う有害事象はほとんどの患者で観察され、髄液中白血球数の増加が4名で、蛋白質増加が5名で観察されました。
・85日目の髄液中SOD1濃度のプラセボ群との差は20mg投与群で平均2%、40mg投与群で平均‐25%、60mg投与群で平均-19%、100mg投与群で平均-33%でした。
・症例数が少ないため、有効性についての結論は出せませんが、12週後にプラセボ群はALSFRS-R得点で平均5.6点、肺機能得点で平均14.5点悪化したのに対して、tofersen100mg投与群ではALSFRS-R得点で平均1.2点、肺機能得点で平均7.1点の悪化となりました。特に進行の早い一群において進行抑制効果が顕著であったとのことです。
・髄液中SOD1濃度の減少はtofersenの最高用量で観察されました。一部の患者で髄液中の細胞増加が観察され、大半の患者で腰椎穿刺に伴う有害事象が観察されました。
・最高用量ではALSFRS-Rの12週間の変化量がかなり改善しているようにみえるので、現在進行中の第3相試験の結果が期待されます
引用文献
1)Mueller C et al. N Engl J Med. 2020 Jul 9;383(2):151-158. doi: 10.1056/NEJMoa2005056.
2)Timothy Miller et al. N Engl J Med. 2020 Jul 9;383(2):109-119 -
臨床試験とCOVID-19
臨床試験の進捗にCOVID-19が与える影響をあまり耳にすることはなかったのですが、これまでも触れたことのあるALSに対するBrainStorm社の自家間葉系骨髄幹細胞移植であるNurOwn細胞の第3相試験(NCT03280056 )が受けた影響が報じられていました。
結論からすると臨床試験の進捗に与える影響は、それほど大きなものではなかったようで、関係者の皆さんを安心させていますが、最も問題となるのは、受診をしないと評価できない臨床尺度をどうするかです。
臨床試験においては臨床症状の経時的な評価が重要であり、この第3相試験においても主要評価項目であるALSFRS-R得点が、正確な頻度は不明ながら、少なくとも3か月に1回以上は測定されるはずだと思われます。
このALSFRS-RはALSの進行を測定する際に用いられる最も標準的な指標であり、患者さんが受診をし、診察を受けて測定されることが通常です。しかし、今回のCOVID-19のパンデミックにより、受診をしての測定はやはり困難(何より患者さんが感染することは避けないといけない)な場合があるようで、遠隔での評価で代替されるようです。しかし副次的評価項目である髄液中のバイオマーカーについては測定ができない状況も起こり、データの欠失が起こりうるものと思われます。
アメリカの6つの施設で行われているこの臨床試験は、COVID-19流行以前(昨年10月)の終了予定時期が2020年10月頃でしたが、終了予定時期はそれほど影響を受けておらず、今年中には結果が判明する予定だということです。近年のALS臨床試験の中で最も期待されている試験であり、COVID-19の影響をあまり受けることなく順調に結果が出て、それが良好な結果であることを期待するばかりです。
精神疾患に対する臨床試験でも、同様の問題が起こりうると思われますが、そのあたりはどうなのでしょうか。既に新薬の発売時期は遅延などの影響が生じていますが、臨床試験があまり影響を受けないことを願います。
-
いじめに関すること
いじめに関して、いくつかの情報をまとめておきたいと思います。
いじめの定義
まず「いじめ」とは何か、ですが、平成25年に制定されたいじめ防止対策推進法第2条によると、
「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」
となっています。被害者の主観的な感情が重要である点がポイントとなります。
これは、いじめの”深刻さ”を評価する際に、加害者が行った行為が性質が客観的に見て深刻であるかのみでは評価されないということです。
つまり、暴力行為と言葉による嫌がらせを伴ういじめが、言葉のみのいじめと比較してより深刻であると一般的に言うことはできず、いじめを受けた被害者が、どのような心理的ないし物理的苦痛を受けたか、によりいじめの深刻さは定義されるということになります。
日本の被害者への心理的影響を主体とした定義では一部のいじめ被害者を見落としてしまう可能性も指摘されています。
例えば文献1ではいじめを以下のように定義しています”Bullying is any unwanted aggressive behavior(s) by another youth or group of youths . . . that involves an observed or perceived power imbalance and is repeated multiple times or is highly likely to be repeated. Bullying may inflict harm or distress on the targeted youth including physical, psychological, social, or educational harm.”
「いじめとは、他の青少年または青少年グループによる、観察された、または知覚された力関係の不均衡を伴う、望まれない攻撃的な行動であり、複数回繰り返されるか、またはその可能性が高いものである。いじめは、対象となる青少年に身体的、心理的、社会的、教育的な被害を含め、被害や苦痛を与える可能性がある」とされています。
ポイントは、「観察された」「可能性がある」との記載が入っている点で、いじめを受けたすべての青少年が、いじめによってどのような被害や苦痛を受けたかをすぐに特定したり、表現することができるわけではないことがありうるということです。
例えば、神経発達症児は、自分がいじめられたりからかわれたりしても、いじめであることを理解できず、将来的にはそれが繰り返されることで重大な結末を招く可能性があるものの、現時点では大きな苦痛を主観的に感じているとは限らないということです。このようなケースもいじめと定義すべきとされています。ですので、被害者の捉え方のみがいじめを定義する要件ではないとされています。
いじめの早期発見
いじめ被害者の心理的苦痛をきちんとアセスメントすることができないと、教師は潜在的ないじめの存在を見落とす危険もあります。
文献2によるとオーストラリアの8歳から16歳までの女子913人、男子755人のうち、約半数の回答者(682人)が、過去 12 ヶ月間に少なくとも 1 回はいじめられたことがあると報告しました。
このうち、教師に助けを求めたのは男子の41.1%、女子の35.6%でした。
日本での調査結果では、いじめ発見のきっかけとして、教職員が発見した割合が約13%、本人が訴えたのは約18%、アンケート結果が約52%、保護者からの訴えが約10%となっています(平成30年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査より)。
つまり、いじめを受けても教師に助けを求めない児童生徒の割合の方が大きいということになります。
これについては、児童生徒の教師への信頼度などにより個人差はあるでしょう。普段から相談しやすい体制作りが重要であるということになります。
アンケートで明らかになる割合が過半数であり。文科省の作成した「いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例」では、「各学期に1回以上、無記名でいじめに特化したアンケートを行う」こととなっています(それを忠実に反映した学校いじめ防止基本方針はあまりないようです。だいたい年に2回とかのところが多いようです)。
保護者への定期的なアンケート実施も必要と思われます
いじめの被害者、加害者の割合
日本での小学校から高校までのいじめ認知件数は平成30年度で年間約54万件となっていますが、これはのべ件数ですので、実際に被害を受けた児童生徒の割合はわかりません。
アメリカでの年齢層が若干異なる4つの全国調査の結果(文献1)によると、National Crime Victimization Survey では、2011年に12歳から18歳の28%が学校でいじめを受けたことがあると回答しています。高校生を対象としたYouth Risk Behavior Surveyでは、2011年には20%の生徒が前年に学校の敷地内でいじめを受けたことがあると報告しています。
The Health Behaviour in School-aged Childrenは、5年生から高校1年までの児童生徒を対象とし、2009~2010年には、28%の児童生徒が過去2カ月間に少なくとも1回学校でいじめを受けたことがあり、11%の児童生徒がこの期間に月に2~3回以上いじめを受けたことがあると報告しています。
2歳から17歳までを対象とした養育者と児童生徒を対象とした全国電話調査では、13パーセントの子どもたちが身体的ないじめを受け、20パーセントの子どもたちが前年にいじめられたり、感情的ないじめを受けたりしたことがあることがわかりました。
アメリカと日本では状況は異なるかもしれませんが、日本がアメリカと同じ状況であり、仮に年間のいじめ被害率が20%とすると、日本での年間いじめ発生件数は小学校から高校までの児童生徒数を1250万人とすると、少なくとも250万件と推計されることとなります。
人種的問題などの背景の違いはありますが、潜在的ないじめ発生件数はもっと多い可能性があることに注意を要します。
一方、いじめに関して、第一群を、他人をいじめているが、自分自身はいじめられていない群(被害者)、第二群を、いじめられているが、他の人をいじめていない群(加害者)、第三群を、自分自身がいじめられているだけでなく、他の児童生徒もいじめている群(被害者であり加害者でもある)とすると、いじめに月に 2~3 回以上関与していた小学3 年生から 高校3年生を対象とした研究では、第一群が全生徒の 13%(被害者)、第2群が4%(加害者)、第3群が3%(被害者であり加害者でもある)との調査結果が報告されています(文献1)。
単なる加害者と同じくらいの割合で加害者かつ被害者も存在する可能性があることに注意を要します。
いじめの態様
どのようないじめが認知されているかについて、文科省平成30年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査より引用すると、「冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる」が62.7%(いじめ全体に占める割合)、「仲間はずれ,集団による無視をされる」が13.6%、「軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする」が21.4%、「ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする」が5.5%、「金品をたかられる」が1.0%、「金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする」が5.5%、「嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする」が7.8%、「パソコンや携帯電話等で,ひぼう・中傷や嫌なことをされる」が3.0%などとなっています。
海外のデータでは、12-18歳におけるネットいじめ被害を受ける割合が生徒全体の9%(いじめに占める割合ではなく、生徒全体に占める割合)との報告もあり、悪い噂を流す(18%)、悪口(18%)に次いで3番目に多い態様であったとの報告(文献1)もあり、海外では生徒の10人に1人がネットいじめの被害を受けているとの報告(2014年)もあり注意を要します。いじめの加害者の心理と加害者のリスク
いじめ加害者になる心理的背景としては、一般化は困難であるにしても、以下のような状況は想定すべきでしょう。
加害者における家庭環境における問題や未熟な防衛機制の発動しやすい状況など、学校内外での抑圧された状況が、心理的な代償として、被害者をターゲットとするいじめにつながると理解できる場合があります。
このあたりはいじめ加害者の保護者と面談の際、考慮すべき状況と思われます。
またいじめ加害者のその後の経過として、中学時代にいじめ加害者となると、成人になってから3つ以上の犯罪歴を持つ可能性が4倍になることや、後に犯罪に巻き込まれるリスクが高いことがわかっています。
また中学生でいじめ加害者となることは、その後の他人へのセクシュアル・ハラスメントやデート・バイオレンスの加害者となるリスクが高いことがわかっています(文献1)。
このようなことから、被害者のみならず、加害者へのケアも重要であることがわかります。単なる加害者に対する注意や叱責、懲罰によるいじめの抑圧は、さらに加害者の抱える心理的問題を悪化させる可能性があり、問題行動の修正のための肯定的なモデルが提案されていないため、最小限の効果しかないと言われています(文献3)
いじめへの対応について
いじめにどう対応すべきか、文科省の「いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例」によれば、
*いじめられた生徒又はその保護者への対応
・ 生徒から,事実関係の聴き取りを行う。
・ 生徒や保護者に「最後まで守り抜くこと」や「秘密を守ること」をはっきりと伝える。
・ 生徒の個人情報の取扱い等,プライバシーには十分に留意する。
・ 事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報は,家庭訪問等で速やかに保護者に伝える(即日対応)。
・ 生徒にとって信頼できる友人や教職員,家族等と連携して支える。
・ 安心して学習に取り組むことができるよう,必要に応じて別室での学習を提案する。
・ 状況に応じて,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの協力を得る。
・ 謝罪や事後の行動観察の結果,いじめが解消したと思われる場合でも,見守りは継続する。
* いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
・ 生徒から事実関係の聴き取りを行う。
・ いじめとして認知した場合,組織で速やかに対応し,謝罪の指導を行う。
・ 聴き取った内容を速やかに保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解を得る。
・ 保護者と連携した適切な対応ができるよう協力を求めるとともに,継続的な助言を行う。
・ 組織として毅然とした指導を行い,いじめは絶対に許されない行為であることを理解させる。
・ 生徒が抱える問題にも目を向け,いじめを繰り返さないよう継続的に指導・支援する。
* いじめが起きた集団への働きかけ
・ 知らなかった生徒や傍観していた生徒に対しても,自分の問題として捉えるように指導する。
・ いじめをやめさせることはできなくても,誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
・ はやしたてたり,同調したりする行為は,いじめに加担する行為であることを理解させる。
・ 教育活動全体を通して,いじめは絶対に許されない行為であり,根絶しなければならないという態度を育む。などとなっています。
実際にどのような対応がなされているかですが、文科省平成30年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査によれば、「いじめられた児童生徒への特別な対応」(特別な対応と書いてありますので、上記のいじめられた生徒又はその保護者への対応以外の対応と思われます)としてはは「スクールカウンセラー等の相談員が継続的にカウンセリングを行う」が3.2%、「別室を提供したり,常時教職員が付くなどして心身の安全を確保」が4.0%、「緊急避難としての欠席」が0.2%、「学級担任や他の教職員等が家庭訪問を実施」が11.3%、「学級替え」が0.1%、「当該いじめについて,教育委員会と連携して対応」が2.9%、「児童相談所等の関係機関と連携した対応(サポートチームなども含む)」が0.3%など(複数回答可)となっています。続いて、「いじめる児童生徒への特別な対応」としては、「スクールカウンセラー等の相談員がカウンセリングを行う」が1.8%、「校長,教頭が指導」が4.8%、「別室指導」が11.3%、「学級替え」が0.1%、「退学・転学」が0.1%、「停学」が0.1%、「出席停止」は全国で1名(中学校1件)のみ、「自宅学習・自宅謹慎」(出席停止との違いがいまいちわかりませんが)が0.2%、「訓告」が0.1%、「保護者への報告」が45.6%、「いじめられた児童生徒やその保護者に対する謝罪の指導」が43.4%、「警察等の刑事司法機関等との連携」は0.2%、「児童相談所等の福祉機関等との連携」が0.2%、「病院等の医療機関等との連携」が0.1%、「地域の人材や団体等との連携」が0.1%などとなっています(0.1%で500件程度)。
いじめに対する対応として、推奨されない方法が存在します。文献1によれば、いじめをした生徒を自動的に停学にするゼロ・トレランス・ポリシーは推奨されません。
またいじめをする生徒を一緒にグループ化することは、攻撃性を高め、いじめを悪化させる可能性があります。
また簡潔な集会や1日だけの啓発キャンペーンは、児童生徒に対する持続的な教育効果という点では、ほとんど効果がないと言われています。
またいじめ対策としては、傍観者をいかに仲裁者ないしシェルターのような存在にするかが重要であるとの議論もあります(文献4)。
これは教師の介入の契機をつくるため、およびたとえ中立的な存在であっても(友人とまでは言えなくても)、被害者を孤立させない仲間の存在があることにより、いじめによる心理的苦痛の軽減効果が大きいことを示唆する研究結果が存在していることによります。
文献1によれば、オンライン実験により、オンラインの活動から排除された若者について、無作為に未知の仲間とのインスタント メッセージのやり取りを行う群と、孤独なコンピューター ゲームをプレイする群とに割り付けしたところ、心理的苦痛からの回復は、孤独なコンピュータゲームをプレイするよりも、未知の仲間と対話する機会を持っていた人のためにはるかに迅速であったことが報告されています。これらの知見は、中立的な社会的交流でさえも、いじめられた後の心理的苦痛の回復に有用である可能性があることを示唆するものです。
したがって、教室における傍観者をいかに積極的に関わりうる存在にするかは重要といえます。
教師らの介入により、どの程度いじめの軽減効果があるかについては、文献2によると、いじめ被害者223名へのアンケートにより、7割近い児童生徒がいじめがなくなった(29%)ないし減少した(39%)と報告しています。
悪化したと答えたのは全体の7.6%でした。
このように教師の介入により大半が改善していることから、まずはいじめを教師が知るところとし、教師が介入を行うことが重要と言えます。
また教師はいじめを認知した場合には速やかに介入することが求められます。文献3によれば、教師がいじめを無視したり矮小化したりする場合、あるいは教師の介入の欠如を生徒がいじめを暗黙のうちに受け入れていると解釈する場合、攻撃的な行動が増える可能性が高くなるとされています。
また被害を受けた生徒は今後いじめを報告することを躊躇し、いじめを観察した生徒は介入したり助けを求めたりする意欲が減退すると感じることがあります。
教師が介入して、教師はいじめは受け入れられないことを伝えると、その結果、生徒はこの種の行動を正当化しようとする傾向が少なくなります。
また、いじめは放置すればするほどエスカレートする可能性も指摘されています(文献4)。早期介入が重要といえます。
教師の介入手法としては大まかに3つの戦略があるとされます。
第一は,加害者に対する懲罰戦略(指導,叱責、除名など)です。
しかし先に述べたように、この方法は社会的行動の修正のための肯定的なモデルが提案されないと、効果が乏しいものとなります。また加害者の心理的ケア(特に未熟な防衛機制が関与していると考えうる場合)が置き去りになってしまうと、根本的問題の解決にはなりません。
第二の戦略は、被害者や加害者に向けられた個別の支援であり、心理的に支援し、被害を受けた生徒への共感を高めることです。
第三の戦略は、生徒間の協力を促進し、保護者や他の専門家の支援を得て、クラスのすべての生徒を巻き込む支援協力的介入になります。
文科省の「いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例」では、加害者の保護者とも連携し、より効果的な加害者への教育的介入を模索する方向性が提示してあります。
この際、加害者の保護者の加害生徒への関わり方、家庭環境などが加害行為の背景要因として存在していないかをアセスメントすることは重要と思われます。実際には平成30年の文科省の報告では、先にみたように、加害者の保護者に対して報告などを行ったケースは全体の45.6%とされており、保護者との連携は半数以下となっている現状があり、今後の課題と思われます。
いじめが集団で行われている場合の対処は困難度が高いと言われていますが、以下のような方法が提案されています(文献2)
第1にサポートグループ法とよばれる方法があります。
これは、まず被害者にインタビューを行い、いじめの影響を受けた経緯や加害者が誰であるかなどの詳細な知識を収集します。
その後、この知識を加害者らと共有し、被害者をサポートし、加害者にも同じように影響を与えることを期待されている生徒を含む会議で共有し、加害者集団の問題意識の自覚と行動変容を期待するものです。
第2に共有懸念法(Method of Shared Concern)、またはPikas法として知られる方法があります。
この方法では、加害者である疑いのある生徒との一対一の面談に始まり、ついで被害者との面談が行われ、その後、加害者である疑いのあるすべての生徒との面談が行われ、話し合いによるいじめ解決策となりうる積極的な提案を考案し、可能であれば、被害者を含む最終的なグループ面談で解決策について合意するという包括的なアプローチになります。
いじめ防止対策推進法の施行に伴い、年々認知されるいじめ件数が増加し、現場の先生方のご負担は増えていきますが、先生方の心身の健康を保持しながら、包括的かつ効果的ないじめ対策が進むことが期待されます。
引用文献
1)National Research Council 2014. Building Capacity to Reduce Bullying: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18762.
2)Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2338; doi:10.3390/ijerph17072338
3)De Luca L, Nocentini A and Menesini E (2019) The Teacher’s Role in Preventing Bullying. Front. Psychol. 10:1830. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01830
4)荻上 チキ. いじめを生む教室 子どもを守るために知っておきたいデータと知識 (PHP新書). 株式会社PHP研究所. -
腸内細菌の話題
基礎研究レベルの話ですので、こんなお話もあるのかくらいの感じでみてください。
中枢神経疾患と腸内細菌叢の関係について2019年にNature,Cellなどの主要雑誌に論文が掲載され(文献1、文献3)、つい先日の5月にもNature誌に腸内細菌叢の論文(文献2)が掲載されたので、これはちょっと注目かもしれないということでとりあげてみました。
まず2019年のNature論文(文献1)について触れてみます。この論文では、家族性ALSにみられる変異SOD1蛋白質を発現するように遺伝子を組みこんだトランスジェニックマウスを作成し、SOD1変異ALSモデルマウス(仕様上イタリックにできないため、遺伝子表記をそのままにしています)の病態進行と腸内細菌叢の関係性が調べられました。
SOD1遺伝子変異によるALSの頻度は家族性ALS(ALS全体の5-10%程度と言われている)の中のさらに20%程度と言われています。
Blacherらはまず最初に、SOD1変異ALSモデルマウスの腸内細菌叢を各種抗菌薬を投与することにより除去しました。その結果病態進行が増悪しました。
続いて、健常マウスとALSモデルマウスの腸内細菌叢の構成細菌が調べられました。その結果、細菌の種類が異なることが明らかになりました。
11種類の細菌がモデルマウスの病態進行に影響を及ぼしうることが同定されました。
続いて、11種類の細菌を1つずつ腸内細菌叢除去モデルマウスに投与したところ、1つの細菌(Akkermansia muciniphila)が病態進行遅延をもたらしうることがわかりました。
一方、Ruminococcus torquesとParabacteroides distasonis は病態悪化をもたらしました。
Akkermansia muciniphilaの産生するニコチンアミドが中枢神経に到達し、保護的な作用を発揮するらしいことがわかりました。
研究者らはさらに、37名のALS患者について、便の遺伝子解析を行うことで腸内細菌叢を調べ、29名の健常者と比較しました。その結果、患者群と健常群とで腸内細菌叢の構成が異なることがわかりました。ALS患者においてはニコチンアミドを産生する腸内細菌が少ないことがわかりました。
以上が昨年のNatureでの報告になります。
今回のNature論文(文献2)では家族性ALSにおいて最も頻度が高い(家族性ALSの30-40%程度を占めるといわれている)C9orf72遺伝子に関連した報告です。
家族性ALSにおけるC9orf72遺伝子変異とは、第1イントロン領域のGGGGCCの6塩基繰り返し配列が過剰伸長し、この領域由来のリピート関連非ATG依存性翻訳(RAN翻訳:開始コドンを介さない非定型的な翻訳形式)によるジペプチド繰り返し転写産物(理屈では5種類のジペプチド繰り返し配列蛋白質:poly-グリシン-プロリン(GP)、poly-グリシンーアラニン(GA)、poly-グリシン-アルギニン(GR)、poly-プロリンーアルギニン(PR)、poly-プロリンーアラニン(PA))が生じるものです。
これらのうち特にpoly-GR,poly-PRの細胞毒性が注目されています。
TDP-43蛋白症の病理を呈することは他のALSと共通になります。
ハーバード大学のBurberryらは、C9orf72遺伝子を改変し、C9orf72変異ALSモデルマウスを作成しました。
これらモデルマウスでは免疫系の過剰応答がみられ、脳内炎症の亢進と運動機能の低下、生存期間の短縮などがみられました。
一方で、Broad Instituteでの全く同じ遺伝子変異を有するモデルマウスにおいては、生存期間の延長など正反対の結果が報告されており、環境要因が生存期間に影響することを示唆する結果が得られました。
環境要因が何かを調べるため、ハーバードの研究室とBroad Instituteの研究室との細菌やウイルスの環境の違いが調べられました。その結果、murine notovirusというウイルスと、Pasteurella pneumotropica, Tritrichomonas muris, Helicobacterと呼ばれる細菌がハーバードの研究室で多く存在することがわかりました。
ハーバードの研究室のモデルマウスに広域スペクトラムの抗菌薬を投与し、細菌を除去するか、もしくはBroad Instituteのモデルマウスより採取した糞便移植を行ったところ、ハーバードのモデルマウスの炎症反応が減弱しました。
研究者らは、細菌がどのように炎症をもたらすのかを調べるため、腸内細菌と共にマクロファージを単離しました。
その結果、ハーバードのマウスより採取され、腸内細菌と共に培養されたマクロファージは、Broad Instituteのマウスより採取された腸内細菌よりも、有意に多くの炎症促進性物質を放出することがわかりました。
以上の結果は、C9orf72蛋白質機能が低下すると、環境、特に腸内細菌叢が自己免疫、神経炎症、運動障害などの修飾因子となりうることを示唆するものといえます。
この結果からわかるのは、もし環境的に脆弱な一部の人々がいるとすると、腸内細菌の力もバカにならない可能性があるということでしょうか。
2019年のCell誌に掲載されたのは、自閉スペクトラム症患者由来の腸内細菌叢を無菌マウスに移植したところ、健常者からの腸内細菌叢を移植したマウスと比較してASD様行動を多く示したという報告になります(文献3)
というわけで、ALS(NCT03766321)、パーキンソン病(NCT03876327)などの神経変性疾患のみならず、精神疾患に対しても、糞便移植の臨床試験が実施中ないし予定されている昨今の状況です。
例えば、摂食障害(NCT03928808:第1相)、てんかん( NCT02889627:第2/3相)、双極性うつ病(NCT03279224:第2/3相)、統合失調症のうつ状態(NCT04001439)、自閉症スペクトラム(NCT03426826:第1相、NCT03408886:第2相、NCT03829878:第2相、 NCT04182633:第2相)、アルツハイマー型認知症(NCT03998423:第1相)など各種疾患に対する臨床試験が世界中で動いています。
ここでは詳細に触れませんが、アリゾナ大学で行われた18名の自閉症に対する糞便移植の第1相試験の長期経過については驚くべき結果が報告されています(文献4)。オープン試験なので本当かどうかは全くわかりませんが。果たして無作為割付二重盲検試験の結果はどうでるでしょうか?引用文献
1)Eran Blacher et al., Nature volume 572, pages 474–480(2019)
2)Burberry, A., Wells, M.F., Limone, F. et al. C9orf72 suppresses systemic and neural inflammation induced by gut bacteria. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2288-7
3)Cell. 2019 May 30;177(6):1600-1618.e17.
4)Sci Rep . 2019 Apr 9;9(1):5821