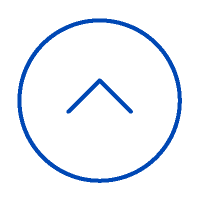-
COVID-19医療従事者のメンタルヘルスへの影響(予備的な結果)
アブストラクトだけみて、重要な論文だと思い、以下の前文を書いてから翻訳してみましたが、論文の問題点が一部みつかって、尻すぼみになってしまいました。しかしながら重要なメッセージは含まれていますので、予備的な結果として残しておきます。
中国湖北省でCOVID-19診療に従事した医療関係者のメンタルヘルスに関する論文が4月29日にAmerican Journal of Psychiatry誌のLetter to the Editorにacceptされ公表されました。COVID-19パンデミックが医療従事者のメンタルヘルスにどのような影響を与えたのか、メンタルヘルスが病的といえる水準にどの程度の割合の医療従事者が至ったのかがわかります。
この報告をみてわかることは、COVID-19診療に従事するだけでも、これほどの精神的影響がありうることであるのに、さらにそのうえ、一部報道でみられたようなCOVID-19医療従事者へ差別的態度が向けられるということは、第一線で診療に従事し、心身ともに疲弊する医療従事者をさらに精神的に追い込む行為であり、社会的に許されることではないということです。以下その概略となります
調査対象となったのは、COVID-19疑い症例ないし確定症例を収容する感染症指定病院に勤務する医療従事者で、オンラインで調査が行われました。
湖北省の感染症指定病院に勤務する2316名の看護師、医師が調査に応じました。
このうち直接COVID-19患者の治療やケアを担当する最前線の医療従事者は885名、その他の医療従事者は1431名でした。
調査が行われたのは2020年1月29日から2月11日(中国では1月29日時点で1日当たりの国内感染者数は1000名を超え、ロックダウンは1月23日から開始されていました)
主要評価項目は、9-item Patient Health Questionnaire[PHQ-9]が6点以上で有意なうつ症状有り、7-item Generalized Anxiety Disorder(GAD-7)で6点以上を有意な不安症状有り、7-item Insomnia Severity Index[ISI]で9点以上を有意な不眠症状有り、22-item Impact of Event Scale-Revised[IES-R]で10点以上を有意なストレス症状有りとされました。
(コメント:感度、特異度の観点から、PHQ-9は10点以上、GAD-7は10点以上、ISIは10点以上を臨床的に有意とする場合が多いので、PHQ-9とGAD-7については拾い上げすぎている感があります。実際にネットで閲覧可能なPHQ-9などをみていただけるとわかりますが。この論文のカットオフ値を適応した場合、必ずしも臨床的に病的なレベルとはいえそうにないことがすぐにわかると思います。なぜこのカットオフ値を用いたのか不明ですし、論文中に異なるカットオフ値を適応した場合の割合なども記載されていればよかったのですが、残念ながらそのようなデータもなく、この報告の数値だけが独り歩きしないことを願います)この論文のカットオフ値を用いた場合、うつ症状を有した割合は全体の46.9%、不安症状は全体の41.1%、不眠は全体の32%、ストレスは全体の69.1%との結果になりました。
最前線の医療従事者はこれらの数値よりも有意に高かった(具体的な数値の記載はありませんでした)とのことです。
一方で、医療従事者の中で専門的なサポートが得られたのは19.2%のみでした。
心理的なサポートを受けることができた医療従事者は、有意に不安、うつ、不眠、ストレスがカットオフ値を超える割合が少なかったということです。
さらに。41.5%の回答者が心理専門職によるサポートや支援を求めており、64.9%の回答者がメンタルヘルスサービスの利用について興味を示したとのことです。(コメント:このデータは重要な結果と思われます。実際に日本の医療現場でも同じようなことが言えるのではないでしょうか)論文の最後では2003年のSARSアウトブレイクの際の出来事にも触れてあり、アウトブレイク後1年以上を経過してもなお、心理的苦痛を訴えた医療従事者が存在していたことが報告されており、長期的視野に立った心理的サポートの重要性が説かれています。
以上となりますが、ごく短期間で出版された報告なため、データが少ないこと(回答者の年齢や性別、有効回答率などの基礎的なデータもない)と、なぜかカットオフ値が標準的ではないことが悔やまれます。
今後日本でも同様の調査、報告が行われ、実際の現場での介入がなされることが期待されます(大学などから遠隔システムでの協力要請があれば、協力したいと思います)
引用文献
Lin K, Yang BX, Luo D, et al: The Mental Health Effects of COVID-19 on Health Care Providers in China
Am J Psychiatry | Letter to the Editor
Accepted 29 April 2020. DOI: 10.1176/appi.ajp.2020.20040374 -
再始動
印象的な出来事があったので、書き留めておこうと思います。
ALS界隈では有名なNeuralstem社というベンチャー企業がありました。2015年当時、ALS当事者の間ではNeuralstem社か、Brainstorm社か、というほど名の知れたベンチャー企業でした。
これらの2つのベンチャー企業はALSに対する再生医療、幹細胞移植における先進的な取り組みで知られていました。
再生医療というとなんだかぼんやりしたイメージですが、wikipediaによると「人体の組織が欠損した場合に体が持っている自己修復力を上手く引き出して、その機能を回復させる医学分野」だそうです。
ALSでは幹細胞移植がこれにあたります。
いちはやくALSに対する実用的な幹細胞移植の臨床試験を開始したのがNeuralstem社とBrainstorm社でした。
ひとえに幹細胞移植といっても、様々なタイプがあります。
臨床試験で報告されているもので一番多いのは中胚葉組織由来の幹細胞です。
中胚葉由来の組織としては、血液、脂肪組織などがあり、骨髄より採取された間葉系幹細胞や脂肪組織由来の間葉系幹細胞などがALSに対する臨床試験に用いられています。
この中胚葉由来の間葉系幹細胞というのが曲者で、てっきり中胚葉由来なので、外胚葉系の神経細胞やグリア(グリア系細胞の中で唯一ミクログリアのみが中胚葉由来ですが)細胞には分化できないだろう。と思っていたら、なんとそんなことはない、というのが現在の見解のようです。
島根大学脳神経内科の長井教授が報告1)されたように、神経栄養因子を分泌するようにもできるし、なんと神経系細胞にも分化できるようです2)。
実際に移植した生体内で目標とする細胞に分化してくれるかどうかはまた別の問題ですが、驚きの多能性を有しているということのようです。
このような中胚葉由来の間葉系幹細胞を用いることの大きなメリットは自家移植が可能なことです。
自身の組織から幹細胞を採取し、それを治療的に用いることができ、同種移植のように免疫抑制剤は必要ではありません。
Brainstorm社のNurOwn細胞はこの方法を用いており、患者自身の骨髄より採取した幹細胞をマル秘の特許技術により神経栄養因子を分泌するように分化誘導し移植する方法になります。
一方で、外胚葉由来の幹細胞を移植する方法もあります。
自身の神経組織から神経幹細胞を採取することは実用的ではありませんので、胎児由来の神経幹細胞を使用する方法がしばしば用いられています(倫理的問題はより大きなものとなりますが)。
また同種移植になるため移植後に免疫抑制剤の投与を必要とします。
Neuralstem社のNSI-566がこれにあたります。NSI-566についてはその安全性もやや気になるところです。
胎児由来神経幹細胞移植は腫瘍化するリスクも報告されています3)
移植の際の投与経路も様々です。静注、くも膜下腔内投与、脊髄内投与などがあります。
このうち静注については注意が必要です。2019年には脊髄損傷に対して自家骨髄幹細胞移植(静注)である、間葉系幹細胞のステミラック注が条件付承認されましたが、これについては批判的な意見もあり、Nature誌でも痛烈に批判されましたし4)、島根大学の松崎教授が解説5)されたように、動物実験では静注された間葉系幹細胞は、新鮮なものはまだよくても、培養を行ったものは、大半が肺の毛細血管にひっかかり、遊走能を失い、ターゲットとする組織には到達しなかったという問題点もあります。
現在ALSに対しては、Mayoクリニックが自家脂肪組織由来間葉系幹細胞移植の臨床試験を行っていますが、これはきちんと投与経路がくも膜下腔内投与となっています。
くも膜下腔内投与は、カテーテルをくも膜下腔に挿入し(ここがやや侵襲的ではありますが)、直接くも膜下腔内に幹細胞を移植する方法になります。
現在第3相試験まで進んでいるBrainstorm社のNurOwn細胞はこの投与経路となります。
一方で脊髄内投与は最も侵襲性の高い治療手技となります。
患者は手術室で椎弓切除術を受け、脊髄を目視下とし、脊髄実質に直接幹細胞を注入する方法になります。この方法をとるのがNeuralstem社のNSI-566となります。
Brainstorm社もNeuralstem社も、2010年頃からALSに対する幹細胞移植の第1相試験を開始しています。
Brainstorm社はイスラエル Hadassah Medical Organizationにて2010年1月から第1相試験を開始(NCT01051882)し、Neuralstem社は2011年5月からEmory大学にて第1相試験(NCT01348451)を開始しました。第1相試験での安全性確認後、Brainstorm社は2013年12月に第2相試験を開始しました(NCT02017912)。
この第2相試験の結果が論文としてpublishされたのは、去年12月であり、ごく最近のことです6)
結果の概要ですが、この第2相試験では、48名のALS患者がエントリーし、36名がNurOwn細胞を投与(くも膜下腔内および筋肉内に単回投与)され、12名がプラセボを投与されました。
患者は投与前3ヶ月間および投与後6ヶ月間症状経過観察されました。主要評価項目であるALSFRS-Rの変化率は治療前後でNurOwn投与群とプラセボ群とで有意差を認めませんでした。
しかしながらALSFRS-Rの変化量が少なくとも1.5点以上改善した群を反応群と定義すると、治療4週後の反応率はNurOwn投与群では47%でプラセボ群では9%であり有意差を認めました。
また治療前のALSFRS-Rの変化量が2点/月以上の急速進行群においては、4週後のNurOwn投与群の反応率は80%に対してプラセボでは0%、12週後の反応率はNurOwn群では53%、プラセボ群では0%といずれも有意差を認めました。
治療後の時間経過と共に反応率が低下していることについて、追加投与の必要性を示唆するものかもしれないと考察されています。
また髄液中MCP-1(monocyte chemoattractant protein-1)濃度(免疫細胞浸潤と神経炎症の指標)については、NurOwn投与後に有意な減少がみられました。
プラセボ群では投与前後での有意差はありませんでした。このことはMCP-1がALSのバイオマーカーとなりうる可能性を示唆するものと考察されました。
この結果を受けて、FDAはNurOwn細胞の第3相試験の実施を承認しました。
このように、主要評価項目において有意な結果が得られず、副次的な評価項目のみで有意差が得られても第3相試験が実施されることはしばしばみられることです(そして残念ながら多くが第3相試験でnegativeとなる)。
現在、NurOwn細胞については、200名のALS患者を対象とした第3相試験が実施中(NCT03280056)であり、2020年中に結果が判明するものと期待されています。
もし有効性が確認されれば大きなニュースになることと思われます。
Brainstorm社のNurOwn細胞については、第1相試験の開始から足掛け10年かかっていますが、比較的順調に進捗している印象があります。
一方で、Neuralstem社のNSI-566はどうでしょうか。
第1相試験で安全性が確認されたのち、第2相試験の実施まではスムーズでした。
2012年12月に第2相試験(NCT01730716)が開始されています。
結果が査読付き論文にpublishされたのは2016年でしたので、NurOwnよりも早く公表されたことになります7)。
この第2相試験は、オープン試験であり、15名のALS患者が対象となりました。
結果の概略ですが、発症2年以内の患者がエントリーされ、頸髄のC3からC5の間の領域に両側性のNSI-566細胞の単回移植を受けました。また最後の3名では腰髄領域にも移植を受けました。
主要評価項目は忍容可能な最大用量を調べること(安全性の評価)でした。
移植後9ヶ月間の経過観察期間において、最も高頻度に報告された副作用は、手術に伴う一過性の疼痛と、併用された免疫抑制剤(同種移植のため、免疫抑制剤が必要)に起因したものでした。
2名では重大な合併症を併発しました。1名では脊髄腫脹がみられ、疼痛と部分的な麻痺が生じました。
またもう1名では脊髄損傷に起因した疼痛が出現しました。
副次的評価項目である、病態進行の程度については、過去の臨床試験のプラセボ群の臨床経過(historical placebo)と比較して、有意な進行遅延は認めませんでした。しかし、被検者が少ないため、有効性に関する結論を出すのは困難とのことでした。
2016年にこの報告が出てから、Neuralstem社の動向がぱったりと途絶えてしまいました。一時はもう開発を諦めてしまったのかと思っていました。
第3相試験の実施には数十から数百億円程度かかると言われており、ベンチャー企業にとっては大変な負担となります。
うまく立ち回ると途中で巨大な製薬会社に買収されたり、提携するなどして資金面での問題があまりなくなる場合もあるのですが、Neuralstem社については、そのようなニュースもなく、数年間新たな動きもないため、最近では忘れかけられていました。
しかし、2019年11月、復活ののろしがあがります。なんと2019年11月にNeuralstem社はSeneca biopharma社と社名を変更し、2020年3月にはNSI-566の第3相試験の実施に向けて、FDAと協議したとのpress releaseが出されました。名前がかわった理由はよくわかりません。新たな資本が注入されたとかのニュースも見当たりません。
第3相試験の実施にあたっては、まず製薬会社はIND(Investigational New Drug Exemption:新薬臨床試験開始届)をFDAに提出し、審査に合格する必要があります。そのINDを提出するための準備としての協議をFDAと行ったそうです。
名前が変わった理由ですが、Seneca社のpress releaseによれば、「今回の社名変更は、これまでの神経疾患関連の研究に重点を置いていた組織から、有望な新科学を発見し、バイオ医薬品のパイプラインを開発し、それらの製品を商業化することに焦点を当て、同時に株主の皆様に価値を提供することを目的とした新たな哲学を表しています」とCEOが語っています。なんだかよくわからないコメントですが、ベンチャー企業にとっては株主の存在は重要です。社名変更は会社哲学の変更ということでしょうか。
第3相臨床試験の実施はまだまだこれから、というところですが、ALSに対する神経幹細胞移植の臨床試験が再開の動きをみせたことは歓迎すべきことと思います。1)Nagai A. et al. PLoS One. 2007 Dec 5;2(12):e1272.
2)Rosa Hernández et al. Biomol Ther 28(1), 34-44 (2020)
3)PLoS Med. 2009 Feb 17;6(2):e1000029.
4)Nature. 2019 Jan;565(7741):535-536.
5)松崎有未 島根医学 vol.39.2 2019.8 1-6
6)Neurology. 2019 Dec 10;93(24):e2294-e2305
7)Neurology. 2016 Jul 26;87(4):392-400. -
COVID-19パンデミックと精神医療
今回は、COVID-19パンデミックにおいて精神医療ができること、注意すべきことなどについて、おそらく現段階でアクセス可能な無料記事が比較的充実していると思われる、The Journal of Clinical PsychiatryのCommentaryより、重要と思われる情報を抜粋し、備忘録も兼ねてまとめておきたいと思います。
まず最初は、イタリア シエナ大学医学部のDr.Andrea Fagloliniらによる報告です1)。
シエナ大学は中央イタリア、ピサの斜塔などで有名なトスカーナ州に位置しています。
トスカーナ州の州都はフィレンツェです。
人口374万人強(2011年)のトスカーナ州に、4月15日現在で7666名(うち死亡556名)のCOVID-19陽性患者が確認されています。
人口比で島根県に置き換えると千数百名の患者が発生した状況に該当しますので、収容可能なベット数をはるかに超える患者数となっています(島根県でも同様の状況を早めに想定して、もしもの場合のためにホテルなど収容施設を県で確保してもらっておいたほうがいいのではないでしょうか)。
また非常事態において全従業員にマスクと同様にゴーグルも装着するようにしたことが記載されており、参考にしようと思います。
ちなみにイタリアでは4月15日現在1日あたり2500名を超える新規感染患者が報告され、500名以上の死者数が報告されていますが、新規患者数はピーク時の半分以下の数値となっており、緩やかにではありますが減少しているようです。
Fagloliniらによる報告では地域の中核機能を担う総合病院精神科において、何が起き、何をしてきたのか、現在までの経過がレポートされています。その概略は以下のようになります。Dr.Andrea Fagloliniらによる報告
”COVID-19 Diary From a Psychiatry Department in Italy”1月31日にローマで最初の3名の患者が発生した時には、まだシエナからは遠い場所での出来事と感じていました。
しかし2月中旬以降ロンバルディア州において急速に感染者数の増加が確認され始めてからは、状況が急変しました。3月22日までで4826名の医療従事者が感染しており、感染者数全体の9%が医療従事者でした。
これほどの状況の深刻さ、急速な感染拡大についてはほとんど想像していた人はいませんでした。
精神科についても、対応を速やかに行い、90%以上の外来診療が遠隔診療(ほとんどが電話)に切り替えられました。通常の外来診療と同じだけの時間を電話診療に費やしました。
WhatsAppやFaceTimeなどのアプリを使用可能な患者については、これらアプリを使用したビデオ診療も十分に機能し、電話よりも効果的でした。
一部の重症患者のみ、対面での診療が行われました。
マスクは乏しく、ゴーグルも無かったため、素材や滅菌の方法も含めて自作のマスク作成法についての情報を共有し(安全性は低下するものの、何もしないよりもよいだろうということで)、正規のマスクやゴーグルが入手可能になるまで、全従業員に少なくとも眼鏡ないし眼鏡がない場合にはサングラス、および自作のマスクを着用するように推奨しました。
会議については、すべてビデオ通話に変更され、外来についても椅子の間隔を離すなどして、人が話している場合は少なくとも2m、くしゃみや咳をしている場合は少なくとも3m、呼吸をしているだけの場合は少なくとも1.5mの距離がとれるようにされました。
精神科の入院患者も制限され、必要最低限、絶対必要な入院に限定されました。
大学病院は、救急部とすべての入院病棟を2つの主要なエリアに分割することを決定しました。COVIDエリアとNon-COVIDエリアで、病院内の異なる別々のエリアに配置されました。
精神科はnon-COVIDエリアでしたが、COVID陽性の精神疾患患者が入院した場合には、COVIDエリアに入院し、感染予防と管理のために職員を再教育し、リエゾンで対処しました。
北イタリアで、トスカーナ州よりもさらに感染状況が深刻な地域では、COVID陽性の精神疾患患者を、精神病棟に入院させる場合もあるようです。そのような患者は通常、身体症状よりも精神症状がより重篤なケースになります。
一般的には、多くのCOVID陽性の精神疾患患者については、遠隔医療により自宅での精神疾患治療を行っています。
入院患者でCOVID陽性の場合には、COVIDエリアに入院していますが、精神症状が重篤で、暴力的行動が顕著な場合には、COVIDエリアに保護室を設けて、そこで処遇しています。患者数が増加しているため、COVIDエリアの保護室が利用できない状況に備え、精神科病棟内の比較的大きな部屋をCOVID陽性患者のための保護室として使用できるように準備をしています。
精神科以外の部署の同僚たちは並外れた業務量と心理的負荷に直面しています。そのうち何人かは不安や疲弊状態、無力感に陥り、精神的な健康が損なわれています。この状況を打開するため、私たちは個別の心理的サポートを提供するプログラムを開始しました。
特にCOVIDエリアで勤務する医療従事者を対象に、業務のシフト終了時にWhatsAppで提供されるビデオセッションを通じて、心理的サポートプログラムが提供されています。
一部の同僚は不眠や不安を発症し、時にそれが警告症状やパニックに発展する場合もあり、さらに退職という選択肢をとる人もいました。そのような心理状態は、より合理的でない行動(マスク、ゴーグル、ガウンを着用しているときに注意を払わないなど)に結びついたり、ストレスにより生体の防御能を低下させうることを考えると、大きな苦痛であり危険でもあります。
このプログラムは、同僚たちがストレスを管理し、できるだけ多くの心理社会的健康を取り戻すことを支援する目的で行われています。
また、今後、より多くの医療従事者を支援することを目的としたグループプログラムを開始しようとしています。これは、コミュニケーションを促進し、話し、経験を共有し、仕事の終わりに恐怖や希望を表現することを目的としたものです。
病院で働く人たちは、マスクと防護服を着用したまま長時間病院内で過ごし、時には他人(同僚を含む)を感染源の可能性があると見なしていることもあります。
仕事が終わったら、イタリア国民全員が自宅で過ごすことが義務づけられているため、家に帰る以外の選択肢はありません。
そのため、仕事の終わりには、自宅にいながら、インターネットを介して、グループで社会的な接触を提供することの利益があると考えられます。遠隔通話により、経験を共有し、お互いを慰め合う場を提供することは、特に家に誰もいない人たちにとって有益であると考えています。
以上Dr.Andrea Fagloliniらによる報告でした
危機的状況において、他の部署の同僚を心理的に支援するための機能としての精神科医療の必要性がわかります。続いて、ワシントン大学医学部のDr. Ginger E. Nicolらによる、COVID-19パンデミックと精神医療についての総論的な解説2)になります。いくつかのポイントをかいつまんで引用します
Dr.Ginger E. Nocolらによる解説です。
"What Were You Before the War?"
Repurposing Psychiatry During the COVID-19 Pandemic.パンデミックの心理的影響
不確実な状況や恐怖に長期間暴露されることは、メンタルヘルスに永続的な負の影響を及ぼしえます。
2013年にPublic Health Preparedness誌に”Posttraumatic Stress Disorder in Parents and Youth After Health-Related Disasters”との論文が掲載されました3)
驚くべきことに、この論文のintroductionに現在の状況が予測されています。”専門家は来世紀中には、1800万人から1億人が罹患し、89000人から20万7千人が死亡するパンデミックが起きることを予測している”とあります(現段階での死者は世界中で13万人以上とされています)。来世紀どころか論文がでてから7年後にパンデミックが生じてしまいました。
パンデミックの災害としての特徴は、他の多くの自然災害と異なり(被災者が集合する)、被災者の分離、隔離、検疫を要する点です。そのため家族は引き離され、特に子供に対する影響に注意する必要があります。
カナダでのSARS流行後のPTSDの発生率は自然災害やテロと同程度(28.9%)であることが報告されています。
2009年のH1N1インフルエンザ流行における流行地域ないし2003年のSARS流行地域に在住していた398名の保護者へのアンケート調査(PCL-Cを用いて親のトラウマを測定し、PTSD-RIを用いて、親の報告により子供のトラウマ症状を測定した)により、隔離などを経験した親の25%がPTSDのリスクがあるとされ(非隔離経験者は7%)、隔離を経験した子の30%がPTSDリスクがあるとされました(非隔離では1.1%)。
このことはパンデミックに伴う隔離によるストレスによる親と子供に与える長期的影響を避けるため、コミュニケーションを促進するような迅速な介入が必要であることを示唆する結果といえます。研究的視点の重要性
同時に重要な着眼点として、パンデミックの脅威とその精神衛生への影響を後世のために記録する義務があります。
具体的には精神疾患を有する人々はどのように対処しているのか?孤立、不確実性、必要なケアへのアクセスの欠如に対して、どのような反応を示しているのか?どのような戦略が機能しているのか?などの観点からの研究に取り組む必要があります。
治療薬の探索と向精神薬
最近のCOVID-19関連基礎研究では、69種類のFDA承認薬が、治療薬候補として報告されており5)、そのうちのいくつかは向精神薬に属します。
例えば、COVID-19に関連した肺および心臓の損傷はサイトカインストーム6)に起因していると言われており、免疫反応を最小限に抑える治療法が探索されています。
抗うつ薬の一部は、シグマ-1受容体(S1R)アゴニストとして作用し、S1Rの活性化は細胞ストレスを緩和し(小胞体ストレスセンサーであるIRE1の活性を阻害することで)、サイトカインの発現を抑制するといわれています。S1Rアゴニストは齧歯類では心保護作用があり、炎症反応を抑制し、敗血症動物モデルでは生存率を高めています。(S1Rアゴニストとしてはフルボキサミンやアミトリプチリンなどでしょうが、私個人的には、細胞内レセプターであるS1Rと抗うつ薬との関連性において、現実的な治療的有効性についてはとても懐疑的な立場です)さらに、マウントサイナイ医科大学のDr. Joseph F. Goldbergは、”Psychiatry's Niche Role in the COVID-19 Pandemic”と題し4)、精神科医の役割について解説しています
Psychiatry's Niche Role in the COVID-19 Pandemic
アメリカでは多くの州や施設が、地域社会でパンデミックに関連した苦痛を感じている人のために、電話により精神保健の専門家にボランティアでサービスを提供するよう求めています。
カウンセリングサービスを提供する精神科医は、純粋なカウンセリング(主に能動的で共感的な傾聴によって定義される)とは別に、以下のような点に注意する必要があります。
(1)安全性のリスクと危険因子の評価(例えば、独居、経済的問題などの存在など)。ただし遠隔診療においては、アルコールやベンゾジアゼピンなどの使用障害についてのアセスメントが困難である問題がある
(2)病的水準の精神病理と非病理的レベルの苦痛の鑑別を行うこと。過去の病歴から現在再発し、より正式な介入を必要としている可能性があるかどうかの確認を行う。正常な不安状態(了解可能な範疇で無力化していない状態)と病的な不安状態(麻痺、非生産的な状態、無力化した状態など)を鑑別する。大きな人生の激変の後の「うつ病」については、悔しさやフラストレーションなどの情動変化を伴う場合よりも、無気力や絶望、失感情を伴う場合は、病的水準が高い可能性に注意する必要がある。
(3)外傷的出来事への暴露が将来の心的外傷後ストレス障害の素因となる可能性が高いかどうかを判断する。
(4)不眠症や不安感など、あまり病的ではない苦痛を伴う症状に対して、短期的な薬物療法が適切であるかどうかを判断する。クライシスワークの基本的な治療の焦点は、
(a) 電話での支援、教育、スキルの提供を行う。適切な場合には的を絞った薬物療法を提供することで、人々の当面の身体的・情緒的苦痛を管理すること。
(b) 目に見える問題により良く対処し、解決するための戦略を考案し、実行することを支援すること
となります。危機による「苦痛」には、一般的に不安、焦燥感、不眠、先入観、悲しみ、健康の喪失の恐れ、および孤立、孤独感が伴います。
身体的苦痛と自律神経亢進を軽減するための行動戦略には、リラクゼーションのテクニック、瞑想とマインドフルネス、運動、ヨガ、スピリチュアルな活動、(仮想的な)グループベースの支援などがあります。
具体的な問題解決の努力には、適応的な対処スキルを向上させ、日々の生活構造を維持すること、社会的な距離が離れている中で社会的孤立を最小限に抑えるためにインターネットの創造的な利用法を見つけること、育児、家庭教育、財政管理について戦略を練ること、不適応な対処スキル(例えば、悪い衝動の制御、物質使用や行動依存症、自傷行為、セルフケアの喪失)に対処することが含まれます力動的見地からは、ストレスや恐怖により一部の人において退行が生じ、好訴的となったり、様々な権利の要求を起こしやすくなることに注意が必要です。(未熟な防衛機制が発動しやすくなるということですね。お店で執拗に攻撃的に店員さんにマスクを求めたりする一部の人の心理はこれでしょうか)
最後に第1線で働く同僚の健康に対するリエゾン活動。および精神科医自身のセルフケアの重要性について触れ締めくくられています。
この論文でも触れてありましたが、隔離下においてはアルコールに関する問題には注意したいものです。しかし遠隔医療では、この問題への介入がより困難となることもまた課題です。
1)Fagiolini A et al. J Clin Psychiatry. 2020 Mar 31;81(3). pii: 20com13357.
2)Nicol GE et al. J Clin Psychiatry. 2020 Apr 7;81(3). pii: 20com13373
3)Sprang G et al. Disaster Med Public Health Prep. 2013;7(1):105-110
4)Goldberg JF. J Clin Psychiatry. 2020 Apr 7;81(3). pii: 20com13363
5) Gordon DE et al. A SARS-CoV-2-human protein-protein interaction map reveals drug targets and potential drug-repurposing. bioRxiv website. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.002386v3. March 27, 2020.
6). Mehta P, et al; Lancet. 2020;395(10229):1033–1034. -
新型コロナウイルス感染症に関した話題
4月1日にアメリカ睡眠医学会のWebinarが行われました。
この時すでにアメリカでは新型コロナウイルスが猛威を振るっており、社会的不安が高まる状況の中で、睡眠専門家がどのようにセルフケアすべきかについて、メリーランド大学の睡眠生理学者のEmerson Wickwire博士が講演しました。Zoomで行われ、アメリカ東部時間の正午から開催で、日本時間の午前4時開始だったので、私は待ち構えていたのですが、結局寝落ちしてしまいました。しかしその後ありがたいことにYoutubeで無料公開されたので、誰でも見ることができます。
興味がある方は”Self-Care for Sleep Professionals During Difficult Times”で検索してみてください。内容は、いかに不安と向き合い、不安を減弱し、睡眠に入りやすくするか、そして終息後に向けて、というものでした。
内容の多くは第3世代認知行動療法がベースにするマインドフルネスの概念などから引用されたもので、馴染みのある内容でしたが、あらためて聞いてみて、実際にwhat if・・よりもwhat is・・に注目するという辺りは、私自身の最近の入眠困難にも効果があった気がします。CBT-iなど、どんなものか耳学問では知っていても、いざ自分がとなるとなかなか自分に対してはうまくはいかないものです。
内容のアウトラインを以下に書いてみます。緊張からの開放
目を閉じて、自身の身体の緊張している部位を感じます。
次に、ストレスをクールダウンさせるための呼吸を3回行います。腹式呼吸で行い、横隔膜が下がり腹部が膨らむことを意識します。
4秒で息を吸い、8秒で吐く。それも合計3回繰り返します。
これにより緊張から解放されます。心の柔軟性を開放し、不安を減らす
次に心の柔軟性を開放します。心が柔軟性を失うと、慢性的な不安に取りつかれたり、慢性的なうつ状態に陥ったりします。
不安の一部は恐怖から生じます。
恐怖は不確実性が存在するとより強まります。
不確実性を無くすことから始めましょう。
まずは不安に思うことを書き出します。
次に自分がどうしたいかを明確にします。
さらにさまざまな代替案を考えます。ブレインストーミングの手法を用います。より自分自身が不安にならない方法を考えます。
たとえば、収入を失うかもしれないという不安であれば、まずファイナンシャルプランナーと話し、ついで公的扶助について調べ、さらに上司に悩みを打ち明けるなど。
ついで考え出した案について、賛否両面から評価します。最後に行動します。
不安を防ぐには、ネガティブな考えに陥る材料を遮断し。不確実な情報源からの情報を遮断し、信頼できる情報源のみから情報を得ることが重要です。ワイドショーやtwitterなども、不要な不安を煽られるならば遮断しましょう。
覚醒を制御する
覚醒を制御するためには、儀式的なプロセスを構築することが望ましいです。
例えば、仕事が終わりメールを遮断することが最初の段階となります、次いでTVを見るなどするリラックスする時間帯をつくり、TVを切ることで次の段階に進みます。睡眠前段階では、歯磨きなどを行います。歯磨きを終えることで次の段階に進み睡眠に入るようにします。
このように一連の流れを儀式化、習慣化することにより、覚醒を制御しやすくなります。
ポジティブな感情を増やす
認知行動療法の基盤でもありますが、感情と行動と思考は相互に影響しあっており、どれかを変えることで、お互いを変化させることができるとの仮説があります。
どんな小さなポジティブな感情であっても、行動や思考を変化させうるとの考えに基づきます。逆にちょっとした行動や思考がポジティブな感情を産み出しうることとなります。
最初のステップは、現実は何かに集中することです。もし・・だったらではなく、現実は何かに集中します。もし・・だったらは多くの不安を産み出します。例えばもし感染が広がったらどうしようとか、もし彼氏が浮気していたらどうしようとか、そういう考えではなく、現実のこと、現実に起きたことのみに集中します。
30秒だけ、視覚以外の感覚を用いて、何が聞こえるか、どんなにおいか、どんな味か、どんな感触か、を描写します。
これにより、ポジティブな感情への感性を高めます。
続いて、3つから5つの、ちょっとした感謝できる事実の出来事を思い浮かべます。
例えば、朝がとても静かな時間だったとか、子供と一緒に葉の上の水滴探しをしたとか、家族と歩くときに日差しを感じられたとか、誰かと一緒に過ごせたこととか、ちょっとした日常の中の感謝できることをでいいのです。寝付くときに、頭の中をぐるぐると不安が渦巻く状況においても、この手法は適応できます。頭の中を、もしも・・ではなく、現実の出来事で埋めていきましょう。そうするといつの間にか眠りに入るでしょう。
他にもいくつかのtipsがありましたが、専門家が話すとなんとも説得力のあるお話でした。明日にでも緊急事態宣言が出されようかという状況の中、少しでも皆さんが心身ともにご健康であることを願います。
最後に、私自身が参考にしているサイトをご紹介します。
もちろん行政機関からの情報は重要ですが、これからどうなるのか、どのように注意すべきかという科学的な根拠と指針が示されているという点で、参考になりました。モデルに基づいた数式からの解析ですが、多くの専門家が信頼できる情報源として認めるところと思います。(基本再生産数3.0を仮定しているので、実際よりも多く見積もられているかもしれません)
佐藤彰洋教授による情報です。
https://www.fttsus.jp/covinfo/considerable-discussion/
ここから得られる情報で重要な点は、仮に基本再生産数が3.0であり、このモデルが妥当であれば、直接接触の機会を8%まで減らしても、その後ダラダラと感染者数が横ばいな状況が続いていくということです。
人と人との接触機会を減らすことに躊躇してはならないというメッセージが伝わります。 -
これはすごい
専門外ではありますが、当事者の方と御縁があったこともあり、最近5年間くらいずっとALSの臨床試験などの動向を追いかけています。
ここ最近、印象的な話題があったのでコメントします。
夢のある話題でもありますので、興味がある方はお読みくださいこのブログの記事を書くきっかけになった論文は、こちらの論文(Mol Ther. 2020 Jan 14. pii: S1525-0016(20)30011-3)ですが、この論文について触れる前に、遺伝子編集技術の進歩を簡単に振り返ります(大雑把なことしかわかりませんが)。
CRISPR-Cas9と呼ばれる遺伝子編集技術は2012年に報告され、遺伝子配列の任意の場所を削除、置換、挿入することのできる技術として注目されました。
当初報告されたCRISPR-Cas9はDNAの二本鎖を両方とも切断するため、その他の部位で予期しない遺伝子変化を生じるリスクがあり、実用性には乏しいとされていました。
その後選択性を高める工夫はいろいろなされましたが、2017年にDNAではなく、RNAをターゲットとする遺伝子編集技術(RNA-targeting Cas9、略してRCas9)が開発されました。2017年8月のCell誌に公表された論文(Ranjan Batra et al., Cell,170(5), P899-912.e10, August 24, 2017)では、RCas9により、ALS患者細胞内(C9orf72遺伝子変異ALSなど)でみられうるマクロサテライト反復伸長とよばれる繰り返し配列を有する異常RNA蓄積の除去に成功したことが報告されました。CRISPR-Cas9システムにおいては、RNAプローブが特定のDNA配列に結合し、Cas9酵素がDNAを切断しますが、RCas9では、RNAをターゲットとし、RNAを切断します。DNAに恒久的な変化をもたらす手法においては、選択性が完全ではない場合に、ターゲットではない部分の遺伝子編集が行われ、危険が生じる可能性がありますが、RNAをターゲットとすることで、効果が可逆性となることから、安全性が高いことが期待できます。
さらにMITの研究者らによりRNAの単一塩基配列の編集が可能となりました(Science. 2017 Nov 24;358(6366):1019-1027)。CRISPRシステムに改変を加えたREPAIR(RNA Editing for Programmable A to I Replacement)とよばれる技術により、正確に選択的なRNA配列のアデノシンをイノシンに置換することが可能となりました。これにより一部のデュシャンヌ型筋ジストロフィーやパーキンソン病などでみられる点変異(グアノシンからアデノシンへの変異)に起因した病態への遺伝子編集による治療が可能となる道が拓けました。
当然、このような遺伝子編集技術を、治療的にALSに対して応用しようということになります。
遺伝子変異が明らかな家族性ALS(ALS全体の10%程度と言われていますが)、その家族性ALSの中の20%程度を占めるといわれるSOD1遺伝子変異ALSなどがターゲットとなります。このSOD1変異ALSにおいては、変異したSOD1蛋白質が折り畳み異常を呈し、細胞質内で凝集体を形成することが主要な病態と考えられています。そうなると当然この異常SOD1蛋白質の発現をなんとか阻害しようという治療戦略になり、そのために例えば変異SOD1遺伝子由来のmRNAの相補的配列を有するアンチセンス・オリゴヌクレオチドにより、mRNAからの蛋白質への転写過程を阻害しようとする治療戦略(これについてはBiogen社などが開発中で、すでに第3相試験に到達しています。日本でも2019年から第3相試験への参加者が募集されていました(まだ募集中でしょうか?)。ただし投与経路がクモ膜下腔内投与のため、腰椎穿刺が必要など侵襲性はやや高いものです)や、マイクロRNAを用いて、発現を阻害しようとする治療戦略(アデノ随伴ウイルスベクターを用いた動物実験での成功例が報告されています。これは静注できるので、投与経路は安全です)などの手法が現在精力的に研究されています。
そこに、遺伝子編集技術による治療法開発も参入しています。こちらの論文(Sci Adv. 2017 Dec 20;3(12):eaar3952)にて公表されたように、アデノ随伴ウイルスベクター内にCRISPR-Cas9システムを組み込んで、モデルマウスに投与し、in vivoで遺伝子編集を行い、運動神経細胞内における変異SOD1遺伝子の発現を阻害しうることが示されました。アンチセンス・オリゴヌクレオチドやマイクロRNAを用いる方法と比較して、選択性や効率がより高い点が期待しうるのではないかとのことです。
DNAについてもCRISPR技術の応用により一塩基編集技術が開発されました(Nature. 2016 May 19;533(7603):420-4.)。CBEs(cytidine base editors)とよばれるこの方法は、単一塩基を変化させるものであり、具体的にはシトシン(C)をチミン(T)に変化させるものです。
これをALS治療に応用しようとしたのが、今回の論文(Mol Ther. 2020 Jan 14. pii: S1525-0016(20)30011-3)となります。研究者らは変異SOD1遺伝子の上流部位を終止コドンに変化させるようCBEsに基づくシステムを構築しました。さらにこのシステムをアデノ随伴ウイルスベクターに組み込み、モデルマウスに投与して治療的効果がみられることを報告しました(そこまで劇的な効果ではありませんでしたが)
ここからが空想です。
このような話が例えば癌医療にも将来応用ができれば、患者ごとの癌の遺伝子変異を同定し、その癌の増殖を抑制するようにうまいこと終止コドンに変化させるようなCBEsをエンコードしたアデノ随伴ウイルスベクターを作成し、それを静注すれば癌の治療終了、みたいな、夢のようなまさにPrecision Medicineが実現できるのでは、などと勝手に夢想していました。実際の研究の進展はどうなのでしょうか。実際にはウイルスベクターを用いることによる限界や、効率の問題、副作用の問題、癌細胞の遺伝子変異なんて同一生体内でもとらえきれない程variantが多く、そんなに単純な話でもないのかもしれません。
しかし夢のある話だと思われませんか?専門家の方に一度お話を聞いてみたい気がします。これからの研究の進展に期待です。