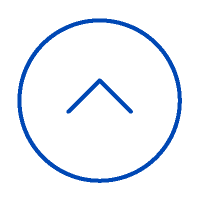-
guanabenzはどうか
・第2相試験は大体100人未満の規模のことが多いし、それで有効性に関する指標について対照群と統計的な有意差が出たからといって、まったく信憑性はないですし(第3相でひっくり返ることも多い)、主要評価項目も有効性ではなくて、副作用とかバイオマーカとかに設定してあることもあって、有効性に関する結果が統計的に有意なものではなくても、第3相試験に進むことはままあるのですが、それでも有効性に関する指標について対照群に対して有意差が出たりすると、期待してしまうものです。
・今回もそのような報告(Brain. 2021 Apr 26;awab167. doi: 10.1093/brain/awab167)にあたるのですが、有意差がでた対照群がプラセボ群ではなく(プラセボ群とは有意差がでていない)、historical cohort(過去の臨床試験のプラセボ群のデータ)なので、手放しに喜べないのですが、目を引いたのは、ALSの中でも特に予後が厳しいとされる球麻痺発症型において、よさげな結果になっていることです。小規模試験の結果なので、有効性に関する結論は出せないところなのですが、本当であってほしいと願うところです。
・この試験で用いられた薬剤はguanabenzであり、α2アドレナリン受容体アゴニスト作用を有する高血圧治療薬です。商品名ワイテンスとして2-4mgの用量で厚労省からも承認されています。なぜALSの臨床試験が行われたかというと、基礎実験の段階でguanabenzが、細胞内において蛋白質の恒常性保持機能に重要な役割を果たしている小胞体ストレス応答において、蛋白質合成速度を調整し、折り畳み異常蛋白質による細胞毒性から細胞を保護するらしいとの報告がなされたことによります(Science. 2011 Apr 1;332(6025):91-4. doi: 10.1126/science.1201396. Epub 2011 Mar 3.)。
・もう少しそのメカニズムについて詳細を述べると、孤発性ALSの病態においては通常は核内に存在しているTDP-43蛋白質がなぜか細胞質に異常局在化し、折り畳み異常を生じ、凝集体を形成するなどして細胞毒性を発揮すると考えられています(たいたい孤発性ALSの95%くらいでTDP-43の細胞質内凝集体が存在するといわれています)。この折り畳み異常を呈した蛋白質が存在すると、小胞体ストレス応答(Unfolded Protein Response:UPR)が発動し、異常蛋白質を除去しようとするメカニズムが働きます。具体的には小胞体膜に何種類か存在するストレスセンサー蛋白質が折り畳み異常蛋白質の存在を探知すると、うち1つ(PERK)が翻訳開始を担う蛋白質であるelF2αをリン酸化し、新たな蛋白質翻訳を抑制します。これにより小胞体への蛋白質流入を抑制します。一方で、リン酸化elF2αはATF4の翻訳を誘導し、折り畳み異常蛋白質を再構成したり、折り畳み異常蛋白質を小胞体から細胞質へと移動させてユビキチンプロテアソーム系による小胞体関連分解を行うことで、蛋白質の品質管理を行います。さらにATF4はelF2αを脱リン酸化する酵素も転写誘導し、これによりelF2αが脱リン酸化し、蛋白質の合成が再開します。一方ATF4はCHOPと呼ばれるアポトーシスに関連する酵素も誘導します。異常な蛋白質が多すぎて、elF2αのリン酸化が持続する場合には、CHOP経路などにより、細胞がアポトーシスを起こすこととなります(Neurobiol Dis. 2014 November ; 0: 317–324)。
・では、guanabenzはどのようにして、小胞体ストレス応答を調節しているのでしょうか。guanabenzは2種類存在するelF2αの脱リン酸化酵素(PPP1R15A-PP1cおよびPPP1R15B-PP1c)のうち、ストレス応答により誘導されるタイプの脱リン酸化酵素(PPP1R15A-PP1c)の機能を阻害し、elF2αの脱リン酸化を抑制することにより、elf2αのリン酸化状態を保持し、そのことにより、新たな蛋白質合成を抑制する一方で、異常蛋白質の修復や分解を促進することで折り畳み異常蛋白質に起因する細胞ストレスから細胞を保護するということのようです。
・永続的なelF2αのリン酸化は新たな蛋白質合成が起こらなくなったり、CHOP経路などのアポトーシス経路が活性化するため細胞にとって有害ですが、2種類存在する脱リン酸化酵素のうちもう1種類の機能が保持されているので、永続的なelF2αのリン酸化は起こらず、問題がないということです(Science. 2015 Apr 10; 348(6231): 239–242.)。ほどよくelF2αのリン酸化状態を保持するということがポイントのようです。
・このように基礎実験では、ALSへの有効性も期待されるguanabenzですが、今回、イタリアで2016年12月から行われた第2相試験の結果が報告されました。
・この試験の参加者は、18歳以上の改訂El Escorial基準でprobableないしdefinite 孤発性ないし家族性ALS患者。発症18カ月未満。SVC 70%以上などとされました。PEG施行例、NIV装着例、気切例、心不全合併例などは除外されました。
・患者はguanabenz16mg+リルゾール100mg(n=51)、guanabenz32mg+リルゾール100mg(n=50)、guanabenz64mg+リルゾール100mg(n=50)、プラセボ+リルゾール100mg(n=49)の4群に無作為割付されました(guanabenzは8mgより開始して3日毎に増量)。guanabenzの用量が高血圧に使用する量よりも随分多いのが気になります。
・試験期間は6か月間で、主要評価項目はALS-MITOS(ALS Milano-Torino Staging)でより高ステージに進行した患者の割合とされました。副次評価項目はALSFRS-Rの変化量、SVCの変化量、死亡ないし気切ないし永続的人工換気までの時間、血清ニューロフィラメント軽鎖濃度などとされました
・対照群としてはプラセボ群の他、ベースラインのBMIや性別、ALSFRS-R、SVCなどをマッチさせた200名のALS患者からなるhistrocal cohortも使用されました。
・副作用が気になるところですが、6か月間での副作用による脱落は、64mg群 30%、32mg群 30%、16mg群 16%、プラセボ群6%で実薬群とプラセボとで有意差を認め、やはり副作用による脱落は多い結果となりました。血圧低下や倦怠感、傾眠、口喝、脱力感などが目立ったようです。特に64mg群では、傾眠や口喝の出現率が60%を超えていました。統合失調症に対するxanomelineの時も、副作用出現率の高さから臨床試験が先に進まなかった経緯があるので、この辺りは心配なところです。・主要評価項目ですが、6か月間でALS-MITOSでより高いステージに進行した割合は、64mg群 25%、32mg群 30%、16mg群 43%、historical cohort 47%、プラセボ群 30%となり、64mg群と32mg群を合わせた結果と、historical cohortを比較すると有意差ありとなりました。プラセボ群と有意差が出ていないのでどうなのかと思いますが、多重比較の補正をしても、historical cohortとの有意差は残りそうです。
・球麻痺発症型については、64mg群および32mg群の18名中、6か月間でALS-MITOSのステージが進行した割合は0%でした(全員がベースラインでステージ0)。一方16mg群では8名中4名(50%)で、プラセボ群では11名中4名(36%)がより高いステージに進行しました(いずれもベースラインではステージ0)。historical cohort群も球麻痺型49名中21名(43%)が6か月間でより高いステージに進行していることから、この結果がもし一般化できるものであれば素晴らしいことだと思います。さらに大規模試験での検証が期待されるところです。
・ただし副作用がかなり多いことから、実用性には問題があるかもしれません。現在、α2受容体刺激作用がなく、より選択的にPPP1R15A-PP1cを阻害する薬剤であるSephin1という物質が同定されているようですので、こちらの方が期待されます。
・小胞体ストレス応答が病態に関与する疾患はかなり多いようですので(金本ら、Journal of Japanese Biochemical Society 90(1): 51-59 (2018)doi:10.14952/SEIKAGAKU.2018.900051)、今後のこの分野での創薬が進み、臨床応用されることが期待されます。
-
久しぶりにみた
・p53というと、学生の頃に細胞内の情報伝達の授業か何かで、癌抑制遺伝子として習って、なんとなくそんな働きをしているんだなあくらいの記憶しか残っておらず、精神科臨床に出てからはまず目にする機会はほぼなかったのですが、久しぶりに目にする機会がありました。
・2021年1月21日のCell誌に公表された論文(文献1)にて、家族性ALS/FTLDの最も高頻度な遺伝子変異であるC9orf72遺伝子変異ALSにおいてこのp53が神経変性に重要な役割を果たしていそうだということが報告されました
・C9orf72遺伝子変異ALSでは、C9orf72遺伝子の第1イントロンにおいて6塩基繰り返し配列の過剰伸長がみられ、過剰伸長遺伝子から開始コドン非依存性のリピート関連翻訳により生成する異常RNAと異常反復配列を有するジペプチド反復蛋白質が細胞障害性を有すると考えられています。
・生成するジペプチド反復蛋白質は5種類(poly-グリシン-プロリン(GP)、poly-グリシンーアラニン(GA)、poly-グリシン-アルギニン(GR)、poly-プロリンーアルギニン(PR)、poly-プロリンーアラニン(PA))が知られています。
・このうち特に、グリシンーアルギニン(GR)およびプロリンーアルギニン(PR)の反復配列を有するジペプチド反復蛋白質が毒性が強いとする報告(文献2)があり、この報告では、ゲノムワイドスクリーニングにより、ジペプチド反復蛋白質が影響を与える遺伝子が探索されました。その結果、核細胞質間輸送に関連する遺伝子が多く抽出され、特に影響の大きなものはtransportin-1と呼ばれる、多くのRNA結合蛋白質の細胞質から核への輸送を担う蛋白質の遺伝子でした。transportin-1の機能がジペプチド反復蛋白質に障害された結果、RNA結合蛋白質の細胞質への蓄積が観察されました。
・さらに別の報告(文献3)ではpoly-GRとpoly-PR蛋白質は核小体に局在化し、核小体の主要な構成要素であるヌクレオホスミンを移動させ、結果的に核小体ストレスの増大と細胞死につながったことが報告されており、核小体機能を障害することも報告されています。
・また文献4では、poly-GRやpoly-PRが、RNAのスプライシングを行うスプライソソームに影響を与えることが報告されました。特にスプライソソームに関連したU2 snRNPとよばれる蛋白質の異常をもたらすことがわかりました。スプライソソームは本来核内で生成されるべきですが、これらジペプチド反復蛋白質の影響により、U2 snRNPが細胞質内に異常局在化し凝集することが報告されました。
・文献5では、Mayoクリニックの研究者らが、蛍光標識したpoly-PRジペプチド反復蛋白質(50回繰り返し)を発現するモデルマウスを開発し、病態への関与を調べました。その結果、ヘテロクロマチンに局在化したpoly-PRジペプチド反復蛋白質がDNAに結合し、HP1α(ヘテロクロマチン蛋白質1α)の液液相転移を阻害し、発現低下をもたらし、ヒストンメチル化異常などをもたらすことがわかりました。核内構造物にも異常をもたらしていることになります。
・文献6では、poly-GRジペプチド反復蛋白質(80回繰り返し)が徐々に蓄積する、poly-GR毒性を誘発しうるモデルマウスが作成されました。その結果、poly-GRは主としてミトコンドリア酵素複合体Vの構成要素であるATP5A1に結合し、そのユビキチン化と分解を促進することがわかりました。
・このように、いろんなところでいろんな悪さをしていそうなpoly-GR、poly-PRですが、今回はスタンフォード大学の研究者らが、神経細胞が変性していく過程において、クロマチンへのアクセス状況の特性と転写プログラムを調べるプラットフォームを開発し(どんなものなのか、詳細はわからないです)、その技術を用いてpoly-PRがどんな悪さをしているかを調べました。
・その結果、なんとpoly-PRは転写因子p53を介した転写プログラムを活性化していることがわかったとのことです。しかもC9orf72遺伝子変異モデルマウスにおいてp53を遺伝子的に除去すると、神経細胞変性が阻害され、生存期間の顕著な延長がみられたとのことです。
・ヒトに応用するとなると、このp53は癌抑制遺伝子なので、これを抑制してしまうと、いろんな不都合が生じてしまいそうですが、思いがけないところでp53が出てきて、懐かしく感じました。c9orf72遺伝子変異ALSについては、2011年に発見され、まだ10年しかたっていないので、新しい技術を用いて研究される度に新しい発見が報告される状況です。まだまだいろいろな興味深い報告が続くものと思われます。
・ちなみに、まだ発見から10年しかたっていませんが、この分野の創薬をリードするBiogen社は、既にC9orf72遺伝子由来の異常蛋白質の生成を阻害するためのアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤(BIIB078)を開発し、第1相試験を開始しています。この結果も注目されるところです
文献1:Cell. 2021 Jan 15:S0092-8674(20)31747-5. doi: 10.1016/j.cell.2020.12.025. Online ahead of print.
文献2:Nat Neurosci. 2015 Sep;18(9):1226-9. doi: 10.1038/nn.4085.
文献3:Human Molecular Genetics, Volume 24, Issue 9, 1 May 2015, Pages 2426–2441,
文献4:Cell Rep. 2017 Jun 13;19(11):2244-2256. doi: 10.1016/j.celrep.2017.05.056.
文献5:Science. 2019 Feb 15;363(6428):eaav2606. doi: 10.1126/science.aav2606.
文献6:Nat Neurosci. 2019 Jun;22(6):851-862. doi: 10.1038/s41593-019-0397-0. Epub 2019 May 13. -
今年も1年ありがとうございました
・今年も残すところあとわずかとなりましたが、皆様体調に御変わりなどありませんでしょうか?
・本年一年間いろいろなことがありましたが、お世話になりました皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。
・勉強会については今年は新たに専攻医の先生4名を迎え、全面的に遠隔形式に移行し、これまでできていたちょっとした議論などがなかなかできずリモートの限界を感じています。一方で学会などはオンデマンドなどでいろいろな講演をじっくりと勉強できたのはとても良かったと思います(このスタイルはできれば残してほしいです)。
・来年はこの状況が一刻も早く収束することを願います。今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。
・皆様にとって来年が幸多き一年でありますよう、祈念いたします。
令和2年12月31日
石東病院
院長 安田 英彰 -
残念なニュース
・非常に期待され、個人的にも期待していたBrainStorm社の自家間葉系幹細胞移植であるNurOwn細胞の第3相試験ですが、同社の11月17日付press releaseにより主要評価項目を達成できなかったことが公表されました。
・189名のALS患者を対象に行われたこの第3相試験の主要評価項目はALSFRS-Rの変化率が治療開始後に治療開始前と比較して1.25点/月以上の改善度を示した反応群の割合でした。
・NurOwn投与群では34.7%、プラセボ群では27.7%で統計的有意差はみられませんでした。
・副次評価項目の28週間でのALSFRS-Rの変化量はNurOwn群 -5.52点、プラセボ群 -5.88点でこれも有意差なしでした。
・その他サブグループではどうなるかということも掲載されていましたが、事前に計画されていた層別化であればいいのですが、結果がでてから都合の良いようにサブグループを選んで、検定を行うことは禁忌ですので、触れないようにしておきます。
・髄液中の神経栄養因子などのマーカーの有意な上昇と神経炎症に関わるマーカーの有意な低下は観察された(プラセボ群では観察されなかった)とのことです
・再生医療関連のALS臨床試験としては、まだ第2相以前ですが同種幹細胞由来アストロサイトの移植(AstroRx)、Mayoクリニックなどで行われている自家脂肪組織由来間葉系幹細胞移植などが進行中です。NurOwn細胞は幹細胞移植のトップランナーだっただけに、残念度が大きいです。
・孤発性ALSに関しては、Ionis社のION541(ataxin-2 mRNAに対するアンチセンス・オリゴヌクレオチド製剤)の臨床試験など期待できる材料もありますので、今後の進展を待ちたいところです
引用元
https://ir.brainstorm-cell.com/2020-11-17-BrainStorm-Announces-Topline-Results-from-NurOwn-R-Phase-3-ALS-Study -
Muse細胞の話題とか
・ここ最近メディア上でもニュースになりましたが、岡山大学の研究チームがMuse細胞をSOD1変異ALSモデルマウスに移植して治療的効果がみられたことを10月13日付のScientific Reports誌に公表しました(Sci Rep. 2020 Oct 13;10(1):17102)。
・何が素晴らしいかというと、静注で中枢神経に到達しているところです。現在第3相試験が行われている自家間葉系幹細胞であるBrainstorm社のNurOwn細胞は髄腔内投与(くも膜下腔内投与)となっていますが、これはおそらく以前の当ブログでも触れたように静注すると肺にひっかかって、中枢神経まで到達しないからだと思われます。
・ですので、これまでの慣習では間葉系幹細胞については、腰椎穿刺をして、髄腔内カテーテルから注入というのが筋でした。
・Muse細胞は優れた遊走能を発揮して中枢神経に到達しているため、非侵襲的な幹細胞移植が可能となる可能性があり、期待がもてるものです。
・間葉系幹細胞といえば、10月19日付のNeurological Research誌に中国の研究グループが公表した論文(Neurol Res. 2020 Oct 19:1-11)に、ヒト臍帯間葉系幹細胞由来運動神経細胞(human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived motor neurons)という文字があり、まじか、となりました。
・これも以前触れたことですが、中胚葉系といわれる間葉系幹細胞でも外胚葉系細胞に分化しうるということが報告されているわけですが、ここまで明示的に間葉系幹細胞由来の神経細胞という文字をみたことがなかったので衝撃でした。技術的背景は気になるところです。
・あと面白いなと思ったのは、フランスのソルボンヌ大学の研究グループが11月号のNature Neuroscience誌に掲載した、末梢のマクロファージを修飾すると、ミクログリアの活性に影響し、神経保護作用を発揮する形態に変化させうるという報告(Nat Neurosci. 2020 Nov;23(11):1339-1351.)でした。
・大学で元論文をゲットしようと思ったのですが、経費削減のためかNature Neuroscience誌にアクセス権がなく、どのようにマクロファージを修飾したのかよくわからなかったのが心残りですが、末梢の免疫系細胞を加工することで中枢神経の神経変性過程に影響を及ぼしうるというのはとても興味深い報告でした。
・あとは10月3日付のCell誌に掲載されたTDP-43蛋白症の病態機序についての報告も面白いものでした。TDP-43はミトコンドリアに侵入し、ミトコンドリアの透過性遷移孔を介したDNA放出を引き起こし、細胞質のDNAセンサーであるcGAS(cyclic guanosine monophosphate-AMP synthase)がそれを探知し、炎症反応を誘発するというものでした。cGASや、その下流経路の存在する物質を阻害するとNF-κBなどの炎症促進性サイトカイン産生が抑制されており、治療的観点からも注目すべきものと思われます。